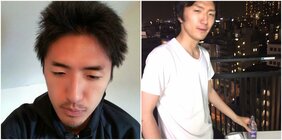実感できない「自殺対策基本法」の力
小林 本書のタイトル通り、近年、子どもの自殺は増え続けているんですよね。まずはその概要を少し教えてください。渋井さんはいつからこのテーマを追いかけているんですか?
渋井 僕が子どもの自殺を取材し始めたのは1990年代後半です。最初は家出少女や援助交際をしている子の取材から入りました。すると、自傷行為をしたり自殺願望を持っている子が6割以上もいる。当時はまだネットにもそういう情報が少なかったこともあり、あるとき、ネット掲示板で見かけた「死にたいと思っている、あるいは自傷行為をしている普通の子」の声も追いかけるようになりました。
日本全体で最も自殺者数が多かったのは2003年で、約3万4000人でした。1998年のバブル崩壊時に、男性の自殺者が1年間で約8000人も増えました。年間自殺者3万人台が2011年まで続き、以降は減少傾向になっています。そもそもなぜ3万人になってしまったのか、そしてなぜ減少してきたのかというのは、誰もきちんと検証してないので要因がはっきりわからないんです。ただ1つ言えるのは、2006 年に自殺対策基本法ができたことが一因だと思います。
小林 自殺対策基本法ってどんなものなんですか?
渋井 それまで、行政として自殺対策の担当部署が定まっていなかったので、自殺を個人の問題ではなく、社会の問題として捉えた基本法を作って管轄を明確にし、社会で取り組むべき施策としたのです。
小林 自殺したい人あるあるなんですけど、私の経験ではまず「いのちの電話」がぜんぜんつながらない! 特に東京とか都市部は全然つながらなくて、地方の番号にかけてました。
渋井 本当につながらないんですよね。ちなみに、いのちの電話は民間の社会福祉法人やNPO法人が運営してるんです。
小林 そうなんですか⁉ LINE相談の「生きづらびっと」も使ったことがあるのですが私には合わなかったのか、話を聞いてもらったと、感じることができませんでした。自殺対策基本法ができても、私自身、4回ほど自殺を試みているので、効果の程が分かりません。
渋井 当事者としては法律の力を実感しづらいですよね。