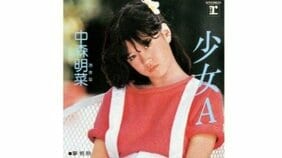衝動的なケースも
子どもの自殺者数が過去最多となった。
厚労省によると、昨年(2024年)1年間で、全国の自殺者数は2万320人(男性1万3801人、女性6519人)と前年から1517人減少し、1978年の統計開始以降、2番目に少ない人数となった。
その一方で、小中高生は529人と前年から16人増加し、統計を始めた1980年以降、最も多い数字となった。内訳は小学生が15人、中学生が163人、高校生が351人だった。
小中高生の自殺の動機として最も多かったのが、「学校問題」。次いで「健康問題」「家庭問題」という結果となった。
子どもが自ら命を絶つ選択をしてしまう背景について、精神保健福祉士の石井綾華氏に話を聞いた。
「大人にとっては気にも留めないささやかな内容でも、子どもからすると非常につらい物事に捉えていることが多くあります。特に自殺を選択する子どもの多くは、『こんなこと相談したら迷惑かな』と一人で抱え込んでしまう傾向があり、大人に知られないように悩みを隠しながら深刻な精神状態に陥ってしまうのが特徴です。特に家庭や学校での居場所が感じられないと、なおさらその傾向は強まります」(石井氏、以下同)
さらに、子どもの自殺は必ずしも長期的な悩みの末に起こるとは限らず、衝動的なケースも多いと石井氏は指摘する。その影響の一つがSNSだ。
「最近では、学校内のいじめだけでなく、SNS上での誹謗中傷や無視といった『ネットいじめ』が増えています。またSNS上で友達の“楽しそうな投稿”を見ることで、『自分だけが上手くいってない』と孤独を感じやすかったりなど、こうした希死念慮を煽る情報に触れて衝動的に行動に走る危険性もあります」
一方、SNSは孤独感を和らげ悩みを共有する相談窓口としての役割も担っており、「上手く活用していくことが大切です」と石井氏は言う。