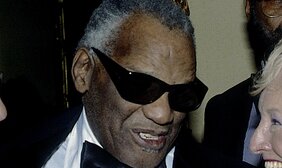なぜベートーベンの音楽に共感できるのか?
またベートーベンは芸術と同じくらい、正義や品性、そして徳の力も信じていました。
そのためベートーベンの音楽を聴いていると、「そんなことでくよくよしないで、もっとしっかり生きなさい」と、活を入れられるように感じる時があるぐらいです。でもそれは苦しみを乗り越えたベートーベンなりの激励の仕方なのかもしれません。
このように強烈な希望のエネルギーが込められている一方で、ベートーベンは人の弱さ、そして苦しみというものを理解していました。それは「緩徐楽章」と呼ばれるゆっくりとした楽章によく表れています。
おそらくベートーベンは、優しさを素直に表すことはほとんどなかったのではないかと思います。ベートーベンはそういう意味ではかなり不器用なタイプでした。しかし、彼は深い優しさを持った人物でした。
そうした優しさはピアノソナタ第8番「悲愴」やピアノ協奏曲第5番「皇帝」、交響曲第9番の第3楽章の緩徐楽章で聴くことができます。心の内側へと、深く深く入り込んでいくような音楽で、優しく聴き手の心に寄り添ってくれます。
大きな希望が外側へ向かうエネルギーとするならば、この優しさは内側へと向かうエネルギーです。そしてここに、ベートーベンの偉大さの秘密があります。内面的な感情から外面的な感情まで、その感情の幅がものすごく広いのです。
だから多くの人々がベートーベンの音楽に共感します。ベートーベンの音楽が現代人の心に共感します。そのようにして多くの人々の心をとらえるのです。
ベートーベンは50歳になってから「ミサ・ソレムニス」と「交響曲第9番」という大作を完成させます。その後、大作は作らず、「弦楽四重奏曲」を続けて作ります。
その「弦楽四重奏曲」に耳を傾けると、ベートーベンが芸術家としての使命を果たしたこと、そして耳が聞こえない自分との戦いがようやく終わったのだ、ということが聞こえてきます。
ベートーベンは耳が聞こえない自分を、そのまま受け入れたのでしょう。そこには和解のようなものが感じられます。心の安らぎが訪れたことが感じられます。
そうした音楽の心に耳を澄ませると、自然に涙がこぼれてきます。そうして芸術家としての使命を果たしてくれたベートーベンへの感謝の思いが沸き起こってくるのです。
文/車田和寿