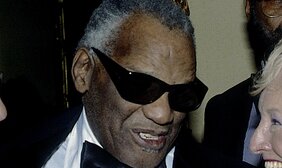音楽に渦巻く強く前向きなエネルギー
難聴を境にベートーベンの人柄はより気難しいものへと変わりました。耳が聞こえないため、コミュニケーションは筆談を使った限定的なものとなります。
自分の声が聞こえないため、その話し方は人々にさらにぶっきらぼうになります。そして時には荒々しい印象も与えたかもしれません。
一方で、ベートーベンの音楽は、耳が聞こえなくなるにつれて、より雄弁になっていきました。ベートーベンは自分が言いたかったことを音楽の中で雄弁に語ったのです。
ですからベートーベンの音楽には様々な想いが残されています。そうした想いに耳を澄ませると、彼が決して人前では見せることがなかった姿が少しずつ見えてきます。
ベートーベンはハイリゲンシュタットの遺書で自殺を考えたと告白しています。しかし彼は生きる決断をしました。その理由も遺書に記されています。それは芸術のためでした。
ベートーベンは芸術家として音楽を世に残すことが自分の使命だと考えていました。その使命を果たすまでは、どんなにつらくとも死ぬわけにはいかなかったのです。
現在、「芸術」という言葉は幅広く使われています。「芸術とは何か」を知りたければ、ベートーベンにとっての芸術がどのようなものだったのかを知る必要があります。
ベートーベンにとっての芸術、そして音楽とは、耳が聞こえないという苦しみを抱えながらも、生きていくほど価値があるものでした。
だからベートーベンの音楽の中では、彼の信じたものが表現されています。
彼が信じたもの、それは「希望」であり、「喜び」でした。
ベートーベンの作品の中でもとりわけ有名な交響曲第5番は、「運命」という名前で親しまれています。
「ジャジャジャジャーン」という衝撃的な出だしで始まるその曲は、恐怖や不安といった気持ちを聴衆に伝えます。
続く第2楽章では、生きるための希望というものが提示されるのです。しかし多くの人が人生で経験したことがあるように、その希望をすぐに信じることはできません。そこには疑念があります。ですが、そのような葛藤を乗り越えて最後に大きな希望が勝利するのです。
ベートーベンは音楽で、人間にとって不変のドラマのような、大きな理念を描こうとしました。同時期に書かれた交響曲第6番「田園」や交響曲第7番、そして「第九」という愛称で親しまれている交響曲第9番でもそのような大きな理念が描かれています。
それらの音楽には強く前向きなエネルギーが宿っています。そうしてベートーベンはその音楽で聴衆にたくさんのエネルギーを分けてくれるのです。