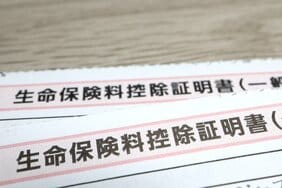投資は「手段」であって「目的」ではない
ハーバード大学の「Harvard Study of Adult Development」(1938年開始、現在も継続中)は、人間の幸福について最も長期間かつ包括的なデータを提供している。現在の研究責任者であるロバート・ウォルディンガー教授による2015年のTEDトーク「What makes a good life? Lessons from the longest study on happiness」では、年収や社会的地位よりも人間関係の質が人生の満足度を決定する最も重要な要素であることが示されている。
この研究では、「お金そのもの」を目的とする人よりも、「お金を通じて実現したいこと」を目的とする人のほうが、長期的な満足度が高いことが示されている。
投資を始めた当初の私の目的は「お金を得ること」だった。しかし投資を続けていくうちに、その目的は少しずつ変化していった。現在では「社会に貢献する活動を、経済的な心配なくできること」が目的になっている。
お金は人生の目的ではなく、あくまで手段だということ。インデックス投資で資産形成ができたことの最大の価値は、手間とお金の心配から解放され、本当に大切なことに時間とエネルギーを使えるようになることだ。家族との時間、健康、趣味、社会貢献など、人生にはお金以上に価値あるものがたくさんある。
実際に1億円を超えたあたりで「これだけあれば、今後十分に生活できる」と気づいた。それからは目標を「3億円の資産形成」から「1億円の資産を安全に維持しながら社会貢献する」に変更した。心の豊かさと経済的な豊かさのバランスを取る視点が大切だと思っている。
インデックス投資は割とロジックがしっかりしている。過去の膨大なデータに裏付けられ、多くの学術研究でも支持されている堅実な投資法だ。これはとても頼もしく、心強いものであるが、時々「原理主義者」のような人物にお会いすることがある。「インデックス投資こそが最強!」とばかりに、他の投資家を攻撃したりケンカをふっかけたりするような困った人だ。
先日もXで、ある個別株投資家の投稿に対して「その投資法は間違っている。インデックス投資以外はすべてギャンブルだ」といった厳しいリプライを送っている人を見かけた。投稿者は自分なりに企業分析をして、楽しみながら投資をしているだけなのに、なぜそこまで攻撃的になる必要があるのだろうか。
市場の懐は深い。短期・長期、インデックス・アクティブ、バリュー・グロース、デイトレードからバイ&ホールドまで、さまざまな異なる投資法でリターンをあげることができる。たとえば、短期トレーダーが市場の非効率性を利用して利益を得ることもあれば、長期のバリュー投資家が割安株を発掘して大きなリターンを得ることもある(私にはできなかったが)。成長株投資家がテクノロジー企業の将来性に賭けて成功することもあれば、配当株投資家が安定した配当収入を得て満足することもある。
重要なのは、これらの投資法は再現性や効率性は異なるものの、それぞれ異なる市場参加者のニーズに応えているということだ。退職を間近に控えた60歳の投資家と、資産形成をこれから始める20歳の投資家では、求めるものが違って当然だ。また、投資にかけられる時間や知識、リスク許容度も人それぞれ異なる。まるで、和食、洋食、中華、イタリアンなど、さまざまな料理が存在し、それぞれの味を求める人がいるのと同じようなものだ。
しかし、お金を増やすという根本的な目的は同じである。その手法の正しさを競うものではないし、派閥を作って勢力を拡大するようなものでもない。投資の世界で「宗教戦争」を起こす必要などまったくないのだ。