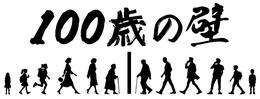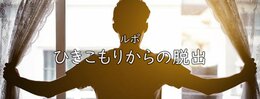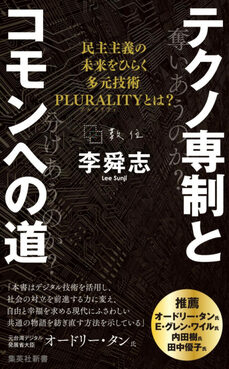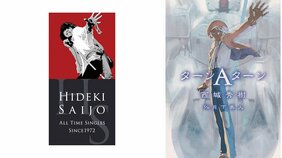QVならトランプは大統領にならなかった?
さきほども指摘したように、ひとり1票のシステムでは、ふたりの候補者のうちマシな方を選ばなければいけなくなることがある。
その結果、2016年のアメリカ大統領選のように、他の有力な候補が勝ったら大変なことになるという不安が循環して全員が嫌っている候補が勝つ可能性が生まれる。
ひとり1票のシステムだと、候補者Aを支持する票と、対立する候補者Bを支持しないために仕方なく候補者Aに投じられる票が、同じ1票としてカウントされてしまう。
そこで、候補者を支持するためにも支持しないためにも票を投じることができて、複数の候補者にボイスクレジットの予算内で好きなだけ支持票や不支持票を投じられるQVシステムを考えてみよう。
票の価格は2次関数的に変動するので、自分のクレジットを支持する候補者への投票と対立する候補者への不支持票に分ける方が、支持する候補者だけにクレジットを使うよりもコストが安く済む(たとえば候補者Aを支持する票と、候補者Aを支持する8票+候補者Bを支持しない6票はどちらも100クレジット消費する)。
その場合2016年のアメリカ大統領選挙はどうなるか? トランプが当選しないようにするためだけにヒラリーを支持しようとしている投票者は、トランプに対する不支持をさらに強く表明したいと考えるようになる。
反対に、ヒラリーだけは避けたいと考える人も、ヒラリーに対する不支持をさらに強く表明する。
今までのひとり1票制度では、「トランプだけは嫌だ」「ヒラリーだけは嫌だ」という動機だけで、投票者はなけなしの1票をどちらかに投票していた。QVの場合、支持票と不支持票を複数投票できるので、戦略投票は打ち消しあい、広く嫌われているふたりの候補者が沈んでいく。その結果、ふたりほど嫌われていない候補者が浮上する。
ワイルたちのシミュレーションによると、2016年のアメリカ大統領選挙に向けた予備選挙でQVが導入されていれば、極端な政治的見解が排除されるため、穏健派とされていた共和党の候補が勝っていた可能性が一番高い。トランプは全候補者の中で最下位になっていた。
同様に、ワイマル共和国において共産党への忌避感がナチスの躍進を招いたのだとしたら、
QVが導入されていた場合、ヒトラーが政権を握ることはなかったかもしれない。
脚注
*1 以上はポズナー&ワイル『ラディカル・マーケット』の記述だが、「ナチ政権の成立にとって決定的だったのは、大統領個人によるヒトラーの首相任命であり、大統領官邸周辺のごくわずかな『奸臣』たちの動きであろう」と歴史学者の原田昌博は指摘する。ヒトラーが首相に任命されたのは多数決だけが原因ではないのだ。
そもそも大統領によってヒトラーが首相に任命されたのは、ナチズム運動が、多くの人々の支持を集め大衆的な運動へと発展していたからであった。ナチスは社会を「敵」と「味方」に分け、敵を徹底的に非難する一方で、民族共同体の理想を強調することで、世界恐慌の影響や共和国への不満を抱える人々の支持を集めていった。
このように「敵/味方」の単純な二元論を用い、「敵」を徹底的に攻撃することで支持を集めていったナチスのような動きを食い止めるには、投票だけでなく、書籍で取り上げたさまざまな多元的テクノロジーを駆使しなくてはならないだろう。
同*1 原田昌博『ナチズム前夜 ワイマル共和国と政治的暴力』集英社新書、2024年、361-362頁。
*2 エリック・ポズナー&グレン・ワイル、安田洋祐監訳『ラディカル・マーケット 脱・私有財産の世紀』東洋経済新報社、2020年、149-150頁。
*3 ポズナー&ワイル、同前、156頁。
*4 ポズナー&ワイル、同前、160頁。
*5 QVがなぜ平方根を取るのかについては次の論文を参照。Steven P. Lalley and E. Glen Weyl, “Quadratic Voting: How Mechanism Design Can Radicalize Democracy,” AEA Papers and Proceedings, May 2018.
またこの論文でも言及されているが、QVは経済学者のデニス・ミュラーとチャールズ・レインの投票理論marginal pivotalityを下敷きにしているため、自分の投票によって結果が変わる可能性を投票の動機とするような、合理的な有権者でなければうまく機能しない。そのため、本格的な政治改革のためには、QVだけでなく本書で取り上げたようなさまざまな制度およびテクノロジーの改革も合わせて必要となるだろう。
写真/shutterstock