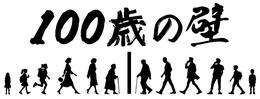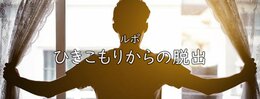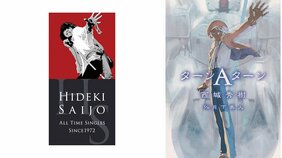投票が抱える問題のまとめ
悪しき候補者が逆説的に勝つ。多数決を繰り返すと独裁体制が生まれる。少数者の権利が守られず、多数派が支配している。そして、民主主義では見識の高い人の意見が無視される傾向にある。
すべては、現行の投票制度では人々の要求や関心の度合いも、一部の有権者の優れた知見や経験も反映されないことに原因がある。
要求も関心もより強い人に資源を割り当て、特別な才能や洞察を示した人に報いる良い方法がある。それが市場である*3。
QV─投票とオークション
市場と言うと「金権政治を肯定するのか」と叱られそうだがちょっと待ってほしい。たとえば選好の強さを競うオークションの背景にある考え方は、「対象の財を最高額入札者に配分すること」ではない。
そうではなく、「自分の行動が他人に課すコストに等しい金額を個々人が支払わなければいけない」ということだ。
私的財の標準的なオークションでは、私が落札すると別の入札者が財を手に入れられないため、落札した最高額入札者は、落札できなかった第2位の入札者の入札額を支払わなければいけない。
この点についてE・グレン・ワイルは次のように説明する。
あなたが自分の車を運転していて誰かにぶつかったら、相手に与えたケガ、痛み、苦痛に対して補償をすることが法律で義務づけられている。
それと同じように、投票では、集合的決定が行われる国民投票(あるいは他の種類の選挙)で負けた人にあなたが与えた損害を補償しなければいけない。
あなたが支払う金額は、あなたの投票によって負けた市民が選好していた別の結果になっていたら、その人たちが獲得していたであろう価値に等しくなる*4。
たとえば発電所は低コストの電力を供給することで街のすべての住民に便益を与えるが、汚染も排出する。発電所の便益は、住民が電力に支払う価格に十分に反映されているものの、汚染によって生じる損害は不確実である。
健康被害が起こる可能性もあるし、悪臭も発生する。政府が規制することもできるが、規制が厳格であればあるほど、汚染量は減るが電気代は上がる。そうすると、人々が汚染のことをどれだけ気にしているかが問題になる。
この問題に答えを出すためにひとり1票の投票を実施するとしよう。そうするとたちまち多数派の専制が生まれる。というのも、ほとんどの人は汚染のことをそれほど気にしていないからだ。
しかし少数者の中には、たとえば喘息の患者など、汚染が死活問題の人もいるはずである。極端に言うと、現行のひとり1票のシステムだと、「汚染はどうしても嫌だ」という人がひとり、「どっちでもいいよ」という人がふたりいた場合、後者が勝ってしまうのだ。
したがって、街の全員の全体的な幸福を考えるのであれば、ひとり1票ではなく、少数者の選好の強さが、多数者の選好の弱さを上回っているかどうかを判断する方法が必要になる。
もちろん、単に選好の強さを聞いただけでは、各々が「100万!」「100億!」と好き勝手に言うだけである。そのため選好の度合いを強くすることに対して、「自分の投票が他人に課すコスト」の支払いを課さなければならない。
公共財に影響を与える個人が支払うべき金額は、その人が持つ影響力の強さの度合いに比例するのではなく、その2乗に比例するべきだとされる*5。
この選考の度合いを反映する投票制システムを、グレン・ワイルは二次の投票(Quadratic Voting, QV)と呼ぶ。