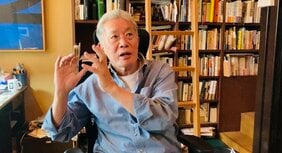SNSの脱構築
以上のメカニズムを活用すれば、既存のSNSで生じがちな対立を、対立の構図そのものをずらすことによって緩和することもできるだろう。
それをフランスの哲学者ジャック・デリダにならって「SNSの脱構築」と呼びたい。脱構築とは、かなりかみ砕いて言うと、敵と味方、善と悪のような二項対立をずらし、相対化することで、意味や解釈の多義性を明らかにすることである。
たとえばSNS上でしばしば見られるフェミニズムと反フェミニズムの対立を例に挙げよう*3。あなたは、女性差別はけっして許されるものではなく、フェミニズムの方に理があると考えるとする。
そのため、ミソジニー(女性嫌悪、女性蔑視)的な発言をする人たちのことは心底軽蔑している。こうして「われわれ」と「やつら」の対立図式が簡単に生まれる。
しかし差別的な発言をするアカウントの他のポストを見ていると、障害があったり、劣悪な状況の中で生きていたりするパターンがある。
他方、ミサンドリー(男性嫌悪、男性蔑視)的な傾向がある人たちも、たとえば性被害のトラウマが激しく、フラッシュバックで過剰に反応してしまう状況にあったり、彼女たち自身にも障害があったりする。
このように、SNS上のごく断片的な発言の背景を掘り下げていくと、「男/女」、「フェミニズム/反フェミニズム」の対立は、事態をきわめて単純化していることが理解できる。Pol.isのようなプラットフォームを使えば、この単純化を緩和することができるはずだ。
たとえば単純に「男/女」という対立軸ではなく、両者が共有するある種の「弱者性」は橋渡しをする意見を提供するだろう。あるいは、「男/女」だけでなく「強者/弱者」のような別の対立するグループの存在を可視化すれば、従来の「男/女」という境界線を流動化することが可能になる。
さきほどのPol.isの図を見ればわかるように、あるテーマに関して意見のグループは複数存在する。それぞれが異なる意見を持っていることは、グループが境界線によって閉じられていることではっきりと示されている。
しかしPol.isのテクノロジーでは、同時に、グループ同士をつなぐ橋を発見することもできる。グループは完全に開かれてはいないが、完全に閉じてもいない。そこには完全な敵も味方もおらず、ゆるやかな共感と合意の可能性がある。
以上のように、対立している集団の間に実は存在する共通点や共感するポイントを発見することによって、「敵/味方」という対立はずらされ、憎悪は緩和される。テクノロジーを使ってSNSを脱構築することは、他者や世界に対する認識を豊かで複雑なものに変えていくことにつながるだろう。