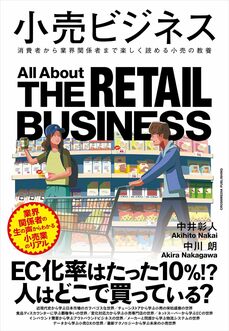コンビニが見出す新たな活路は…
ただ、出店余地がなくなったからと言って、本当にコンビニはこれ以上伸びないのかと言えば、実はそうではありません。現在は、大手3社のシェアが8割以上という寡占化が進んだコンビニ業界ですが、少し前までは大手が中堅コンビニの統合競争をする大再編期でした。
大手はシェア確保が最優先課題であったため、一部を除いて単一の店舗形態で店舗数を増やす競争をしてきたと言えます。今よくみかける、いわゆる各社の標準店舗を増やしていく場所はなくなってきつつあるのですが、別の店舗形態を開発することによって、また新たな出店余地を生み出すことは可能だということです。
コンビニ各社がDXを活用した無人店舗の実験をしているといったニュースを時折見かけると思うのですが、こうした取り組みは単にコストダウンを目的としているだけではなく、損益分岐点を下げることにより、これまでは出店できなかった小さい商圏にも店を出すことができるようになるからです。
例えば、オフィスビルにはこれまでもビルインのコンビニが1階などに入っていたと思いますが、小商圏型店舗なら1フロアごとに出店することも可能になるのです。そうなれば、確実にビル全体での売上は拡大することができる、といったイメージで、損益分岐点を下げれば、事業所内、過疎地、高齢化団地などなど、様々な出店余地が生まれてくるのです。
商圏のスキマを埋めるこの取り組みは「商圏の細分化」と言われますが、これだけでも、コンビニ市場は飽和したというにはまだ早いことは、わかっていただけるかと思います。
文/中井彰人 中川朗