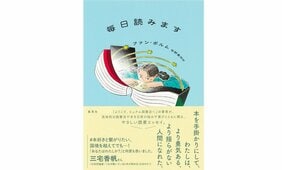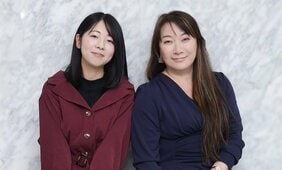創作する側の気持ちってどういうものなのか、
突き詰めて書いてみたかった
「この絵の中に入りたい」と思ったんです
── 篠田さんはこれまでアジアの国々を舞台にした作品を数多く手掛けられてきましたが、今回はハワイ島が舞台です。いつか小説で書いてみたいと思っていた、馴染みのある土地だったのでしょうか?
いえいえ、まったく。旅行は好きで、若い頃から南の島にはよく行っていたんですが、ハワイには特に関心を持っていませんでした。母がまだ元気だった頃、親孝行で海外旅行へ連れて行こうと思った時に、友達から「それなら絶対ハワイよ」と言われて、一緒にオアフ島へ行った一回きりです。今回、取材のために初めてハワイ島に行きました。
── では、なぜ今回ハワイ島を舞台に選ばれたのでしょうか。
実は何年間か認知症の母親の見守りをしていた時期があって、仕事と介護でくたびれ果てると、母を寝かせた後に車で片道一時間半かけて山中湖のリゾートホテルに出かけて朝帰ってくる、というのが唯一の息抜きでした。ある時、そのホテルの地下へ行ってみたらクリスチャン・ラッセンの絵があったんです。南の島の、海岸の風景を描いた絵でした。
── ラッセンは、南の島の海や海洋生物を題材にしたマリンアートの大家として知られる、ハワイ在住の画家ですね。イルカの絵は特に有名です。
バブル期の日本でものすごく流行った画家ですね。当時、アートにあまり興味がないような人たちも彼の版画を何十万円も出して買っていたんですが、専門家からは完全にスルーされる存在で、私自身も正直なところ、興味を惹かれることはありませんでした。でも、ホテルの地下で目にした瞬間、「この絵の中に入りたい」と思ったんですよ。この絵の中に入り込んで、現実に帰ってきたくないな、と……。当時、携帯の待ち受け画面を南の島の青い海とキラキラの空の写真に設定して、それをよく覗き込んでいました。母がいるので国内旅行すらもままならない中で、どこか遠くへ行きたいという願望の象徴が、南の島だったんです。そういった状況にラッセンの絵がぴったりハマって、ぼーっと見入ってしまった。自分がホテルで経験したその感覚を、小説にできないだろうかと思ったことがこの作品の出発点でした。
── 本作の主人公である有沢真由子も、同じ経験をしていますね。彼女は50歳の誕生日を迎えた日、熱海のホテルの地下でジャンピエール・ヴァレーズの絵と出会います。バブル期に人気を得たマリンアートの巨匠の作品を、彼女はかつて「鼻先で笑って黙殺していた」ものの、心を大きく動かされた。そして、ヴァレーズの価値を再検証するような書籍の企画を立ち上げます。「謎」に満ちた画家の足跡を追う、という主人公の動機づけとしてこれ以上ない入口だと感じたんですが、出発点には篠田さん自身の経験があったんですね。
そこが出発点ではあったんですが、ラッセンのモデル小説を書くつもりはありませんでしたし、そうはならないことが分かっていました。というのも、母とオアフ島へ遊びに行った時に、ラッセンみたいな絵が現地に山のようにあることを知ったんです。あの画風はオリジナルではなく、マリンアートというジャンルに属するもので、ラッセンは無数にいる画家の一人にすぎなかったんです。
── ラッセン本人ではなく、マリンアートというジャンルそのものへの興味が強かった?
そうですね。それと、マリンアートの画家はたくさんいる中で、なぜラッセンだけが日本で一人勝ちしたのか。こういう時って作り手の意図や売り手の戦略に目が行きがちですが、忘れてはいけないのが見る側、買う側の事情です。こういうものを見たいという人々の欲望が作り手を動かし、そこに作り手の本来の動機との齟齬が生じていく。美術市場のあり方や大衆性と芸術性のせめぎ合い、「売れてしまった画家」を取り巻くさまざまな欲望への興味から、ジャンピエール・ヴァレーズという画家の人物像が固まっていきました。
── 真由子という主人公にも強烈な実在感がありました。新聞社の社員としてかつてアート誌の編集に携わり、最年少の女性管理職として社内のアイコン的な存在であったけれども、いつからか周囲が自分を追い越していった。独身で子供はおらず、私生活でも仕事でも鬱屈を抱えていたところで……と。
新聞社勤務のちょっと知的でおしゃれで孤独なキャリア女性が、かつて一世を風靡した画家の謎を追う、という設定止まりキャラ止まりだと大人が読む小説にならないんですよね。彼女はどんな会社でどういうキャリアを積んできて、50歳になった今は組織のどこに位置してどういう仕事をしているのか。彼女の人生を綿密に作り上げて提示しないと、彼女がヴァレーズの絵画と出会った時の衝撃も伝わらないですし、その存在を追いかけていく説得力に欠けてしまうんです。