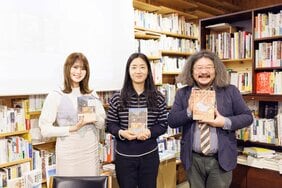「読者」というアイデンティティを自覚する
ソウルの小さな書店「ヒュナム洞書店」を舞台にした小説、『ようこそ、ヒュナム洞書店へ』が2024年の本屋大賞翻訳小説部門第1位に選ばれた韓国の作家・ファン・ボルムさん。この3月に、デビュー作である『毎日読みます』が日本で刊行されました(訳=牧野美加)。読書のための隙間時間の作り方からアンダーラインの引き方、時々のおすすめの本まで。実用的であると同時に、「人間にとって本とは何か」という根源的な問いに向き合う、珠玉の読書エッセイ集です。
新刊の刊行を記念して、文芸評論家の三宅香帆さんとの対談をお届けします。「労働と読書」の関係に切り込んだ三宅さんの『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』(集英社新書)は、本好きに勇気と示唆を与えるのみならず、読書という切り口で日本社会の構造や課題に迫る社会批評としても高い支持を得て、「新書大賞2025」に輝いています。
〝本オタク〟のお二人の初顔合わせとなる今回のオンライン対談。好きな本から韓国と日本の読書傾向の相違まで。三宅さんからファン・ボルムさんへ、たくさんの質問が投げかけられました。
通訳=延智美/構成=砂田明子
三宅 はじめまして。『毎日読みます』をとても楽しく拝読しました。実は私もデビュー作は読書エッセイ(『人生を狂わす名著50』ライツ社)で、好きな本をいろいろと紹介したんです。今回、ファン・ボルムさんと好きな作家や本がかぶっていることもわかり、共感しながら読みました。それからこの本には古今東西の作家と本が紹介されていて、ジャンルも文学からビジネス書まで多岐にわたっています。日本の作家もたくさん出てきますが、その一人が立花隆さんで、「ネコビル」(立花さんの事務所、20万冊以上の蔵書があった)に心奪われていると書かれています。私も憧れていて、見学に行ったことがあるんです。
ファン 私と同じような思いを持っていらっしゃるということで、より親しみを感じます。お会いできてうれしいです。
『人間失格』は韓国で根強い人気
三宅 ありがとうございます。まずお聞きしたいのは、ファンさんの本にはヘルマン・ヘッセはじめ、古典といわれるような作家や作品が出てきます。今の若い世代は古典と出会う機会が減っているような気がするのですが、どのようなきっかけで古典に出会われてきましたか。
ファン 今はどうかわからないのですが、私が高校生の頃は「推薦図書」があって、その中に、世界文学のいわゆる古典が入っていました。ですから高校生たちは読まずともタイトルだけ知っていたり、あるいはそのうちの何冊かを読んでみたりしていたのだと思います。私もそのうちの一人でした。
最近でも韓国には、古典文学を読んでいる層が一定数いるのではないかと感じています。というのは、小説のベストセラー100の中に、依然として古典が入っているんですね。たとえば太宰治の『人間失格』は根強い人気があります。
三宅 推薦図書というのは、国語の授業で先生に読みなさいと言われるとか、感想文を書きなさいと言われるような本なのでしょうか?
ファン 私の記憶では、青少年向けの推薦図書の目録がどこかに出回っていて、それを見ていたのだと思います。推薦図書を読みなさいと先生に言われることは、私の学生時代にはありませんでした。むしろ学校は、本を読んでいると怒られてしまうような雰囲気だったんです。そんな暇があったら勉強しなさい、と。
三宅 そういう中でファンさんが本を読むようになったのはなぜでしょうか?
ファン 私の場合は家族の影響です。4人家族のうち、両親も姉も本を読む人だったので、自然と本を読むようになりました。ただ学生時代は私も学校では読まず、主に家で読んでいましたね。
三宅 日本では、「古典を読む意味は何か?」「昔の本は読まなくてもいいのでは?」といった議論が定期的に起きるのですが、韓国ではどうですか?
ファン そのような議論を私は聞いたことがないですね。最近は本離れが進んでいるので、古典を読むべきか、という以前に、なぜ本を読まなくなっているかが多く語られているように感じます。
私自身は、この本にも書いたように、古典は読まないよりは読んだほうがいい、と考えています。長い年月に打ち克って私のもとに辿り着いた古典にはやはり、人間に対する本質的な理解が書かれていると思います。といっても、古典ばかり読むのは大変なので、古典を読んだら次は現代文学を読む、というふうにバランスをとっています。
なぜ男性は女性より本を読まないのか
三宅 私の問題意識とも重なるすごく興味深いお話です。韓国では最近「テキストヒップ(Text Hip、〝文字〟と〝素敵〟を組み合わせた造語)」という言葉が流行っているとか、若い世代が読書会をしているとか、先ほどお話に出ましたが『人間失格』がYouTubeをきっかけに売れているとかという話を聞くので、若い世代に読書が広がっているのかなと思っていたのですが、そうではなく、読書離れが進んでいるという認識があるんですね。
ファン 毎年発表される統計などによると、明らかに読書人口は減少しています。ですが、読書に関心を持っている若者たちは一定数いて、今言われたように造語が生まれたり、韓国には「ミリの書斎」という電子書籍プラットフォームがあるのですが、ここで一番本を読んでいる層は20代なんですね。ですから全体の傾向としては読書離れが進んでいるけれど、希望を持てる側面もあるというのが韓国の現状だと思います。
三宅 ちなみに若い世代と上の世代で、読書傾向に何か違いはありますか?
ファン 正確にはわかりませんが、最近、若い人は短い作品を好む傾向があるようです。韓国では本がどんどん薄くなっているんです。短編が多くなり、2、3ページの超短編小説も出てきています。薄い本は手にとりやすいですが、短い作品ばかりに親しむと、長編が読めなくなるのでは、と心配したりもします。一方、上の世代は長編に慣れていますから、短すぎる作品や薄い本は物足りないと感じる人がいるようです。
三宅 ファンさんの『ようこそ、ヒュナム洞書店へ』は、どのような読者層だったのでしょう。
ファン あの本は30代の女性が主人公で、大人たちの物語、それも疲れた大人たちの物語なので、読んでいる読者層は大人ばかりだろうと思っていたら、意外なことに中高生や小学生の読者もいて、たいへん驚かされました。でも一番多かったのは40代の女性です。韓国で最も本を読む層が、40代の女性なのです。
三宅 男性よりも女性のほうが本を読むのでしょうか?
ファン はい。男性より女性のほうがはるかに本を読んでいると思います。本にかぎらず、韓国では、文化生活全般に男性の姿が見えにくいのです。なぜだろうという話を、出版関係者の人たちもよくしています。
三宅 何か仮説は出ていますか?
ファン もちろん本を読む男性はいますし、文化生活を楽しんでいる男性もいるけれど、女性たちより少ないということです。では男性たちがどこに関心を向けているかといえば、どうすればお金をもっと稼げるのか。その点に集中しているのではないかという仮説はあります。
日本もそうかもしれませんが、今、韓国には、新自由主義社会の生きづらさを抱えている人が多いと思います。
三宅 私の『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』でも、新自由主義的な価値観が広まった時期と、読書離れが始まった時期とが重なるという分析をしています。韓国と共通する話なのだとわかり、興味深くお聞きしました。