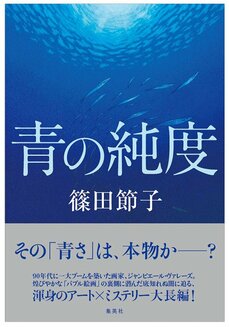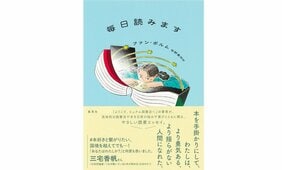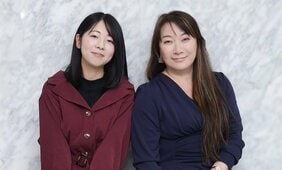美術館で鑑賞する絵と、家に飾りたい絵は違う
── バブル終了と共にブームが去り、「終わった画家」とされていたヴァレーズは、近年、日本での再評価が始まっていた。第一章では、バブル再来を思わせる展示即売会へと真由子が足を運び、今でも彼のプリント絵画が一枚数十万円から一〇〇万円を超えて販売されている現実を目にします。アートの価値を何も知らない庶民に高額で売りつけるのは詐欺ではないか、とかつて社会問題になった商法ですよね。当時のことはネガティブに語られることが多いですが、それまでは美術館に行って鑑賞するだけだったアートを、自分で所有して飾る、というムーブメントはここから始まったのではないか……という指摘が作中に出てきて、目を開かされました。
その売り方には私も否定的な印象を持っていたんですが、その頃絵を買ったという方にお目にかかったことで、イメージが変わりました。その方は、当時買った絵を今でも本当に大切にされていたんです。言ってしまえば、やたらケバい絵ですが、置き場所とライティングで馴染ませることで、絵を中心とした居心地のいい空間を作るというアイデアが湧きました。私も自分の部屋に置くのであれば、(ジョルジュ・)ルオーとか(ジェームズ・)アンソールではなくて、マリンアートを選ぶでしょうね。芸術的な評価はともかく、自分を心地よくしてくれるのは圧倒的に後者だなと思うんです。
── ヴァレーズは何者なのか、何が人々を惹きつけるのか。第一章で好奇心や疑問をめいっぱい搔き立てられた後の、第二章冒頭の展開に度肝を抜かれました。本人と連絡がつかないならば会いに行ってしまえばいい、と真由子は彼が住んでいるハワイ島に飛んでしまうんですね。
すごい行動力ですよね(笑)。その展開に持っていくにはどうしたらいいか、悩んでいたんですが、たまたまバブル時代に編集者をしていた女性とお会いして、即座に解決しました。「自分のおカネで行けばいいじゃないですか」と言われまして。当時の女性たちは、思い立ったら週末に海外、なんてことが当たり前だったんですね。さらに言えば、出版界も元気で、社員をばんばん海外出張させていたから、海外旅行が日常の延長でもあった時代ですね。現代を舞台に同じようなことはできませんから、勤続何年かのリフレッシュ休暇を使って旅費は自腹という設定にしましたが、行動力と腰の軽さは、この時代を知る人特有のものとなっているかもしれません。
── ハワイに飛んだ真由子は日本人コーディネーターのサポートで、ヴァレーズが住んでいる豪邸の所在地を知ります。アポなしで突撃するものの、彼は住んでいなかった。そればかりかだいぶ前にオーナーは代わっていて、引っ越していた。読者を驚かせるために、いきなり大きなカードを切ってみせた、という感覚だったのでしょうか?
自分としては、わりとサラッと出したつもりです(笑)。日本でのブームが終わって落ち目になった段階で、そんなお屋敷を持ち続けていられるわけないですから。じゃあどこへ行ったのか、真由子はどうやって本人に辿り着くのか。刑事でもないのに近所に聞き込みするのも変だし。どうしようかなと思いながら取材でハワイの高級住宅地をうろうろ歩き回ったことで、ひらめくものがありました。豪邸に住んでいる人がパーティをするとなれば、レストランのシェフに来てもらうようなこともあるだろうし、デリバリーもありかな、と。それなら近所でフードデリバリーをしている会社から、かつてその豪邸に住んでいたヴァレーズの情報をもらうこともできるはずだと考えました。
── その展開、印象的でした。その国のその街の、そのエリアのリアリティから生み出されたものだったんですね。
実際にその地に行ってみることで、初めて気づくことはものすごく多いです。海なんかも、自分の勝手な想像とはまったく違ったんですよ。南の島の海と言えば、インドネシアかマレーシアの海の景色や色が刷り込まれていたので、ハワイの海を見てみたら何だこれは、ここは日本海かい、と(笑)。彩度の低い穏やかな青色で、マリンアートで描かれているきらびやかな海の絵と、あまりにも乖離していたんですよね。この乖離はどういうことなんだろう、どう解釈したらいいんだろうというところから、当初予定していたお話の設定も微妙に変わっていきました。
言葉では表現できない永遠をどうやって閉じ込めていくか
── 真由子は自費出張の数日間で、なんとかしてヴァレーズの消息を摑まなければならないわけですが、通常のやり方では時間がかかってしまう。ハワイにいる日本人コミュニティのネットワークと繫がることで情報をゲットしていく、という展開に納得感がありました。物語のキーをなす人物のひとりが、ヴァレーズの妻であるミレです。一向に顔を出さないヴァレーズの代わりに、真由子と対面して交渉ごとを進めるんですが、彼女は日本人なんですよね。
その設定は最初から決めていました。一時期ニュースで騒がれていたんですが、贋作で詐欺を働いていたイラン人の画商がいました。その奥さんが、日本人だったんですよ。カモは日本人だから、その裏で奥さんが大活躍していたんです。ミレは書いていてすごく楽しかったですね。私好みの、胡散臭い人物なんです(笑)。
── ミレとの出会いを契機に、物語はぐんぐんスケールアップしていき、サスペンスも高まっていきます。そして、ハワイにおける日系人の問題にもフォーカスされていく。この問題は当初から取り上げる予定だったのでしょうか?
書くつもりではあったんですが、取材でハワイ島へ実際に行ったことで構想が大きく変わっていきました。まず驚かされたのは、故郷である日本への思いです。日系人の墓地に行ってみたところ、全ての墓石が西の海側、つまり海を隔てた日本を向いて建てられていたんですね。それから、ハワイの日系人たちは、サトウキビ労働者や開拓民としてやって来て、たいへんな苦労をされているんです。そのイメージがあって今でも貧困とまでは言わないけれども、白人に比べて決していい暮らしはしていない、というイメージを私は持っていました。ところがいくつかのデータを取り寄せたうえで、実際に現地を回りコーディネーターの方にお話を聞いてみたところ、ハワイの日系人は非常に教育程度が高く、しかも勤勉なので、良い仕事につき成功している例が多い。ハワイの社会の中でも、高い地位を占めていることを知って驚いたんです。ハワイの日系人に関して認識をあらためたことで、設定が大きく変わり、ストーリーに奥行きが出たかな、と思っています。
── ちなみに、ヴァレーズはダイバーでもあり、海に潜り海を内側から見ているからこそあの絵が描ける、と言われています。ダイビング関連の描写に関しても、取材をされたのでしょうか。
もともと泳ぐことが好きなので、自分の経験が生かせる部分もあるかなと思いつつ、ダイビングスクールに行ってスキンダイビングを体験してきました。一回だけですけどね。六メートルプールの底までういーんと潜っていく時のフィンの動かし方、浮上の仕方などは参考になりました。自分の身体を通した詳細な描写は、臨場感を出すのに欠かせません。
── そういった小さな描写、細部の展開のリアリティが、物語の大きな歯車をなめらかに動かしていくんでしょうね。絵に関してはどうでしょうか。ご自身でもお描きになるんですか?
昔は描いていましたね。高校、大学の頃は趣味で油絵なども描いていましたが、もう何十年間も絵筆は握っていないです。
── でも、かつて描かれていた。絵を描く際の気持ちの動きと、小説を書く際の気持ちの動きには通じる部分もあるのでしょうか。
明らかに繫がっていますね。絵筆を動かしている時、目に見えている部分以外のところにどれだけのものを閉じ込められるだろうかと考えています。言葉として記録されていくものの中に、言葉では表現できない永遠をどうやって閉じ込めていくか、というのは大きな課題です。
── ヴァレーズという画家の正体を追うミステリーである本作は、ものづくりの本質は何かという謎を追う物語でもあります。後者の謎にも、ご自身の実感と重なる部分があったんですね。
すごく印象的だった出来事があるんです。この三月に御年95歳になられた皆川博子さんのところにふらりと遊びに行ったのですが、お部屋にあったのは資料本がぎゅう詰めになった本棚と机とパソコン、軽いエッセイや講演でお茶を濁したりはしない、まさに現役の作家です。小説誌から注文を受けて連載しながら、次に書きたいものの構想に取りかかられている。注文があるからとか、収入とか名誉や評価が欲しいといった動機で書くわけではないんですよね。「あなただってそうでしょう? 書きたいから書くだけよね」とおっしゃっていて、本当にその通りだなと深く共感しました。創作するってどういうことか、創作する側の気持ちってどういうものなのか。そこを突き詰めてみたいという思いが、この小説を書き進めるうえでの原動力だったとそのとき気づきました。