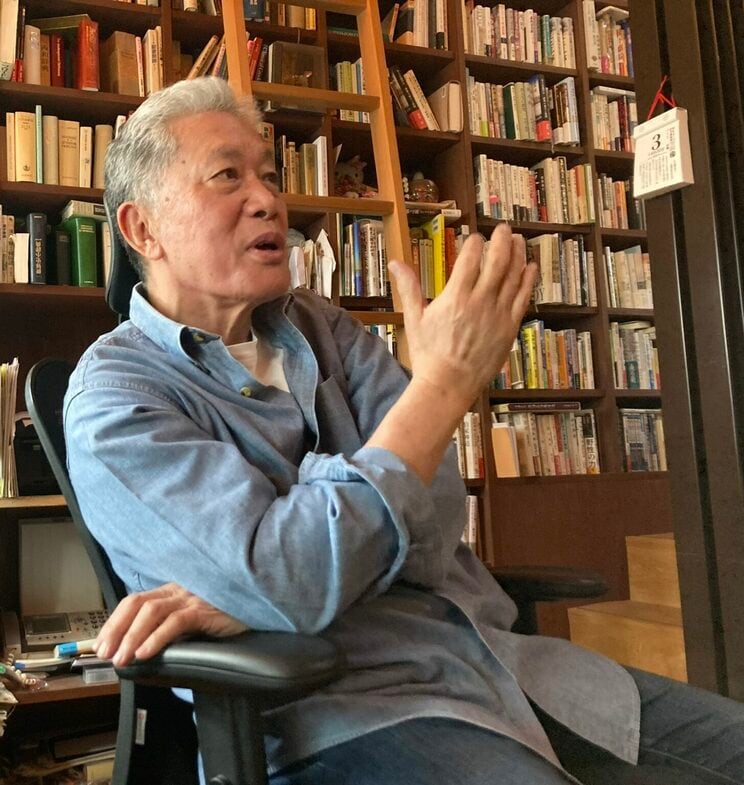「ためらい」を取り戻したい
内田 これは僕の個人的印象なんですけれども、欧米の社会には「仲裁」とか「調停」ということについて、あまり成熟した文化がないんじゃないかという気がします。どちらかが真でどちらかが偽か、どちらが善でどちらが悪かという二元論的な発想なので、どちらの言い分にもそれぞれ一理あるから、「どうですこの辺でナカとって」という裁量が働かない。
仲裁については、法社会学の川島武宜先生の『日本人の法意識』(岩波新書)という名著がありますけど、その中で川島先生は「日本人には真偽の判定をしないで、あいまいな調停に持ち込む文化がある」という話をしています。
例に上がっていたのが歌舞伎の「三人吉三廓初買」です。お嬢吉三とお坊吉三という盗賊が、夜鷹から奪った百両を巡って斬り合いになっている。そこに三人目の和尚吉三が現れて、まあ収めてくれと百両を五十両ずつに割り、「半分ずつでは御不満だろうから、俺の両手を斬って一本ずつ差し上げるので、それで収めてくれまいか」と提案する。これを聞いた二人が感動して、和尚吉三を兄貴分と頂いて義兄弟の契りを結ぶ……、という話なんです。
これは「仲裁」ということの本質に触れていると思うんです。仲裁人というのは、両方にとって同じぐらい不満な落としどころを見つけるだけでなく、自分も何かを犠牲に差し出さなければいけない。仲裁人は身銭を切らなきゃいけないんです。別にそんな義理もないのに。この不条理を呑み込んでもらわないと調停とか仲裁ということはできないんじゃないかと思います。
現在の国際紛争を見ていると、「うまい調停案を出す」という叡智的な課題にみんなが取り組んでいて、「自分が何を犠牲にすれば、同じ程度に不満な解にたどりつけるか」という仲裁の本質が理論化されていない気がするんですね。
李 たしかに。今のようなお話は、内田先生が2001年にまとめられた『ためらいの倫理学』(角川文庫)の冒頭にもありまして。
内田 みんな二元論に居着いて、真偽の判定にこだわり過ぎだと思ったんです。それよりは「決めかねてためらう」というのでいいじゃないか、と。
李 『ためらいの倫理学』は、僕が「もっと勉強したい、研究したい」と思うきっかけになった本なんです。先生はたとえばフェミニズムについて、フェミニズムにも反フェミニズムにも「どちらにも与しない」という態度を取っていらした。日本的な空気では「どちらかの側に立つ」というのが普通だと思うので、結構勇気が要ったと思うんです。先生はどうして、判断を留保する「ためらいの境地」に至ったのですか?
内田 どちらの言い分もよくわかるからでしょうね。フェミニズムの言い分はよくわかる。一方フェミニズムは「ちょっと正しすぎる」という反感を感じる人の気持ちもよくわかる。フェミニズムがめざしている「正しい目標」を実現するには、この「正しすぎることに対する反感」を解除しなければならない。そのためには「正しすぎる」過剰な部分はすこし抑制した方がいいんじゃないか。
フェミニズムってものすごく切れ味のいい社会理論ですからね、何でも切れちゃうんです。そして、人間って切れ味のいい論理的な利器を手にすると、つい「そこまでやらなくてもいいところ」まで切っちゃう。これも切れる、これも切れると。理論の過剰適用の誘惑に屈してしまう。
だから僕は「フェミニズムが間違っている」と言ったわけじゃないんです。「ちょっと我慢してください」と申し上げただけなんです。そんなに「正しさ」を振り回しすぎると、そのうちバックラッシュが来るから。フェミニズムに論破された人たちってやっぱり、屈辱感や敗北感を覚えるわけで、その「負けたことのトラウマ」はそのうち別の形で症状として回帰してくる。これは確かなんです。フェミニストが批判したパターナリズムはそのうち全然別の形をとって、より病的な形で回帰する可能性がある。だから、それはしないほうがいい、と。
そうではなく、あまり論争相手に屈辱を与えずに、相手の理論の毒性をゆっくりと時間をかけて希釈してゆく。その方が手間はかかるけれど、最終的には目標に近づけると思ったんです。でもね、正しいことを言っている人に向かって「その正しさをすこし抑制してくれませんか」と言ったって、そんな理屈通りませんよね。「正しいことを言っている人間に、正しいことをすこし控えてくれってどういう了見だ」ってフェミニストから猛攻撃をくらいました。
李 そうだったんですね。『ためらいの倫理学』は、対立が先鋭化している今こそ読むべき本だと思います。というのも今の若者って、人類史上初めての「マスメディアはあるけどマスコミが存在しない」、マスコミが力を失った時代に生きていると思うからです。