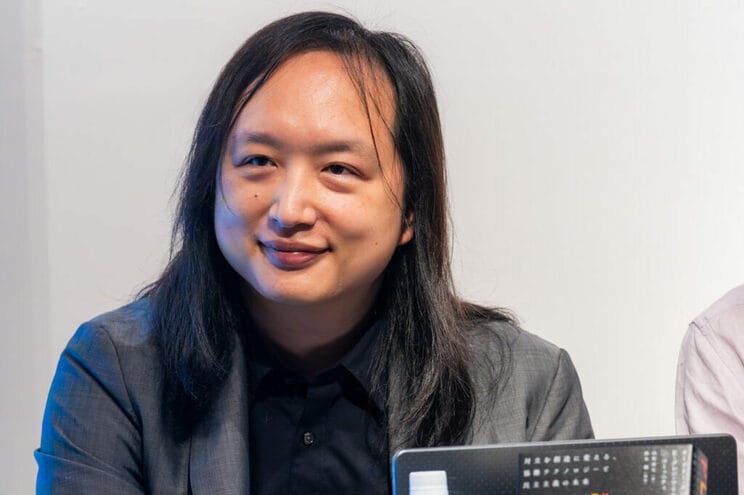ディストピア物語の「効用」とは
李 内田先生も書いていらっしゃったんですけど、テクノロジーに関するディストピア的な話っていっぱいあるんですよね。シンギュラリティを提唱しているレイ・カーツワイルの「AIが人智を超える」みたいなSFチックな話には乗れないですけど、テクノ専制や監視資本主義といった「いかにテクノロジーが未来を暗くしているか」という現実的な話も読んできました。
テクノロジーを全て捨て去ることはできないので、それをどう使うかを考えなくてはいけないと思っている時に、オードリー・タンたちの試みを発見したんです。
テクノロジーの未来を、単に楽観的に語るのではなくて、一回絶望を経由して、それでも明るい未来はあるかもしれないというビジョンに共感した。それが今回の本を書いたきっかけです。
内田 科学がもたらすディストピアを描くという伝統は、オルダス・ハクスリーの『すばらしい新世界』やジョージ・オーウェルの『1984』から始まって、アングロサクソンの文学的な伝統として確固として存在するわけです。
ディストピアを物語として描いて、娯楽として消費することができるというのは、ある種の健全さの証だと思うんです。監視社会ができる話であったり、核戦争で世界が滅びるSFとかって、無数に作られていますよね。1945年から80年間僕たちは「核戦争で世界が滅びる話」や「人間が機械に支配される話」を娯楽としてたっぷり消費してきているわけですけど、幸い核戦争は起きていないわけです。僕はディストピア物語はディストピアの到来を阻止する実際的な効果があったと思います。物語には強い現実変成力がありますから。
「破滅のリスクを回避したい」という素朴な願いに駆動されて、「このようにして世界は滅びる」という話を事細かに書く。すると、さすがに物語と同じ道筋をたどって世界を滅ぼすという人はなかなか出てこないと思うんです。もう物語に書かれて、娯楽として消費されているのと同じシナリオでディストピアをもたらしても、あまりに独創性がない。
せっかくならもっと違うことをやろうと思う。そうやって物語はディストピアの到来を先送りしてきた。僕はそんなふうに思っています。ただ現在の「テクノロジーがもたらすディストピア」については、これまでそういう物語がなかったんですよね。だから、どういうふうにディストピアが到来するのか、その道筋がよく見えない。よく見えないと阻止しようがない。