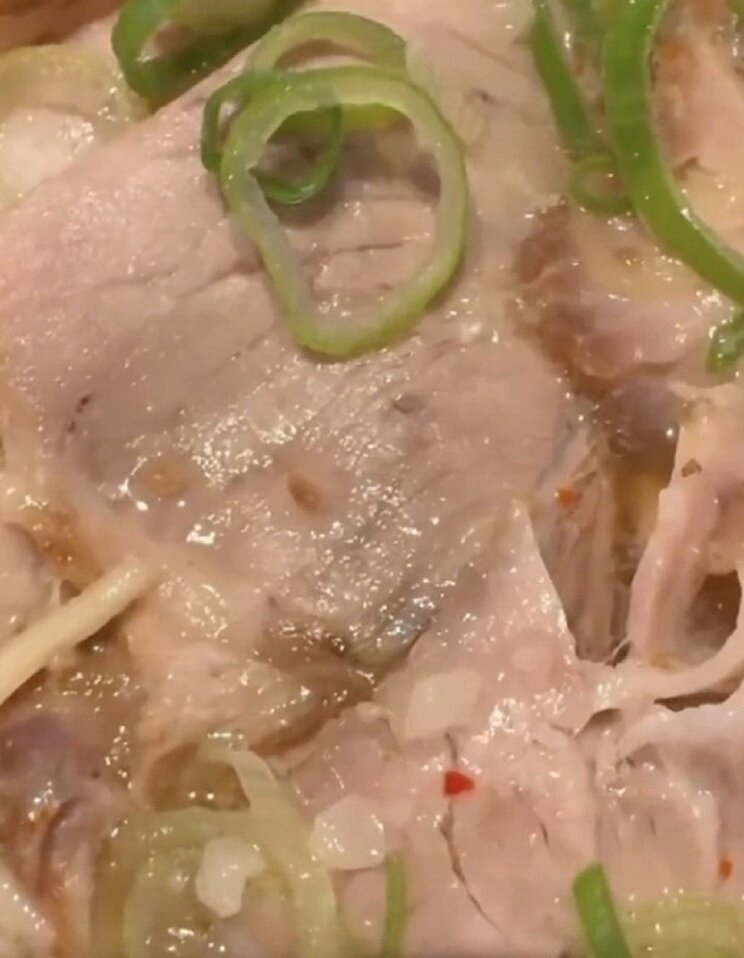炎上をきっかけに見直される衛生面
とはいえ、客側としてはまさかネズミが入っていたなんてということが立て続けに起きると、この国の飲食チェーンの衛生状態も心配になってしまう。
「立て続けに“起きている”というより、“可視化されている”と言った方が正確だと思います。もちろん、現在は昔と比べて現場のチェック体制も厳しくなっています。かつては企業側に『黙っていれば済むだろう』という空気もあったでしょう。今回のすき家の初期対応も、それに近い印象で、『ずいぶん放っておいたな』という印象を受けました。
とはいえ、『放っておいても良いことはない』と、企業側も少しずつ理解してきているのではないでしょうか。今では、炎上するくらいなら、むしろ先に公表してしまった方が良いという判断が主流になりつつあります」
多くの企業が情報を公表している中で、自社だけが隠していても結局は悪目立ちしてしまう。それならば、自分たちも公表した方が目立たず、傷も浅く済む……。そのような考え方に変わってきているのかもしれない。
「企業として『隠蔽すること』が非常に悪いことであるという認識も広がっており、特に食品を扱う企業では、何か起きたときのダメージが極めて大きくなります。だからこそ、問題が起きた際には、速やかに公表し、情報をつまびらかにし、必要があれば謝罪する。そうした適切な対応を取っていこうという流れが、いまのトレンドになっていると思います」
また、すき家は24時間営業をやめ、午前3時から午前4時の間、営業を休止して、店舗営業中に実施しづらい機器の裏側の清掃など、集中的に清掃作業を行う時間を確保することになった。
「清掃の時間を設けるようになったのは、評価すべきであり、やはりそこに、日本の飲食店のいわゆる“ブラック”な働き方の問題があったと考えられます。リーズナブルに美味しいものが楽しめるというのは、日本の飲食店の良いところです。
ただ、それを何が支えてきたかというと、従業員の厳しい労働環境や、無理のある賃金・労働体系がベースになっていたという点は見逃せません」
価格、美味しさ、スピード、接客…飲食店に求められるものは多い。中でも衛生面は消費者にとって重要なことの一つだ。とはいえ、飲食店も完璧ではない。異物混入があった飲食店がこれからどのようにして信頼回復をしていくのか見守っていきたい。
取材・文/千駄木雄大