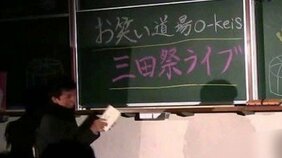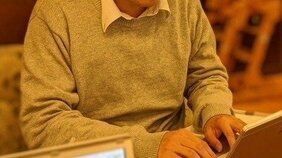令和ロマン・高比良くるまのコンサル的思考
大学のお笑いサークルという文脈で先ほど発言を紹介したラランドのサーヤと並んで引き合いに出されることが多いのが、2023年のM−1グランプリをわずか結成5年8か月で制し、さらには翌2024年も優勝して史上初の二連覇を達成した令和ロマンである。
慶應義塾大学のお笑いサークル出身の彼らは、M−1後のメディアでも大学サークルという枠組みをあえて持ち出しながら、お笑い業界に新たな軸を持ち込んでいる。
大学のお笑いサークルに出自があるから知的だというのはあまりにも短絡的だが、令和ロマンの髙比良くるまはそういったパブリックイメージを引き受けて様々な発信を行っている。
そして彼の行動からは、良い大学を出た人たちが身につけたいポータブルスキルとしての課題解決力、ファクトを捉えたうえでそれに対する解決策を見出すコンサル的な思考が随所に垣間見える。
僕は個々のネタじゃなくて「お笑い」自体を分析しているんです。いまはこういう要素が入ったネタが流行っているから、次はこういう人が出てくるんじゃないか、という。社会人的な思考なのかもしれません。漫才という商品を売りたいから、市場では何が流行っているのかリサーチしているだけなんです。
(「令和ロマン・くるま『ケムリさんは考えない葦だからね』ケムリ『パスカルでいうところの、人間の逆ね』」双葉社THE CHANGE、2023年9月28日)
決勝前に2015年からのM−1を全部、見返したんですよ。ヘッドフォンで、音をめっちゃでかくして。そうしたら、トップはウケていたときでも、やっぱり(ウケの)初速は遅い。なので、もっとお客さんの方を向いたネタにしなきゃダメだと思ったんです。
(「M−1王者は天才か努力家か…『決勝直前にM−1全部見返した』史上最速優勝・令和ロマンが語る“圧倒的努力”『だから異例のネタ選びをした』」Number Web、2024年4月7日)
「ケース面接」のようなネタ作り
コンサルの就職活動に、「ケース面接」と呼ばれる論理的に物事を考えるプロセスの精度を問う面接スタイルがある。
たとえば、「新幹線でコーヒーってどのくらい売れると思う?」と訊かれたなら、「東海道新幹線で」「コーヒーは1杯いくらくらい」と前提を限定し、「1日の新幹線の乗客数」を「東京駅からの1時間あたり発車本数」と「1車両あたりの最大乗客数」「新幹線1本あたりの乗車率」あたりから見積もり、そこに掛け合わせる「コーヒーの購入率」を「乗客のタイプ別」や「時間帯別」などから設定し……などといった話をしながらロジックを組み立てることが求められる(こうした方法は「フェルミ推定」と呼ばれる)。
当然正確な数値は出せないが、おおむねの桁がどのくらいの金額になるかくらいまで辿り着くことはできる。
くるまにとってM−1グランプリをはじめとする賞レースは「ケース面接の題材」のようなものであると言える。
条件を与えられた中で仮説を立てて、最適なアウトプットを出す。人を笑わせるという漠然としたゴールではなく、既定のルール内で審査員からの評価によって順位が明確に決まる賞レースがお笑いの中心となり、そういった催しの中で最も影響力のあるM−1グランプリはもはや年末の国民的行事になっている時代が今である。