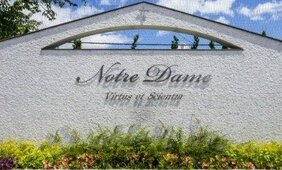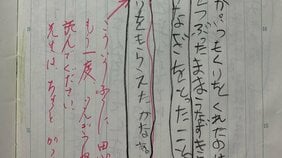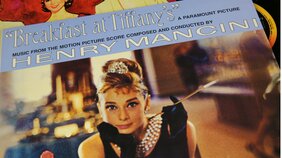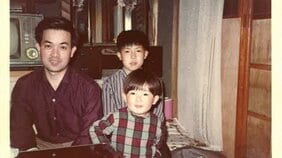イヤでも残業代を払いたくない文科省
――文科省は現在は残業が発生していないという認識なのでしょうか?
給特法に基づけば、校長が教員に残業を命じることができる4つの領域があります。いわゆる「超勤4項目」と呼ばれるもので、
①職員会議
②生徒の実習
③学校行事
④台風とか災害とかそういう緊急事態の時
これらの時だけは残業を命じることができるんです。でも、いまの教員の働き方を見ていると、これらの4項目によって残業が増えるケースはほとんどありません。むしろ、それ以外の業務で残業時間がどんどん増えていっているのが実情です。
「脱ゆとり教育」以降、授業時数はどんどん増やされ、「カリキュラムオーバーロード」とも呼ばれる今日。教員の持ち時間が増え、空き時間は減り、ただでさえ全ての業務を勤務時間内に収めるのがムリな状態です。
イヤでも残業代を払いたくない文科省はどうしたかといえば、翌日の授業準備や生徒指導や保護者対応、部活動などの業務を、教員による「自発的な業務」と解釈することで対応しました。
翌日の授業準備の時間や、生徒指導や保護者対応。いずれも教員のきわめて重要な仕事ですが、これらは全部、教員が自主的にやっている仕事なんだ。だから残業代は支払う必要がないんだ、と。
文科省のこうした認識が変わらなければ、いくら教職調整額を増やしたところで業務量も勤務時間も恐らく変わらないでしょう。
先述の髙橋哲教授は、4月25日に衆議院で行われた給特法の改正に関する文部科学委員会に参考人として招聘され、「実際に発生している教員の時間外勤務を、労働基準法上の労働時間として認めること。これが働き方改革の一丁目一番地 」と指摘しましたが、結局は文科省の法的に誤った認識が正されないまま衆議院を通ってしまいました。
給特法の改正議論の発端は、「学校における働き方改革」です。だとしたら、まずは「学校」とはどんな場所なのか、「教師」のしごととは何なのかを議論せざるを得ないのではないでしょうか。シンプルに言うならば、「学校」とは、地域から集ってきた様々な子どもたち一人ひとりの「人格の完成」を可能にする場所であり、「教師」とは、子ども一人ひとりの「人格の完成」に寄り添い支援するしごとだと、私は思います。
必要なのは、そのようなビジョンに基づき、教師の業務を精査することです。「人格の完成」には何が大事で、何が関係ない業務なのか。生徒指導、学校行事、部活動などは、学校教育においてどのような位置付けが相応しいのか。
一学級にどれくらいの生徒数が最適で、各授業の準備時間はどれくらいが適当なのか。それを可能にするためには、教員1人につき何コマくらいを上限とし、どれくらい教員を増やさなくてはいけないのか等、具体的な指針が見えてくるはずです。
給特法の改正は「入り口」に過ぎない、というのが私のスタンスです。だからこそ、こんな入り口で押し問答していること自体が「終わっている」のです。日本の教育の未来を真摯に考えるなら、給特法改正の議論をきっかけにして、教員の定数改善、教員の業務の精査、標準授業時数の削減、他の先進国並みの教育予算の拡充に繋げていかなければならないのです。