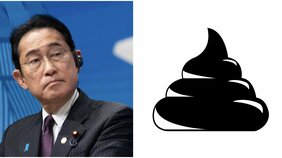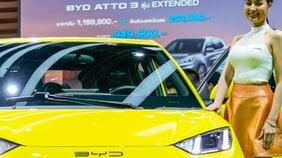牛糞を発酵させてバイオガスを発生させる「バイオガスプラント」
人間の50倍もの重量のウンコをするのが乳牛だ。酪農家の数が減り、一戸当たりの飼養頭数が増えている。酪農家が頭を悩ませるのが、家畜糞尿の処理だ。
北海道道東の大樹町は、農業生産額の8割を酪農が占め、「酪農王国」と呼ばれる。ここで、乳牛を中心に、約2700頭を飼育する株式会社サンエイ牧場は、牛糞を発酵させてバイオガスを発生させる「バイオガスプラント」を二基導入した。代表取締役の鈴木健生さんは、きっかけは臭気対策だったと振り返る。
同社では毎日約200トン、年間では7万3000トンほどの糞尿や雑排水が生じる。以前は貯留してスラリー(液肥)を生産していたが、これは散布すると強烈な臭気を発する。そこでバイオガスプラントを導入し、よりにおいの少ない液状の有機質肥料「消化液」の生産に切り替えた。
「地域の基幹産業だから、ある程度臭くても許される。これからはそういう考え方ではやっていけない。地域住民が納得できる営農スタイルを考えていかなければ」と、鈴木さんは語る。