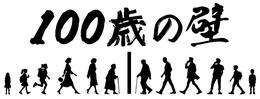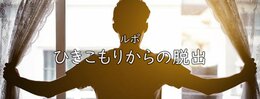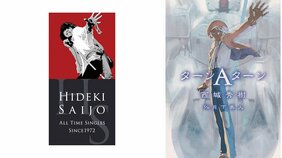なぜ国産オレンジで代用できない? その“単純明快”な理由
一方で、微妙なタイミングとなってしまったのが「バヤリース オレンジ」だ。
先述のとおり、同製品は4月8日から果汁の割合を減らし、販売を再開。しかし、先物価格が下落し始めている現在の状況を考えると、もう少し耐えれば、従来の仕様での再開も可能だったかもしれない。
この点についてアサヒ飲料に「先物価格の落ち着きに伴い、果汁割合や価格を元に戻す予定はあるか」と尋ねたところ、「現時点で予定はありませんが、引き続き状況を注視していきます」との回答だった。
各社に大きな影響を与えているオレンジ果汁の高騰だが、こうなると疑問に思うのは「国産オレンジで代用できないのか」という点だ。
構造的な円安に加え、エネルギーコストの高騰、さらには投機筋の参入による不安定な相場といったリスクを考えると、海外産に頼らず、国産でまかなうほうが安定した調達につながるのではないかと思えてくる。
しかし、結論から言えば、国産オレンジは国内の旺盛な需要をまかなえるだけの生産量がないのが実情だ。この点について中央果実協会は、次のように説明してくれた。
「日本ではオレンジはほとんど生産されておらず、その量は年間3万トン弱にすぎません。ミカンは年間70万トン程度が生産され、そのうち1割強が果汁用に加工されているようですが、品質のよいものは青果として高値で売れるため、果汁向けには出回りません。
さらに、加工業者が青果用を高値で仕入れても、果汁として製造・販売した場合に採算が合わないのです」
あらゆるモノの価格が上がり続ける昨今、せめてオレンジジュースだけでも気軽に手に取れる存在であってほしいが……。我々消費者は、ただ静かに見守ることしかできない。
取材・文/集英社オンライン編集部ニュース班