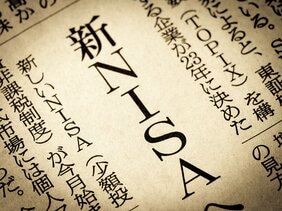異動が多い公務員
服部 国債市場の実務家は非常に専門家が進んだ世界です。私の知っている債券の市場参加者は入社以降、債券ビジネス一筋という人も少なくありません。この観点でいえば、官僚は、プロ集団に対峙し、望ましい政策を作る必要があるともいえますが、神田顧問ご自身はどのような形で専門性とジェネラリストのバランスを取られたのですか。
神田 私が一番長くいたのは、10年ほどいた主計局なんですが、次に長かったのは6年いた世界銀行なんです。因みに併任ですがOECDの委員会議長は8年やりました。主計局という非常にドメスティックな場所と、世界銀行という国際的な組織を行ったり来たりしており、例えていえば、環境の違う場所を行き来するサウナにいるようです。
二つの場所での経験にシナジーがあり、いろんな分野の人と出会えてよかっただけでなく、仕事においても極めて有益でした。例えば、海外にいるときに最先端の世界のベストプラクティスやセオリーなどを学ぶ一方で、世界のルールメイキングのときに日本の国益をどうやって入れていくのかという作業ができます。
国内にいるときは、海外で勉強したものの中で日本に適用できるものについて導入を図ることもあります。海外の新たなパースペクティブや知見の導入自体、ともすれば内向きになりがちな国内組織に先進性、多様性、開放性を齎す貢献ができるのです。また、多くの物事が国際社会で決まってしまう中、日本が必要とする国際秩序は何なのかということを、国内でいろいろ悩みながら勉強し、海外に行ったときにそれにチャレンジすることができる。
例えば主計局では多くの省庁の担当をさせてもらいましたが、相手の省庁はその分野の専門であるわけです。尊敬すべきカウンターパートであり、必ず謙虚に教えて頂く姿勢で意見交換してきました。相手の省庁の中でも細分化された局や課であれば猶更です。そうすると、僕らの強みというのは、幅広いパースペクティブを持っていることにあります。
極端にいえば、普通の国民の目線、偉大なる素人として一から考えることも大切です。いろんな仕事をすることが様々な教訓や成功事例、幅広い政策手段を獲得し、そのシナジー効果を持って、それ自体が専門性になることがあります。
だから、両方必要であって、一人一人がハイブリッドであるべきだというのが私の考えです。役所にきたら、そういった楽しいことが両方できる人生になりますよそうして自ら成長できて社会貢献もできる、と学生に伝えたいです。
服部 公務員の場合、異動が多いので、書籍を読むなど、より一層自己研鑽が必要な側面もあるとおもいます。『はじめての日本国債』も異動が多い公務員が情報のキャッチアップができるように、という思いも込めて書きました。
神田 仕事と直接関係のない勉強をすることも極めて重要です。公務員の場合、身近な役人や政治家、言論界、実業界以外の人、つまり、芸術、スポーツ、科学技術、芸能界までと貪欲に出会ったり、専門外の書物を読むことが人生を広げ、新しい発想を得ることができます。
それは可能で、毎晩のように色々な業態、国籍、年齢の方々から学んできましたし、刺激を楽しんできました。私はSNSについては、いわゆるエコーチェンバーやフィルターバブルの問題があると思っていますが、組織で働く経験自体も狭いところに留まっていると、似たような方とだけ共鳴し合ってしまうリスクがありますよね。
また、大きな仕事はチームでやるという視点も大切です。一人では大したことはできませんが、みんなで協力してやれば、その数百倍、数千倍のことができます。組織としてやるときは、一人一人の個人の知恵を蓄積しながら、政府あるいは世界全体でその知恵を有効活用するという姿勢です。
過度に専門性だけ重視してる人たちは、チームで取り組むという観点が欠けてるときがあるかもしれないし、逆にジェネラリストを重視している人たちは、実は何ら本当のプロフェッショナルな付加価値なしに、薄っぺらい調整をやったふりだけになってしまうリスクもあるわけです。