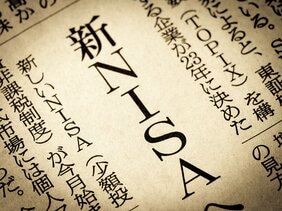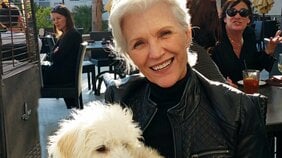公務員だと人事異動が多く、専門性が身につかないのではないか?
服部 私が所属する公共政策大学院では政策を担う人材を育成するという側面も有しています。私が実際に学生と接していると公務員だと人事異動が多く、専門性が身につかないのではないか、という声が聞かれ、公務員の志望にも影響を与えているように感じます。人事のご経験がある神田顧問は、この点についてはどのようにお考えでしょうか。
神田 現在のような激動し、不確実性の高い社会では、複合的な知見、ひいては哲学や歴史が与えてくれるような教養や大局観、これに基づいた革新的な試みが求められています。私の親友である各国の政官学リーダー、民間会社のCEOは、いずれも、幅広い実務経験からも読書などからも博学で、好奇心にあふれている方ばかりです。
また、どんな会社でもある程度の役職になると、調整などの仕事が重要になります。例えばコンサルがやっていることも、要するに、役所がやっていることと近くて、いろんなケースから抽出した法則みたいなものをヒアリングして、把握できた状況に当てはめてアドバイスしているわけです。
その意味で、みんなある意味ジェネラリストともいえるのですが、ただ、プロ意識が必要だという点がすごく大事です。民間も公的機関も関係なく、この乱世で何が答えかがわからないときには、とにかく一生懸命、例えば時代の変化に合わせて高い付加価値を国民に提供する必要があり、過去以上にプロフェッショナリズムが必要なのです。
問題解決に資する専門的知識を鍛えることと、広い視野、経験を持つこと、これらはどっちも必要で、全く専門的知識のない存在も、総合的な視座がない存在も問題です。いわばハイブリッド人材が最強となります。
人事の運用では、人材育成のプロセスの中で幅広い視野を持つ人材を育成する一方で、相対的によりフォーカスしたエリアの専門性を確保する、そのバランスが必要となります。よくいわれてるのは、二つぐらい専門分野を持ち、ジェネラリスト的に働くというものです。いわゆるT字型人材とかΠ字型人材などといわれるものですね。