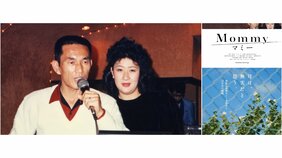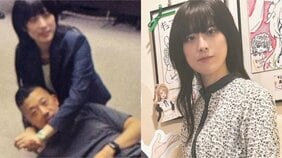警察の不可解な動きとDNA型鑑定
1992年2月20日、福岡県飯塚市で小学一年生の女の子二人(ともに7歳)が、朝、家を出たまま学校に現れず、捜索願が出された。翌日になって20キロ近く離れた山の中で、二人の遺体が発見された。
二人は首を絞められ、殴られた跡もあった。膣とその周辺から、犯人のものとみられる血痕が採取された。さらに翌日には現場から3キロほど離れた道路沿いで、ランドセルなどが見つかった。
この街では、この事件の3年あまり前にも小学一年生の女の子が行方不明になり、いまだに見つかっていなかった。
警察は大掛かりな捜査態勢を敷き、それによって遺体が早く発見され、捜査は進むかに見えたが、その後は順調には進まなかった。
二人の女の子が突然姿を消し、遺体はそこから20キロも離れたところで見つかった。
犯行に車が使われたことは、ほぼ間違いない。しかし、車に関して、まったく違う情報が錯綜していた。
事件の発生以前から、この地区内では、不審な白色の小型自動車がしばしば目撃されていた。路上に停めて、小さな女の子に声を掛けていたという。一方、事件当日、遺留品が発見された近くで、道路脇に紺色のワゴン車が停まっているのを見たという人がいた。
目撃者はその際、ワゴン車の後輪がダブルタイヤ(後輪だけ2輪ずつ装備されている)だったことを確認したという。
「紺色のワゴン車」の証言に捜査本部は刮目した。それは、警察が事件発生直後から目をつけていた人物の所有する車と、その特徴が完全に一致するからだ。
久間三千年氏(当時54歳)は3年前の女児失踪事件で、女の子を最後に見た人物として、警察に調べられていた。事件か事故かも分からないまま時は流れたが、警察は今回の事件が発生した直後から、正確にはこの3年あまりずっと、久間氏の身辺に目を光らせてきた。
そして、彼が所有している車は、紺色のワンボックスカー(ワゴン車の一類型)で、後輪はダブルタイヤだった。
事件発生の5日後に、久間氏は最初の事情聴取を受けている。妻子とともにこの街に住み、当時は定職についていなかった。
捜査本部はその後、鑑定試料として久間氏の毛髪を入手し、遺体から採取した犯人の血液痕とともに科警研(科学警察研究所)に送った。当時はまだ、DNA型鑑定は本格的には運用されていなかったが、科警研は、その前年に足利事件のDNA型鑑定を実施していた。
間もなく、「一致した」との鑑定結果が届いたはずである。しかし、その後2年以上、警察は久間氏を逮捕せず、泳がせている。さらに、この間に別の研究機関にDNA型鑑定を依頼している。なぜ、そんなことをしたのか。その理由を探るために、同じDNA型鑑定を使ったもうひとつの事件、足利事件まで時を遡ることにする。