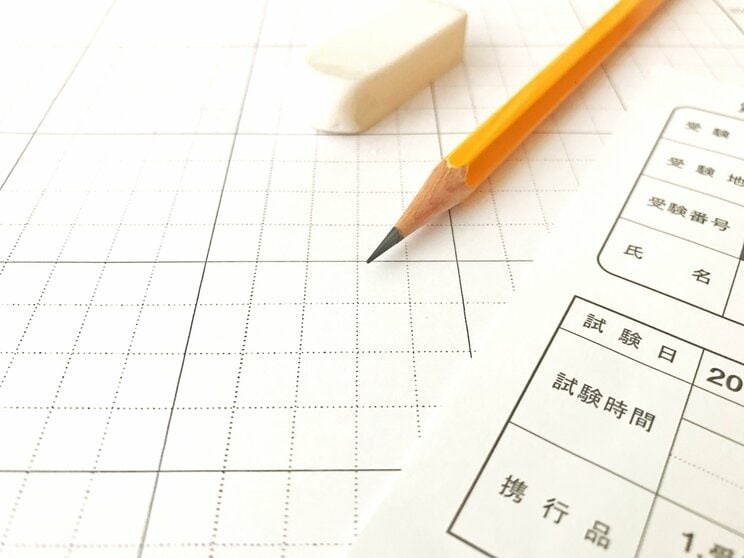加熱する受験戦争
共通一次試験導入の本来の目的の一つに、アメリカの全米共通テストのSATのように、高等学校における学習達成度を見る指標とし、それを受けて大学がそれぞれ独自性に富んだ二次試験を実現することがあったはずです。
しかし、本制度の導入によってアメリカのようなスタイルには至らず、むしろ学歴主義を加速させてしまうことになります。
共通一次試験は、二次試験と合わせて総合的な合否判定に使用されるというよりも、二次試験の受験資格を得るためのパスポートの側面が大きくなってしまったのです。
一次試験と二次試験の得点比率を大学側が自由に設定できることも問題でした。
東大や京大など最難関大学では二次試験が重視されましたが、多くの国立大学は共通一次の比率を7割や8割に設定しました。こうした共通一次偏重の傾向により、各大学の特色となるはずの「アドミッションポリシー」などは生まれず、むしろ「詰め込み教育」の温床となっていきました。
さらに、共通問題が導入されたことによりその得点率によって大学が序列化されるようになり、国立大学の偏差値ピラミッドがはっきりと現れてしまうという思わぬ事態も生みました。
共通一次試験が導入された1979年以降、学歴社会に拍車がかかった感があります。
受験戦争が過熱する中、どうしても我が子に学歴を身につけさせたい親たちが暴走してしまう事例がこの時期(昭和後期)から見られるようになります。
それまでの日本では、農業、漁業、林業といった一次産業や、工業や製造業といった二次産業に従事する人たちが圧倒的多数派であり、大学は経済的に恵まれた人や、一部の秀才が行くところだと考えられていました。1950年代までは大学進学率は10%以下、高校進学率ですら60%を下回っていました。
ところが、1950年代後半からの高度成長期に入ると、第一次産業が急速に衰退していき、都市を中心としたサービス業や情報通信業といった第三次産業が急成長するという、産業構造の大きな変化が起こり始めました。