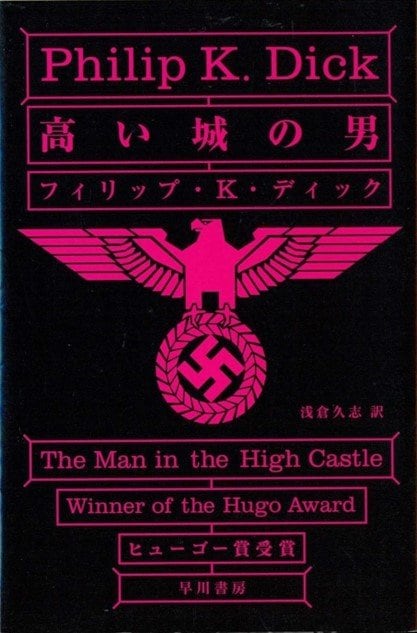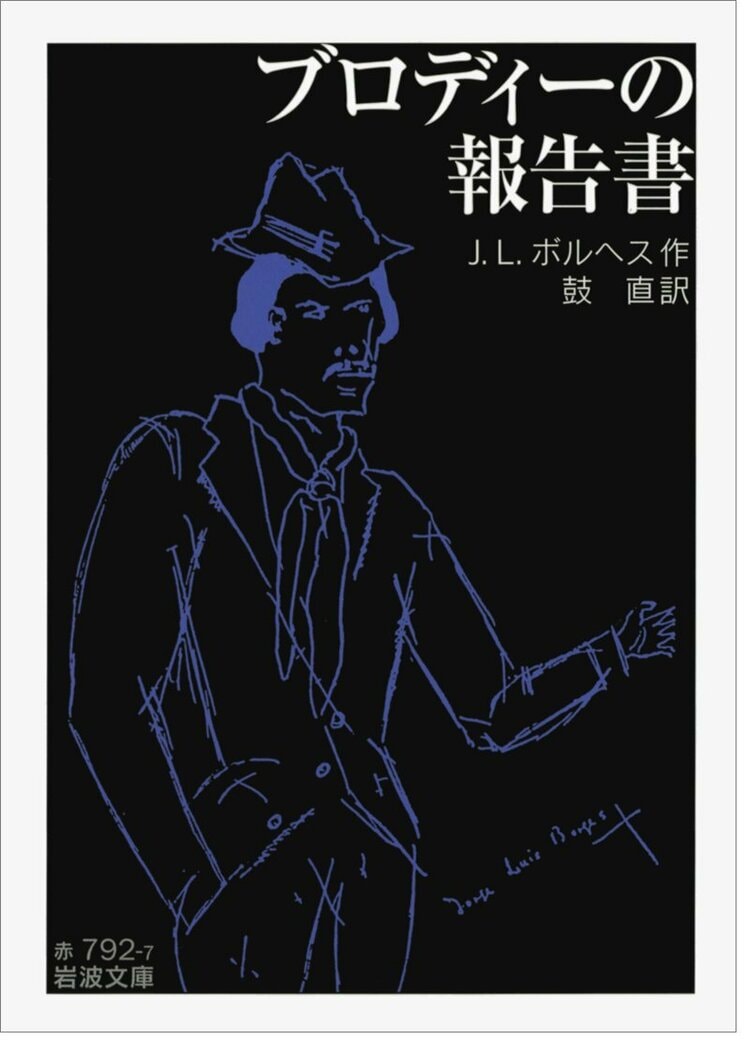異文化受容、多文化共生を! と叫ばれて久しいが、むしろ世界は、というか世間・生活空間・ネット領域では、そういった意識高い系文化フレグランスへの反発に由来する、アンチ異文化ムーヴが激しさを増している。在日ドイツ人たる私も、実際、ふたつの文化の懸け橋という以上に両文化の板挟みに遭って双方を呪う展開が多い。おお、我は求め訴えたり!
そんな私が選ぶ「闇黒ぶりが活力となる!」異文化遭遇本、まずはフィリップ・K・ディックの『高い城の男』だ。ナチスドイツが世界制覇に王手をかけ、友邦たる日本に核攻撃を仕掛ける5分前の世界を描くという時点でもうすでにネガティブ極まりないが、本書のキモは「ナチス」の政治的狂気以上に、「ドイツ」の文化的狂気に踏み込んでしまった点だ。ヨーロッパの伝統哲学的な理性が人間のスペックを超えてなお人間を支配することで生じるヤバみ。
彼らの観点――それは宇宙的だ。ここにいる一人の人間や、あそこにいる一人の子供は目に入らない。(中略)抽象観念が現実であり、実在するものは彼らには見えない。“善”はあっても、善人たちとか、この善人とかはない。時空の観念もそうだ。彼らはここ、この現在を通して、その彼方にある巨大な黒い深淵、不変のものを見ている。それが生命にとっては破滅的なのだ。
……いやぁどーですか。ナチスの宿業とは何か、とかを真面目に考え抜いた末にこの言霊が目の前に出てくると、これまでに無かった負のパワーで魂が推進されるのを実感せずにいられない。ついついご飯をおかわりしてしまう!
そしてもうひとつの「異文化」闇黒奥義小説は、20世紀最強の文豪ともいわれるアルゼンチンの巨匠、ホルヘ・ルイス・ボルヘスの短篇「ブロディーの報告書」だ。中部アフリカのある部族の村を訪れた宣教師の手になるリポートという体裁の物語で、単なる野蛮さを超えて何かを突き抜けてしまった「文化」に直面すると意識の奥底の何が壊れるのか、ということを見事に謳いあげる逸品だ。無自覚な知的敗北感が心地よい。
いったん戦いが始まると、呪術師たちは王を洞窟の外にはこび、種族の者にその姿を示して士気を鼓舞する。そして旗幟か護符のように、肩にのせて戦場のまっただなかにかつぎ込む。この場合、おおむね王は猿人たちの投げる石に打たれてたちどころに死ぬ。
ちなみにこの「王」は絶対的な権威と権力を有するが、生まれつきの身体的特徴から即座に選出され、選出されると同時に目を潰されて去勢され、その後ずっと洞窟の奥で監禁され続けるのだ。権威権力とはそもそも何か。ここに一つの昇華しきった姿があるのではないか。
ということで、ディックやボルヘスが内面で直面し続けた異文化的深淵に比べれば、我々の主観が嘗め尽くす日々の地獄など、それこそものの数ではないわ! ……と言ってみたいなぁ(笑)。