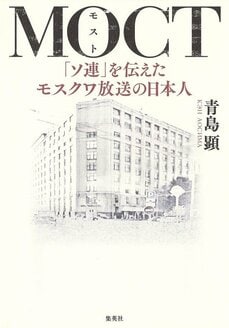地下流通していた「肋骨レコード」
島田 冷戦時代のソ連社会のエピソードもたくさん書かれています。その中に、袴田氏の名前が出てきますが。
青島 袴田陸奥男さんですね。
島田 そう。彼の息子さんは青山学院大学で教授をされていた袴田茂樹さんで、80年代から90年代にかけてロシア通のコメンテーターとしてニュース番組に出ておられた。一度、袴田茂樹さんとは対談後に飲みに行ったことがあり、お父さんの話を告白的にしてくださった。『МОСТ』を読んでいて、「あっ!! お父さんが出てきた」と。
青島 シベリア抑留者であるとともに、収容所では当局に保護され元将校をつるしあげ、「天皇」と恐れられていた。
島田 ある意味ソ連側の人間になってしまい、帰国できずにモスクワに留まった。そうした詳細をよく調べられているのに驚きました。
青島 袴田陸奥男さんは向こうで結婚もし、モスクワ放送の翻訳員を務め、80年に退職した後も仕事をされ、91年に亡くなられています。やはり茂樹先生は、お父さんに対しては複雑な思いを――
島田 抱いていらしたと思いますね。
青島 そうですか。
島田 冷戦時代のトピックとして、レントゲン写真を使った「肋骨レコード」も出てきますね。蓄音機の録音機能を使い、使用済みのレントゲンフィルムに傷をつけて作るものなんでしょうけど。
青島 はい。ちょっと聞かせていただきましたけれども、不思議なものでした。骨が写っているので「ボーンレコード」ともいわれ、一枚一枚作り、中心に穴を開けるんですが、モノによって穴が2個開いていたりするんです。
島田 あれは地下で流通していた音源ですよね。活字メディアのサミズダート(地下出版物)の実物は見たことがあるけれど、“ロッコツ”は知らなかったなあ。
青島 サミズダートの実物をご覧になっているんですか?
島田 ペレストロイカ(改革政策)以降のグラスノスチ(情報公開)で、保存しているグループに見せてもらいました。いろんなバージョンがあって、よくあるのがタイプ原稿。
青島 タイプライターを使うんですか。
島田 まず原本を最も信頼のおける相手に貸す。その原本を、カーボン紙を挟んでタイプで打つとコピーが2部出来る。その一部をまた別の人に渡し、原本を返す。そういうふうに広まったものです。見つかったら逮捕されるので、写真に撮って自分の部屋で現像したものとかミニチュアバージョンもありました。
青島 それで1万部になったものがあるというのはすごいですよね。
島田 あと、私も実は『亡命旅行者は叫び呟く』を書くときにシベリア抑留経験について調べたことがあったんです。
青島 やはりそうなんですね。
島田 当時は(自身もシベリア抑留経験のある)三波春夫が向こうのホテルで歌ったりしていて、そういうことも懐かしく思い出しました。
青島 「ハバロフスク小唄」ですね。
島田 ハバロフスクのインツーリストホテルに一泊すると墓参団と受入機関との歓迎会が行われ、三波春夫が登場する。
青島 その場にいらしたことがある?
島田 レストランで夕飯を食べていると「あっ、三波春夫だ」という声が聞こえてきて。そうした抑留者とも関連するのですが、モスクワ放送で働いた日本人も幾つかの世代に分かれるんですね。
青島 淑徳大学の田中則広先生がモスクワ放送で働いた日本人の世代分類をしているんです。それによると、日中戦争の頃に越境した岡田嘉子さんなどの亡命者が第一期。第二期がシベリア抑留者、南樺太の残留者。第二期とそれほど違わないのですが、第三期が戦後のレッドパージでソ連に渡った人。第四期が70~80年代に渡った人たちになります。
島田 ということは、私が存在を感じていたのは第四期の人たちになりますね。皆さん、お金目的だと到底続かない仕事をされていたわけじゃないですか。持っていたのは個人的な動機、あるいは情熱。その辺の思いをよく酌み取って書かれていて、琴線に触れるところがありました。
青島 そう言っていただけると本当に、取材に協力してくれた方に対してありがたいなと思います。
島田 今、モスクワ放送は?
青島 ソ連崩壊後、1993年に「ロシアの声」と名前を変え、2014年から15年の間にインターネット放送の「ラジオ・スプートニク」になり、17年にそれも停止しました。ただ、ソ連崩壊後も混沌とした時代によく続いたと感じます、むしろ。
島田 そうですね。ソビエト連邦というものが存在していた時代までは、採算性を度外視してでも必要だとされたんでしょうけど。イデオロギー対立が消滅したら、個人の欲望を満たすことだけが目的となる。今だけ、金だけ、自分だけ。
青島 ロシア全体が「ギャング資本主義」と言われるものに変わっていくんですね。でも放送がなくなってしまった今、まずいと思うのは、戦争を起こしたロシアの考えていることが日本に伝わってこないことです。
島田 それは(外務省の)ロシアンスタディーが手薄になったからですよ、間違いなく。
青島 安倍首相(当時)がプーチンに「ウラジーミル」と呼びかけていましたが、ロシア人に向かって、西側みたいにファーストネームで呼ぶなんてあり得ない。
島田 ロシア人は、仲の良い人であれば「ワロージャ」(ウラジーミルの愛称)と言いますよね。
青島 愛称で呼ぶ。そういう基本的なことをなぜ周りが教えてあげないんだろうか。すごく違和感を覚えたんですけど。
島田 佐藤優氏がまだ外務省にいた頃には、チャイナスクールや国際協調派、地政学派などいろんなグループが省内にはあって、アメリカンスクールはその一つでしかなかったんです。
青島 バランスをとっていたんですね。
島田 それが今は対中政策も、対中東、対ロも、アメリカンスクールが独占的にやっていると。
青島 アメリカの情報一辺倒になり、それが日本の報道にも影響を与えているとしたら、よくないです。
――『МОСТ』の中にソ連で働いた後に帰国され、ロシア語学校を開設されていた東一夫さん夫妻との交流を綴ったくだりがあります。一夫さんは過去をあまり人に語らない。その事情を「私」視点で調べていく一章には私小説的な趣きがあります。
青島 東一夫さんには分からないことが多いんですね。あの学校に通ったことがあり思い入れもあったので、あの章だけは、こう書こうと思ったというよりは、自然に言葉が出てきてしまったんです。
―― 機会があれば、東さんのことを書きたいということだったのでしょうか。
青島 それもあって、東さんが亡くなった後も続けておられた妻の多喜子さんが、学校を閉じるとき新聞記事にしました。多喜子さんにも魅力を感じていたので。とても厳しい人で、(自分の心の中で)第二の母親みたいな感覚もあったのかなと。
「おい、40%くれ」
―― ロシア人の情に厚い一面も語られていますが、今後の日ロ関係を考えた場合、そういうところに期待できるとお感じになりますか。
青島 シベリア抑留を体験された人と話しても、そういうことをおっしゃる方が多かったですね。虜囚の待遇としては、食料は乏しく最悪だけれども、人間扱いされたと言うんですね。
島田 あそこは柵がない。凍土なので、逃げたら死ぬ。だから現地では協力し合って暮らすしかないというのもあったでしょうね。ロシア語を勉強していたときに習ったのが、「ダイチェ・ソーラク」。「40%くれ」という意味です。たとえばタバコを喫っている人にそう言うと、喫っているのを渡してくれる。
青島 四対六でシェアしようということですね。日本ではソ連・ロシアは「嫌いな国」「何だか怖い国」というイメージが定着してますが、温かい人たちが暮らしていて、その人たちと触れ合った日本人がいたんです。そのことを、登場人物を通じて描けたらなと考えました。読者の皆さんに、そんな空気感や人々の願いが少しでも伝わったら、嬉しいです。