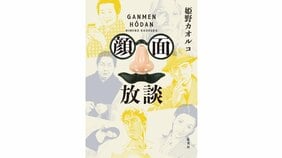ノンフィクションより、
小説のほうが真実かもしれない?
―― そして、『くもをさがす』を読んだ方にオススメしたいのが、「Crazy in Love」(「文藝」二〇二二年秋季号)です。『くもをさがす』で描かれていた、カナダの病院で手術開始を待つ西さんの身に降りかかった一連の出来事が小説の形で語り直されている。主人公は、名前こそ「一戸ふみえ」となっていますが、西さんのプロフィールを重ね合わせた小説家ですね。
金原ひとみさんが責任編集を務める「特集私小説」に参加しませんか、と声をかけていただいたんです。最初は、『くもをさがす』にも出てくるがん仲間のコニーが「人生の目標がないから小説を書き始めたんだ」と話していたことを思い出して、そのエピソードは私小説というテーマと合うんじゃないかと思ったんだけど、いや、それはコニーのこと、私は私のことを書くべきだ、と考え直したんです。自分のがんについて改めて振り返ってみた時に、書きたいのはやっぱりあの瞬間のことだなと思ったんですよね。「何してくれてんねん!」はもちろんあったけど(笑)、「何やろ、これ? なんでこんなに清々しいんやろう」って思ったんですよ。
―― 手術直前に他の患者と名前を間違えられるという大トラブルが勃発するんだけれども……と。間もなく手術が始まるとは思えない祝祭感は『くもをさがす』でも記録されていたものですが、小説ならではのマジックがいくつも振り掛けられていますよね。例えば、間違えられた名前は、実際はボニータでしたが、小説ではビヨンセになっています。この変更の意図とは?
現実もドラマチックだけど、それをもっとポップなドラマにしたかったんです。自分が間違えられたって分かった瞬間に頭の中で鳴り出した音楽は、現実ではア・トライブ・コールド・クエストの「Bonita Applebum」で、それは私の大好きな曲だったんですよ。でも、小説で書くんだったらビヨンセの「Crazy in Love」のほうが、リズムが合うんじゃないかと思って。実在の人が関わっている出来事なので、『くもをさがす』では消したけれども、小説では違う形で残っているノンフィクションの部分があったりもします。読み比べてみて「あれっ、こんなふうに書いている」とか「小説のほうが真実かもしれない?」と、現実とフィクションの関係に思いを巡らせていただけたら嬉しいですね。
ポリコレ的に正しくても、
優しくなかった反省を込めて
――『くもをさがす』の中で、西さんはカナダで格闘技を習い始めたと書かれていました。「ママと戦う」(「文藝」二〇二二年春季号)は、その経験が物語の種になったのでしょうか?
それが種でしたね。特に理由もなく衝動で柔術の教室に飛び込んでみたら、スパーリングの時に先生から何度も「サバイブ!」と言われたんです。「生き延びろ!」と何度も言われて、私も必死でやったんです。それがものすごく印象に残っていました。翻訳者と喋っていて面白かったのは、これがウィズなのか、バーサスなのか、ということ。日本語の「ママと戦う」って、どっちにも解釈できるんです。「ママという相手と戦う」にもできるし、「ママと共に戦う」にもできる。それは意図して書きました。これはママとバーサスで戦う話でもあるけれど、ママとウィズで共に世界と戦っていく話でもあるということです。
―― コロナ禍真っ只中、都内のマンションでエッセイストのママと二人暮らしをしている一七歳の女の子・モモが主人公です。彼女は高校に進学せず、家に籠って日々をやり過ごしている。ママは愛情深いんですが、どうしようもなく間違っている部分がありました。〈ママがずっと欲しかった言葉と、私が今欲しい言葉は違うのに〉。何故こんなふうにすれ違ってしまい、何をきっかけにどう変わるのか。二人の関係性を真摯に見つめていきます。
いわゆるポリティカルコレクトネス的に正しいことは全然言えないけど、優しい人っているじゃないですか。「ママと戦う」のママはまさにそういう人だったんだけれども、大人としてもっと正しくなろうとして逆に、娘に対してどんどん距離を作ってしまう。ここにも私自身の感覚が反映されています。自分も最近、自分の中の正しさを求めすぎることで、優しくなくなってしまっているんじゃないか。間違った言葉でもいいからかけて、抱き締めたほうが良かったこともいっぱいあったんじゃないかな、と思うことがあって。その逆に、「ママと戦う」のママと不倫していた男性が妊娠を知らされた時、「君の体は君だけの、大切な体なんだ」と、一見正しい言葉を言います。その正しい言葉を使って逃げるんです。彼のように、私も正しい言葉を使って、優しさを放棄する瞬間がある。自分への反省の意味を込めて、書きました。
―― ただ、これもまたラストで、とてつもなくパワフルで光に溢れた場所まで駆け上がっていくんですよね。最終編「チェンジ」(書き下ろし)の光の見出し方も素晴らしかった。昼間はアパレル店員として、夜はデリバリーヘルス嬢として働く主人公の話ですが、自分を絶望させた言葉を自分の武器に作り変えていくんです。
カナダで日本のコロナ禍のニュースを知るにつけ、腹が立って仕方がなかったんです。都民、国民にひたすら負担をかけて変わらせようとするけれど、「変わるのはそっちだろ。都だろ、国だろ!」って怒りを覚えたんですよね。でも、そういう怒りを持った主人公を書いている私自身は、バンクーバーの、ソーシャルディスタンスがナチュラルにできているような、余裕のあるエリアで暮らしている。自分自身に対して「どういうつもりでこれ書いてんねん」という思いはずっとありました。だから、自分を最後に一発殴るつもりで、ある場面を描写しました。
―― コロナ禍で感じたことと、カナダで過ごしたこと、がんのこと……。執筆期間中に起きたことや考えていたことが、一つ一つの物語の種になっていったんですね。
短編って書いたその時のことが随分と入ってくるものなんだなって、今日お話ししながら痛感しました。それと同時に思うのは、例えば「わたしに会いたい」を書いている時に、自分が乳がんになるなんて思わなかったんですよ。でも、予言ってわけでもないんですけど、後で自分の体や人生で起こることに対してこういうふうに考えればいいんじゃないかなって、準備していたというか、未来の自分に教えてくれていた感じがするんです。読み返していて、そこがすごく面白かった。心強かったです。
―― この一冊は効きが強いぞ、と感じたんですよ。ゴールテープを切る直前の駆け上がり感、そこで炸裂するメッセージは、長編であれば基本的に一回だけしか表現できません。でも、今回の短編集であれば八回も経験できる。その過程で、本書全体に通底するメッセージが濃く輪郭づけられていく感触があったんです。
そう思っていただけたら、とても嬉しいです。短編の名手と呼ばれる方が書くものも好きなんですが、普段は長編を書いている方が書く短編を読むことも好きなんですね。例えば、私はアリ・スミスというイギリスの作家が好きで、彼女は基本的に長編を書いているんですが、アリ・スミスの短編集を読むとアリ・スミス性に矢継ぎ早に会えるんですよ。すっごいぜいたくな感じがするんです。この本でも、短編全てに私性がどうしようもなく現れていると思います。結局、それぞれの短編で、いろいろな角度から同じことを言っているんだと思うんです。自分の体は自分のもの。自分の体は一つだということ、自分の体を自分のものにするということを、手を替え品を替え言い続けている。長編であれ短編であれ、私はそのことをこれからもずっと書き続けていくんだろうなと思います。