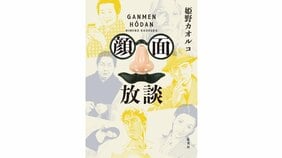自分の体を自分のものにするということを、
書き続けていく
移住先のカナダ・バンクーバーで乳がんが見つかり、両乳房摘出手術を受けた日々を綴ったノンフィクション『くもをさがす』(河出書房新社、四月刊)が、八月には二五万部を突破し話題となった西加奈子さん。最新刊『わたしに会いたい』は、小説としては長編『夜が明ける』以来二年ぶりとなる、短編集だ。
コロナ禍で感じたこと、カナダで過ごしたこと、がんになったこと……。自身の体験や記憶を種に生まれた、パワフルで光に満ちた八つの物語。普段は長編を中心に活動する作家の短編集には、長編にはない“効きの強さ”が宿っていた。
聞き手・構成=吉田大助/撮影=中川真人(CUBISM)
自分は自分以外になれない絶望と、心強さ
―― 今回の短編集は、文芸誌「すばる」に発表した作品をはじめとする全八編が収録されています。実は、西さんが集英社から本を出されるのは初めてなんですよね。何かきっかけがあったのでしょうか。
『おまじない』(二〇一八年三月刊)という短編集を出した時、「すばる」の編集者の方から素晴らしい感想をいただいたんです。自分の知らない私の短編の良さを教えてくださった、すごく力になる感想だったんですよね。その方に新しい短編を読んでほしいなと思って、書いたものをお送りしたのがきっかけです。
―― 収録作で最も時期が古いものは、「すばる」二〇一九年一月号の第一編「わたしに会いたい」(単行本収録時に「私に会いたい」から改題)。西さんがご家族とカナダに滞在していたのは二〇一九年一二月からの三年間ですから、まだ日本にいる時に執筆されたものですね。
数年に一度起きることなんですが、「わたしに会いたい」と「VIO」(「すばる」二〇一九年六月号)と「掌」(「すばる」二〇二〇年六月号)の三本のイメージが、ある夜ブワッといっぺんに浮かんできたんです。「わたしに会いたい」で言えば、もう一人の自分がヒーローのマントを翻して自分の元へやってきて助けてくれる、という断片的なイメージです。それを元にして、主人公の女の子が歯の治療で痛い思いをしている時に、自分と同じ歯医者さんのケープをつけたもう一人の自分がやってきて、会えないんだけれども救ってくれる、というシーンができました。
―― 短編集の表題作となった「わたしに会いたい」は、本書全体を象徴する内容だと感じます。主人公の未唯は五歳の頃、病院で身体的なハンデについての診断をくだされ、母やお姉ちゃんたちの反応からネガティブな状態に陥りかけてしまう。そんな時、親友の男の子が、自分にそっくりな女の子を見たと言い出します。その後も、人生の要所で折に触れて「もう一人のわたし」(ドッペルゲンガー)が彼女の近くに現れる。ドッペルゲンガーといえば一般的に「会うと死ぬ」という恐怖を伴う存在ですが、会いたいけれど会えないその存在が彼女を救うんですよね。これまでの西作品の主人公は、自分という存在の厄介さに苦慮する人も少なくなかったと思うんですが、本作では「わたし」が忌避すべき存在ではなく、自分を救ってくれるヒーローとして描かれている。
ヒーローが他に存在してしまった場合、その人が来てくれなかったら解決しないですよね。でも、自分がヒーローだったら、自分を救うのも自分次第じゃないですか。
―― 本書収録のどの短編も主人公たちが負の状態、あるいは凪の状態から、希望と生命力に溢れた状態へと終盤にかけて駆け上がっていく姿が印象的なんですが、この一編は格別でした。
私もこの短編は、最後のほうで一段ギアを上げたと感じています。さっき「厄介さ」とおっしゃっていただきましたが、たぶん私は自分という存在に対して「もどかしさ」をずっと感じているんですよね。四十数年間、自分が自分以外になれないということに対して淡く絶望し続けてきたように思うんです。その一方で、世界をどう切り取るか、世界から何を得るか、世界をどう見るかは結局全て自分にかかっているんだと思うことで、そっか、だったら自分次第なんだなという、驚くほどの心強さもある。自分は自分以外に絶対なれないことがプラスの方向に振り切って出ていったのが、この短編だったんだと思います。
――「VIO」と「掌」は、どんなイメージから出発したんでしょうか?
「VIO」は若い頃、VIO(下半身のデリケートゾーン)脱毛をした時にアホかというぐらい痛くて、当時「何のためにこれをやってるんだろう?」と思ったんですよね。「私は、誰のためにこの痛みに耐えないといけないんだろう?」と。「掌」も若い頃の思い出として、雑居ビルでバイトしていた時に、磨りガラス越しに、屋外の踊り場でセックスしている人たちを目撃してしまうことがあったんです。その磨りガラスに手をついているというか、手をつかされていたのは圧倒的に、女性が多かった。「女性の手ばっかり見るなぁ」と当時ぼんやり思っていたことが急に浮かび上がってきて、その記憶を元にした小説が書きたいなと思ったんです。
―― 西さんの脳裏にふと蘇ってきたかつての記憶を手がかりとしながらも、二作ともストーリー性が高く、イメージの跳躍力があります。「掌」にはミステリー的な要素がありますよね。「VIO」はガールズバーで働く女の子がエステで下半身のムダ毛を処理するという入口から、戦争へと話題が膨らんでいくことに驚きます。
下半身の毛をレーザーで焼いてもらっている時に、主人公が思ったのと同じことを私も思ったんです。施術してくれた女性に「このレーザーは黒いものだけを燃やすんです」と言われて、「じゃあ、金髪の人は燃えないんですか?」「燃えないです」と。その瞬間ドキッとして。まるで特定の人種だけに効果がある兵器みたいなものだなと思いました。例えば、残酷すぎて禁止になった兵器があるというけれど、兵器の存在それ自体が残酷だろうと思ったんです。「残酷すぎるから」とかそんなグラデーションではなく、なんであれ、兵器を使って痛めつけて殺そうとしている時点でおかしいじゃないですか。そもそも人間が痛い思いをせずに済む、そんな世界はないのだろうか、という思いと、卑近な自分の痛みが繫がって、あの短編になりました。
がんについて改めて考えたり、感じ直してみたかった
―― 本書には、乳がんを題材に扱った作品も三編含まれています。『くもをさがす』で克明に記録されていますが、西さんがカナダで乳がんを宣告されたのは二〇二一年八月一七日。とすると、がんの治療中に作品を執筆していたことになりますよね。
書いていた時のことは全然覚えていなかったので、初出を確認して自分でもびっくりしました。「治療中、こんなに働いてたんだ!」って(笑)。当時は締め切りがあったわけでもないですし、完全に自発的に書いたものだったと思うんです。『くもをさがす』の元になった文章も、いつか誰かに読んでもらおうという意識もなく治療中に書いていたものなんですが、それとは別にやっぱり小説が書きたかったのかもしれません。
―― 同じ題材を元にフィクションで書いてみたいものがあった?
がんを扱った物語はどれも、自分の体験から生まれた種を、自分とは違う人生を生きている女性たちの中に埋め込んで、それぞれの物語を育ててもらいました。そうすることで、私と共にあったがんというものについて改めて考えたり、感じ直したりしてみたかったんだと思うんです。例えば「あなたの中から」(「すばる」二〇二二年四月号)の主人公は、容姿に異様なほどコンプレックスがあって、というより持たされていて、人にどう見られるかばかり気にして生きてきた女性です。これは一編目の「わたしに会いたい」で書いたことでもあるんですが、自分のことを一番知っているのは自分のはずで、自分の命を一番大切にしているのも自分のはずなんだけれども、いつの間にかその一部が他者に委ねられている。彼女の場合は特に、ほぼ全てを他者に委ねていた人生だった。そんな彼女が自分ではコントロール出来ない病気になったら、どんな景色を見ることになるだろうと想像していきました。
―― そう聞くとネガティブ一色の情景が広がるのかと想像する方がほとんどだと思うんですが、違いますよね。
これは私自身の経験から得た本当に個人的な感覚なんですが、乳がんは私に、本質的なことを教えてくれたという気がしているんです。それを、彼女にも経験してほしいという気持ちがあったのかもしれません。
――「あらわ」(「すばる」二〇二二年七月号)は、両乳房の全摘出手術を受けた二八歳の露が主人公です。一〇代の頃から人気グラビアアイドルとして活動していた彼女にとって、Gカップの胸を失うことは深刻な事態を引き起こしますが……本人は非常にカラッとしています。
書きながら「この子、素敵。かっこいい!」って、とても頼もしかったです。私はもともとブラジャーが必要ないぐらいちっちゃい胸だったんですけど、大きな胸を持っていて、それがあなたのアイデンティティだと周囲に言われている子が胸を失ったらどうなるだろう、と思ったんですよね。ただ、彼女は自分がエロい存在であることにすごく誇りを持っているんだけれども、そのエロさが一組のパーツに集中していると思われていることに対して全然納得がいってない。もっと言うと、女の子のグラビアなどでよくある「乳首見えた、見えない問題」なんかバカバカしいと思っている。もし自分と違う胸にセクシャルなものを感じるのであれば、その対象は乳房であるはずじゃないですか。男性と女性で違うのは乳房で、乳首があるのは一緒ですよね。なのに、どうして女性に関してだけは乳首が見えた、見えないで大騒ぎするのか。その辺りの、私自身ずっと疑問に思っていた乳首にまつわるいろいろな不思議さを、あらわちゃんにぶっ飛ばしてもらった感じです。
―― 本書全体を通して、「恥ずかしい」という感情がさまざまな場面で描かれている気がしました。日本人には恥の文化があるとよく言われますが、SNSなどを通して伝達される、それは恥ずかしいことだよ、恥ずかしがれよという圧は、現代社会特有の暴力だと感じたんです。
人にひどいこと言っちゃって恥ずかしいなとか、自分で恥を感じることもいっぱいあります。ただ、本当に自分が自分の体をきちんとコントロールしていて、自分を肯定していて、自分の人生を歩んでいたら、自分の中からは基本的にあまり浮かんでくる感情じゃない気がするんですよね。そう考えると、恥ずかしさって結構他者から手渡される感情なのではないでしょうか。そういう類のものはもう十分です、と宣言したかったのかもしれません。少なくとも、他者から手渡された恥ずかしさは本当に自分にとって必要なのかを考えられる環境にありたい、と日々感じます。