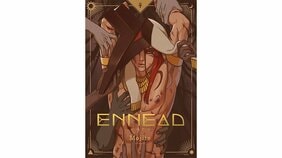いかに娘を「そそる女」にするかに大貴族は心血を注いだが…
なぜこの時代、こんなにも男色が政界に目立つようになったのか。
その理由について五味氏は「まずは京都という狭い政治社会の場のあり方と関連していると見るのが正しいであろう。また院政という特殊な政治構造と関連していると言えるかもしれない。ここでは早急な結論を出すことはすまい」(前掲書)と明言はしていません。
それを強いて追究するのは僭越という気がするものの、学者の立場ではない気安さから考えてみるに、女の性を使った外戚政治に陰りが見えながら、性を使って繁栄するという馴れた手法を彼らが変えなかったため、なのではないか。
外戚政治というのは娘を天皇家に入内させ、生まれた皇子を即位させ、その後見役として一族が繁栄するという、天皇の母方(外戚)が中心となって政治を動かす仕組みのことです。
この仕組みで天皇の母方である藤原氏の摂関家は栄えていたために、平安中期には男女の関係が重視され、いかに娘を「そそる女」にするかに大貴族は心血を注いでいました。多くの妃たちの中で、天皇(東宮)が娘のもとに通ってくれるよう、娘を飾るためにも才色兼備の女房たちを雇うことに余念がありませんでした。清少納言や紫式部、赤染衛門、和泉式部といった天才的な文学者がほぼ同時期に輩出されたゆえんです。

性を使って政治をするという手法を手放せなかった性
ところが平安後期、内親王を母にもつ後三条天皇の即位によって、この潮流に変化が起きます。
権力が、天皇の母方から天皇の父……つまりは上皇(院)に移り、院はそれまで力のあった大貴族ではなく、中流以下の貴族や武士を盛んに取り立てるようになります。
その際、院は中流貴族と男色で以て結びつき、権力に陰りが見えつつあった頼長のような大貴族もまた中・下流貴族と男色で結びつくということをした。
それはつまり、外戚政治の時代にあった「性=政」の観念がそのままスライドした結果ではないか。
天皇(東宮)と娘をセックスさせることで生まれた皇子の後ろ盾として権力を得る――セックスで結びつく、繁栄するという政治の仕方をしてきた彼らは、娘の性を使った政治の効力が低下しても、セックスを使って結びつくという方法を捨てなかった。