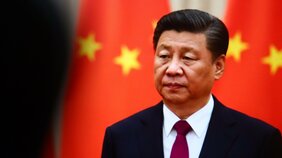こどもNISAは「国家によるリスクの個人化」である
2026年の日本を語るとき、まず決めておくべき前提がある。
今年は「何が起きるか」の年ではない。すでに起きているにもかかわらず、政策的・言語的に先送りされてきた問題が、いよいよ生活の領域で顕在化する年だ。
しかもその影響は、まず国民の生活から始まる。市場は最後に必ず数字として回収する。政治はその途中で言葉を失うことになるだろう。
ここ数年、日本は円安を「放置」してきたのではない。正確に言えば、円安を止めると短期的に不都合が生じる政策構造を選び、それを国家運営の前提としてきた。
輸出企業の利益、株価水準、名目税収。これら短期の指標を優先する結果、通貨価値の維持が相対的に後景に退いた。
そしてその状態のまま、国民に「投資で救われろ」と促してきた。今年、この順序の倒錯はスローガンではなく、生活実感として露出してくる。
その焦点は「こどもNISA」の是非そのものではない。問題は、それが円安容認の政策環境と切り離されない形で語られている点にある。
本来、投資促進政策は、賃金が上昇し、通貨価値が安定し、生活に一定の余力があるという土台の上で初めて機能する。余力のある家計が長期で資産形成を行い、経済全体の厚みが増す。これが健全な順序だ。

ところが今年の日本は、その逆をさらに進めることになる。
円安の進行により実質購買力が低下し、食料品やエネルギーといった生活必需品の価格上昇が常態化する一方で、金融資産を持たない、あるいは投資余力を持たない世帯が相当数存在することが各種統計から示唆されている。
そうした状況下で、0歳から利用可能とされるこどもNISA制度案を掲げ「非課税で株を持てば将来は安心だ」というメッセージを一律に配布する。
生活基盤の脆弱化というリスクを解消しないまま、将来不安への対応を個々の家計に委ねる構造である。資産形成支援というより、「国家によるリスクの個人化」と表現する方が実態に近い。
ここで一度、世界の通貨の力と日本円を並べて見ておく必要がある。この数年で、日本円は実質的におよそ3割程度、通貨としての購買力を力を失っている。
一方で、同期間にスイスフランは約3割上昇し、年平均ベースでは4割前後の円安が進行している。米ドルやユーロも、対円では上昇、少なくとも大きな下落は回避してきた。
インフレ抑制のために景気を犠牲にした国でさえ、通貨価値の防衛自体は優先してきた。その中で日本は、相対的に通貨防衛の優先順位を下げてきたと評価されうる。円の価値が3割低下したのは、単なる市場の気まぐれや一時的な外的ショックだけでは説明できない。