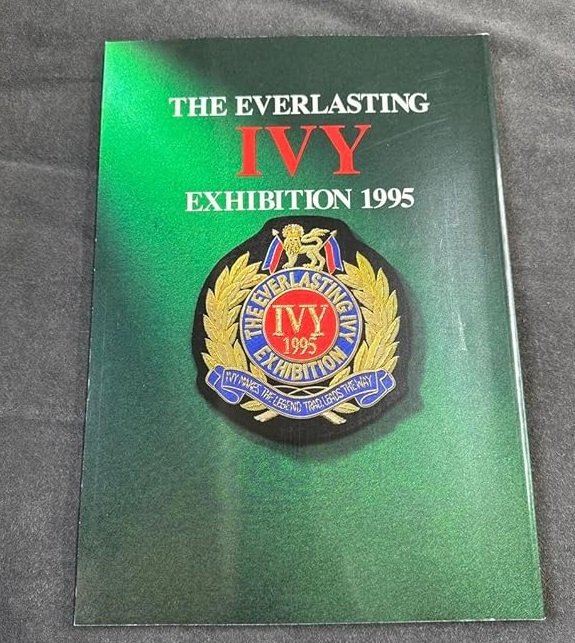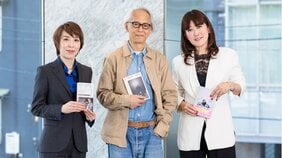渋カジ、日本で初めてファッション雑誌を捨てた若者たち
1980年代の終わりに登場した「渋カジ」は、渋谷カジュアルの略称である。「渋カジ族」と呼ばれることもある彼らは、一つ上の世代にあたる新人類へのアンチテーゼともいえる存在だ。
新人類と呼ばれた若者たちは、全身をDCブランドで固めていた。デザイナーの作った個性的な服を上下で揃え、トータルコーディネートをそのまま着ていた。一方、渋カジの特徴は「定番アイテム」を自分なりに組み合わせて個性を表現することだった。彼らは、デザイナーや雑誌の提案を鵜呑みにせず、自分で考えた。
もう一つ、渋カジがこれまでの日本の若者ファッションと決定的に違うことがある。
日本で初めて路上から生まれて、メインストリームになったファッションであることだ。
『ポパイ』などで、マニュアルがあふれて、若者はインプットばかりされてきた。それが八〇年代の終わりになって、やっと自分たちで自分たちのスタイルを加工・編集しはじめた。その象徴が渋カジです。(略)あれは、初めて街が生んだスタイルだったんです。それまでのアイビーにしろ、イタリアン、ロンドンパンクにしろ、海外にルーツがあって、形だけ取り入れるところがあった。ところが、渋カジではそのままの格好がどこにもなかった。(前掲書、『永遠のIVY展―戦後のライフスタイル革命』日本経済新聞社、1995年)
セレクトショップとして日本の若者たちに定番アイテムを届けてきた「ビームス」の創業者・設楽洋は、渋カジが「初めて街が生んだスタイル」だったことを強調している。
みゆき族、六本木族など、街の名前のついた「族」はこれまでも生まれてきた。
これまでの族と渋カジ族の違いは、彼らがファッション雑誌を必要としていなかったことである。太陽族や暴走族のように、映画やテレビの真似をしたわけでもない。渋カジは海外にも存在しない、日本に固有のファッションだった。
ファッション雑誌の中に存在せず、路上にだけ、ある。日本のファッション史における記念碑的な現象である。