三者三様のファッションとの関わり
平芳 「ファッション」とは、現代では流行の服といった意味で使われる言葉ですが、語の歴史としては1300年頃までさかのぼることができます。元々は形、近世では作法やふるまいといった意味合いが強かったんです。
豪華に着飾ることができたのは貴族階級、つまりごく限られた人々であった時代には、目まぐるしく流行が変化することはなかったんですね。西洋においてファッションが大衆化するのは、フランス革命や産業革命などの社会変革によって市民社会が成立し、既製服の生産体制が整った近代以降のこと。
一方で「モード」というフランス語は、女性名詞の「モード(la mode)」が生活様式を表していましたが、のちに男性名詞の「モード(le mode)」が登場することで、流行という意味に変化していきます。
日本では1980〜90年代にかけてハイエンドなデザイナーズブランドを指す言葉として用いられました。モード系とかモード誌といったように。同じ頃に登場した「セレクトショップ」もまた、和製感のある用語ですね。
栗野 はい。セレクトショップは海外では一般にマルチレーベルストア、またはコンセプトストアと呼ばれます。僕は1978年にビームスに入社し、初めは主にアメリカのライフスタイルから派生する服や雑貨などを紹介していました。
その後1989年にユナイテッドアローズを立ち上げるんですが、当時ニューヨークのバーニーズとかロンドンのブラウンズなどを視察して、日本にもこういう店があったらいいな、という思いで店のコンセプトを作っていきました。
単に服を仕入れて売るのではなく自分たちの美意識で編集し、さらにはお客様の視点で「この値段で買いたい」と思える価格で品揃えをするために自社輸入して販売していく。
その後はバイイング(商品の仕入れ)した商品に加え、プライベートレーベルでオリジナルも作っていく、という日本独自の流れもできていきました。
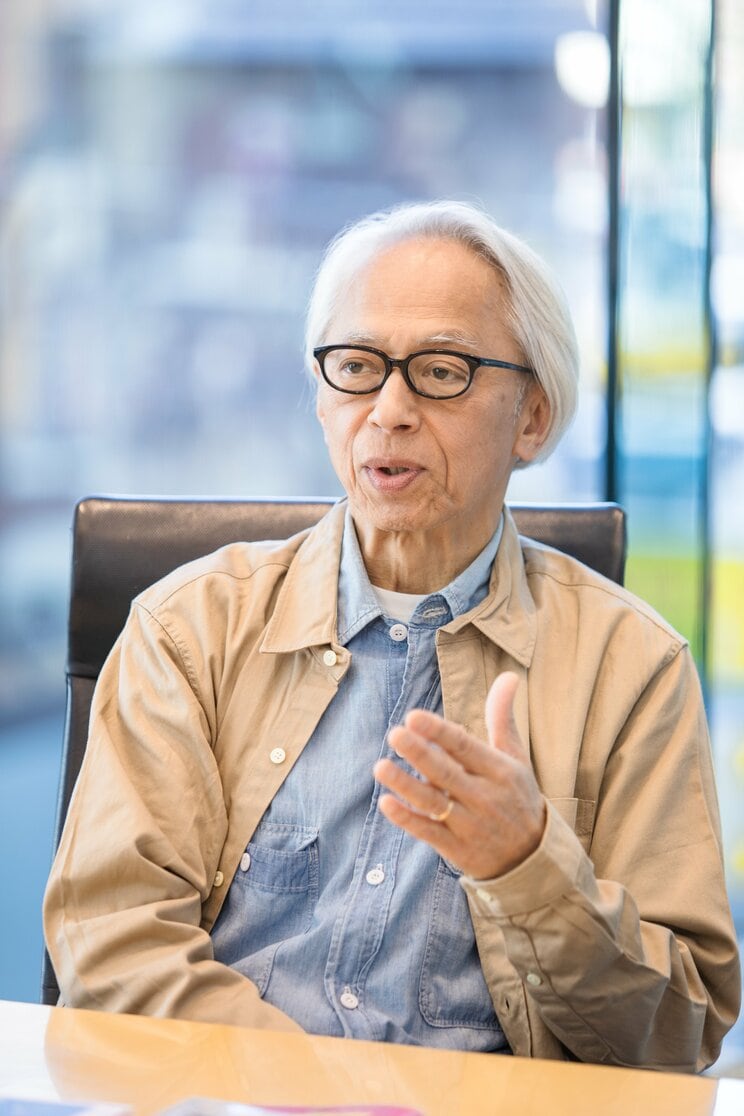
龍淵 私は編集者としてずっとハイファッションを扱う女性誌の現場にいるんですが、2010年にインスタグラムが登場して以来、雑誌の在り方が大きく変わっているのを日々感じています。
かつてはパリやミラノ、ロンドン、ニューヨークなどで発表されるコレクションをもとにトレンド分析をして読者に紹介するのがその役割でした。今は、誰が着ているか?という人物重視の文脈に変わってきています。
どんな服か、ではなく誰が表紙か、によって雑誌の売れ行きが左右される中、 “映える”キャスティングが優先され、肝心の洋服の話が脇に追いやられてしまった。
そんな業界の動向に疑問を持ち、自分のファッションエディターとしてのリアルな日々をThreads(スレッズ)で書き始めたものが今回書籍になりました。
表紙で表現したのはジャケットを着て、オンラインミーティングのためPCに向かう「映える私」と、パジャマ姿で机の下には散らばった洗濯物がある「映えない私」、その両方がどちらも真実だということ。この本は、映えばかりが評価される昨今の風潮へのアンチテーゼでもあるんです。






























