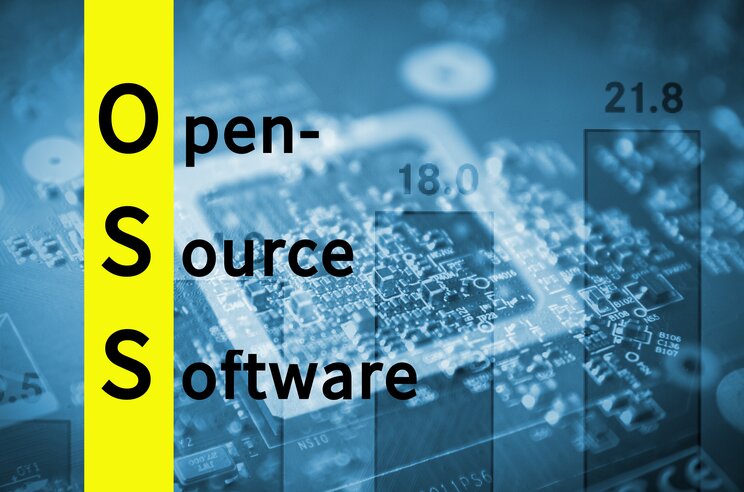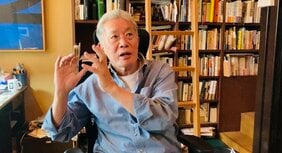インターネットは基本的に「オープン」である
Xのアルゴリズムが一般にも公開されていること。それが示唆していることは、たとえアルゴリズムが公開されたとしても、それが一般のユーザーからは社会的ブラックボックスとして扱われてしまうことには変わりがないということだ。
このことは、プラットフォームの基盤にあるインターネットのアルゴリズムの状況を考えてみるとより興味深い。
企業運営によるプラットフォームのアルゴリズムは確かに非公開であることが多い一方で、その基盤としてインフラ化しているインターネットのしくみの多くは、「OSS(オープンソースソフトウェア)」とよばれる、一般公開されたアルゴリズムによって動作している。
OSSとは、インターネット上などでそのプログラムの「ソースコード(プログラミング言語によって記述された処理手順そのもの)」を原則として無償で公開することで、複数の開発者による共同開発を可能にし、コミュニティによる継続的な改良を企図したソフトウェアを指す。
インターネットが普及する以前は、ほとんどのアルゴリズムは一部の企業に独占されており、ソースコードはまさに「秘密のレシピ」として秘匿されるのがあたりまえであった。
しかし、インターネットそのものはもともと学術ネットワークを中心に利用者を拡大してきた「管理者不在」のネットワークだったという背景もあり、収益目的ではなく共同してオープンな開発を進めていく土壌をもっていたため、OSSの思想と相性がよかった。実際、インターネットの基盤となるアルゴリズムやプロトコル(通信手順)のほとんどはOSSによって(今でも)実現されている。
インターネットの基本的な通信手順を定めたTCP/IPや、ウェブページの通信手順を定めたHTTP、メール送信の通信手順を定めたSMTPなどのプロトコルは、基本的にその仕様はすべてオープンであり、世界中のユーザーに共有されている公開情報である。
それだけでなく、誰でも自由に改善提案を行うことができ、オープンな場で議論されて、よりよいアルゴリズムに変容していく可能性に開かれている。