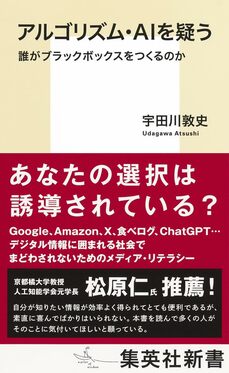ユーザー自身の本来の目的は無視される
社会心理学者のショシャナ・ズボフは、このようなプラットフォームによる主体のデータベース化が、人間を監視することで収益を上げる「監視資本主義」だと批判的に論じている。
監視資本主義において、プラットフォーム企業がユーザーのデータベースを独占的に保有することは、情報の流れを自動化するというよりも、ユーザーの行動そのものをアルゴリズムによってコントロールし自動化することが目的となる。
プラットフォーム上のアルゴリズムは、ユーザーを、広告主という他者の目的を果たすための手段として扱う。そこではユーザー自身の本来の目的は無視されることになる。
すなわち、ユーザーは自分の意志で広告の商品を購入しているというよりも、プラットフォームのアルゴリズムが構築する予測に合致するように購入させられる道具にすぎない、というのだ*2。
実際、アルゴリズムによって商品化された行動ターゲティング広告をみたユーザーが、ターゲティングどおりに購入したとして、その「選択」にどこまでユーザー個人の「主体性」があるといえるかは疑わしい。
たとえそのタイミングで必要としていた商品だったとしても、類似のサービスや機能を満たす商品の選択肢は他にもあったかもしれない。あるいは広告掲載をしていない商品の中に、より価格の安い商品や自分の好みに合う商品がある可能性に気づかないまま、広告主の商品を買わされている可能性もあるわけだ。
プラットフォームは、大量の選択肢の中から最適な自己決定を実現するためのシステムであったにもかかわらず、アルゴリズムによる過度なパーソナライズによって、かえってその選択の「自由」を制限する結果をもたらしているとも考えられる。
情報オーバーロード環境において、その情報量をアルゴリズムによって縮減することは、主体としての選択の「自由」を自ら放棄するという逆説につながっているのだ。
脚注
*1 Google (2025)「Google について」(2025年2月10日取得 https://about.google/?hl=ja)
*2 Zuboff, S. (2019=2021). The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier
of Power. PublicAffairs. (野中香方子訳『監視資本主義│人類の未来を賭けた闘い』東洋経済新報社)