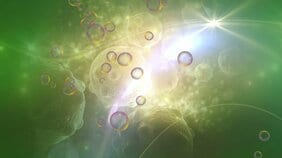すでに動き出している自治体の成功例
私が苛立つのは、すでに成功例があるにもかかわらず、全国展開されていないことだ。
佐賀県では、中学3年生の88.9%が検診に参加し、感染が確認された生徒の除菌も順調に進んでいる。長野県の高校では11年間にわたって検診を実施し、99.7%という驚異的な参加率を達成した。
これらの自治体は、学校の健康診断で集めた尿検体を活用することで、追加の負担を最小限に抑えている。技術的にも運営的にも、全国展開は十分可能だということが証明されているのだ。
世界は動いている。予算がない、は通用しない
2020年の台北国際コンセンサスでは、胃がん高リスク地域における若年成人へのピロリ菌スクリーニングと除菌が推奨されている。韓国、台湾といった国々も、すでに対策に乗り出している。
日本は世界有数の「胃がん大国」だ。なぜ最も積極的に対策を進めるべきなのに動かないのか。このままでは、アジアの中でも予防医療後進国になってしまう。
「予算がない」という言い訳は通用しない。
厚生労働省の研究によれば、ピロリ菌除去後の胃がん関連医療費は99.9%削減された。中学生全員の検査費用と、陽性者(5%程度)への除菌治療費なんて、1人の胃がん患者の治療費と比べても微々たるものだ。
手術、抗がん剤、入院費、そして働き盛りの人材を失うことによる社会的損失。これらを考えれば、中学生へのピロリ菌対策は最高の「健康投資」だ。
実現を阻む本当の壁
なぜこんな合理的な政策が実現しないのか。
一つは、現在の医療システムが「治療」に偏重しているからだ。胃がんが激減すれば、内視鏡検査や手術、抗がん剤といった巨大市場が縮小する。予防よりも治療の方が儲かる――この構造が変わらない限り、真の改革は難しい。
もう一つは、日本特有の「責任回避」文化だ。新しいことを始めるには誰かがリスクを取らなければならない。「感染症」という言葉に対する過剰な反応、プライバシーへの懸念、前例がないことへの恐れ。これらが複雑に絡み合って、誰も動けなくなっている。