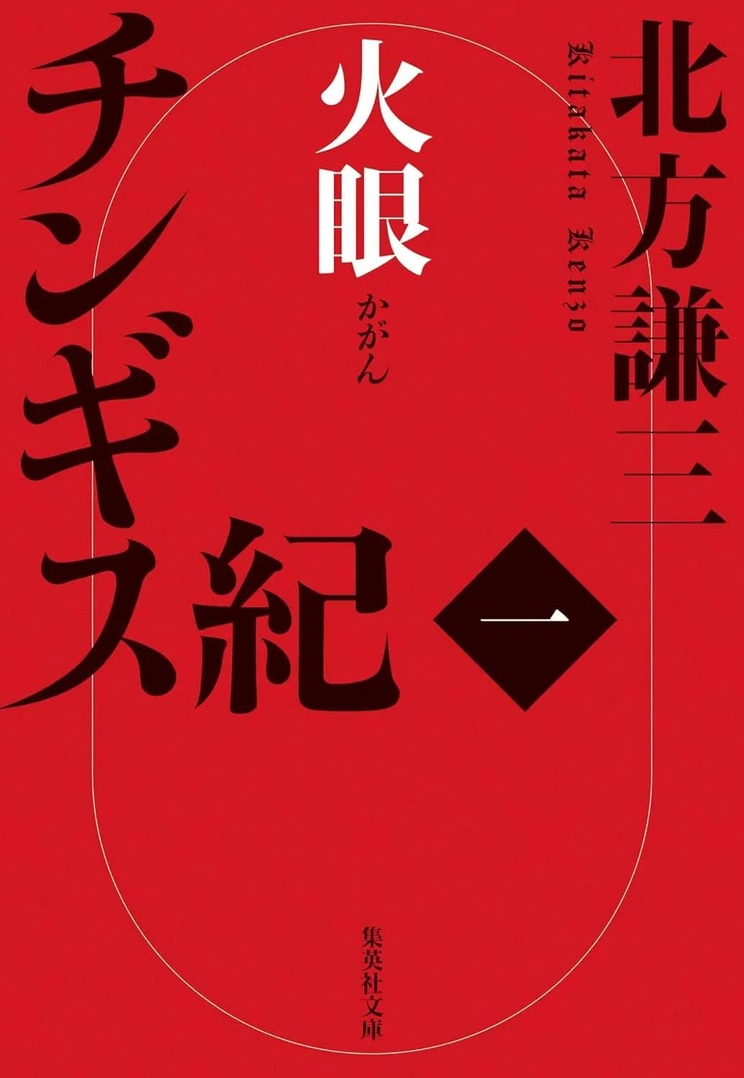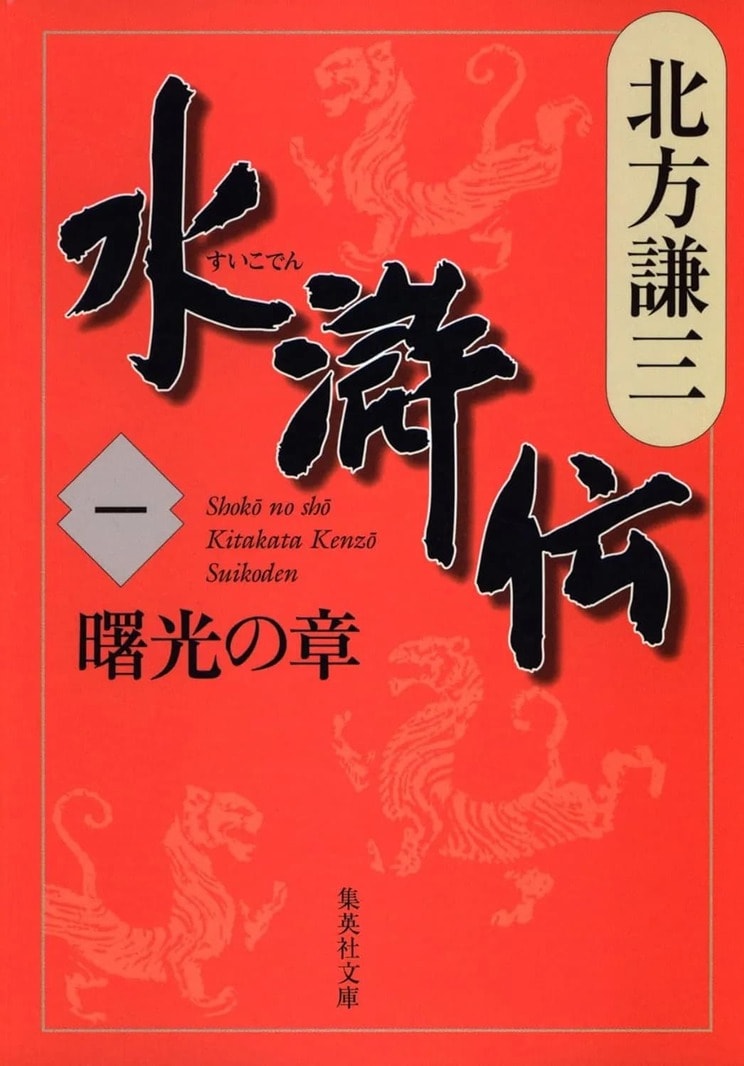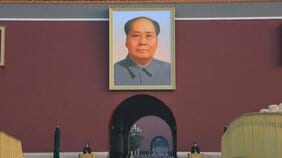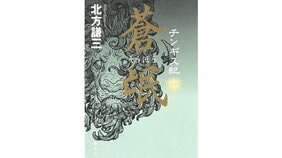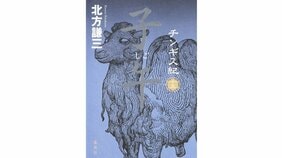国とは何か、日本人とは何か
加藤 元寇を書こうと思ったのはどうしてなんですか。それも『チンギス紀』の後に。
北方 『チンギス紀』のその先を書こうと思ったら、面白いのは孫のクビライの時代です。それに、私がずっと書いてきた中国大陸の歴史のなかで、日本と国同士で直接関わる最初の出来事が元寇なんです。
加藤 ああ、そうですね。日本と大陸の戦いを書くとしたら元寇になるんですね。
北方 そのときの日本側の指揮官だった北条時宗を、日本人としてきちんと書いてみようと思ったんです。一度目の元寇をなんとか退け、さらに石垣を築いて、もう一回来られるものなら来てみろと備えた。神風が吹いたなんて言われているけれど、それだけで勝てるはずがない。当然、そこには戦った男たちがいた。これは私の最後の大長編になると思うけれど、日本人の不屈さを書きたいというのも大きな動機ですね。
加藤 歴史としての日本と大陸との関わりを描くということですね。
北方 クビライがつくった帝国が歴史上、世界で一番大きくなる瞬間を描くことになるし、その同じときに日本という豆粒みたいな小国とぶつかって負ける瞬間も書くことになるでしょう。
加藤 なるほど。国と国とがぶつかり合う物語になっていくんですね。国とは何かという問いも、すでにこの第一巻で出てきていますね。
北方 国とは何かという問いは、実は『水滸伝』を書いたときから始まっているんです。もちろん国とは何かなんて答えは出ないですよ。でも、私たちが国と呼んでいるものは何なのか、という問いはずっと存在してきました。『森羅記』では、国とは何かに加えて、日本人とは何なのか、そういう民族的なテーマも入ってくるだろうと思います。
加藤 『森羅記』を書いていて、どんなところに新鮮さを感じますか。
北方 物語の舞台がどんどん変わることですね。日本のなかだけでも、北九州の五島列島や唐津に始まって、鎌倉はもちろん、琵琶湖と若狭湾を拠点にする波瀬水軍が出てきて、津軽半島の十三湊も出てくる。大陸にもモンゴル、南宋にいくつも視点があるし、高麗も出てきます。場所が変わるたびに視点も変わる。群像小説にぴったりなんですよ。それぞれ、いまはまだばらばらに動いているけれど、やがてつながりが出てくる。連環ができていくことが小説を書く醍醐味です。
稗史に目を向けるのが作家の仕事
加藤 歴史上の事実を押さえながらも、空白の場面でドラマをつくっていく。それがやがてつながっていく。たしかに面白いですね。
北方 そうです。それに歴史的な事実ってそんなにたくさんはないんです。たとえば、作品の冒頭でクビライが旅をしているというのは私の創作なんですよ。実際には、クビライが三十代まで何をしていたかはよくわからないんです。
加藤 そうなんですね。どこまでが北方さんの創作かわからないまま読んでいたんですけど。
北方 モンゴルは文字ではなくて口承で歴史を伝えていたから、記録が残っていないんです。
加藤 ヒントになるような史料はあるんですか。
北方 のちに口承を文字で書き起こした『元朝秘史』というものはありますね。ただ、読んでみると民話の類いで歴史書という感じではないんですよ。
加藤 どこまで信憑性があるかわからないということですか。
北方 そうですね。でも作家は正史に目を向けては駄目だと思います。正史は学者が研究するもので、作家が目を向けるべきは稗史なんです。稗史は正史に対して非公式の、言い伝えのようなものをいうんですが、そのなかに真実が含まれているかもしれない。
たとえば、日本神話でスサノオノミコトがヤマタノオロチを退治する話があるでしょう。退治したヤマタノオロチは八つの頭と八つの尾を持った大蛇だって言い伝えられているけれど、それが反政府勢力の象徴だという解釈もできるんですよ。想像力をもって稗史のなかにある物語を取り出すのが、作家の仕事だと思いますね。
加藤 史実が少ないと、人間を描くときの立脚点みたいなものも少ないので、キャラクターづくりが難しくないですか。
北方 どんなキャラクターにしようとかは考えていません。私が小説で人間を描くときは、こういう人物をどう描こうかと考えるわけじゃない。この人間がこうなってしまった、ということを描くんです。
小説のなかに登場人物が現れる。その登場人物なりの感覚があり、思想がある。その人間が動き始めたら、作者の私にもどうにもならない。書いているうちに思わぬ方向へどんどん行ってしまって、死んでほしくなかったのに死んでしまうやつがいたりする。
加藤 書く前に考えないんですか。北条時頼はこういう人間だっただろうとか、北条重時はこうだとか。
北方 考えないです。登場人物に何かあるたびに、それに対する反応を書いていく。そうすると性格が表れてくる。
たとえば、クビライがタケルという水師の青年と出会う。お互い相手が誰だか知らない。ただ、出会う。二人が出会ってどういう話をするのかというところから、二人の人物像が少しずつできてくる。そうすると、二人が次に動くときに、その人間ならではの動きをし始めるんです。
加藤 書き分けることを意識しているわけではないんですね。それなのに、北方さんの小説のキャラクターはいつも生きていますよね。
北方 たぶん、全部の登場人物が自分なんですよ。つまりスケベだったときの自分とか、腹を減らしてるときの自分とか。卑怯なことをする主人公だって自分。全部、自分だと思って書けば、無限にありますよ。
書き分けるっていうのはテクニックの問題ですよね。そうじゃなくて、全部の登場人物が自分の一部である、それが無数にあると思って書けば、それぞれが自然と違う人格になる。同じ人格は出てきません。『三国志』から『水滸伝』『楊令伝』『岳飛伝』、それから『チンギス紀』。何人出したかわからないくらいたくさんの登場人物を書いてきましたが、「人格が重なってますよ」なんて言われたことはない。「どうしてこんなことを思い付くんですか」って訊かれることはあるけど、「ある日の俺だよ」って答えることが多いですね。
加藤 自分の一部だとしたら、愛着も湧きますよね、キャラクターに対して。
北方 最初は自分だけど、書いているうちに自分じゃなくなっていくんですよ。そいつが歩き始めたらもう駄目。制御不能になりますね。どんなに愛着があってもね。ちょっと待て、と思うときもありますよ。そっちのほうへ行くなよと。でも止まらない。それはもう生きてるからです。
加藤 なるほど。自分の欠片がどんどん変わっていって、自分から離れていくんですね。それで、最後は死んでしまうこともあると。
北方 死んでしまうのはもうどうしようもないですね。死ぬように生きてしまうんですよ。そうなったら、できることは酒を飲むしかない。弔い酒を飲むくらいしかね。