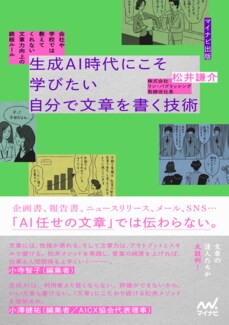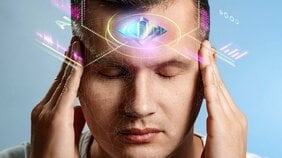接続詞は「ないと道に迷うシーン」でだけ使うべき
さて、ではこのルールをすべての局面に適応すれば、わかりやすく、素敵な文章になるのでしょうか。私は違うと思います。
接続詞は不要なものは削除しつつ、「ないと道に迷うシーン」でだけ使うべきなのです。道路案内でも100メートルごとに「このまま直進」と出たら煩わしいように、「そのままでOK」を示す順接は、省略可能なケースが多いのです。
「この書籍は面白い。すごく売れています」。接続詞を排除しましたが、これで道に迷う人はいません。では、逆接はどうでしょう。「この書籍は面白い。松井某は面白味に欠けます」となってしまっては、文章として言いたいことが不明瞭ですよね。「この書籍は面白いんだけど松井はちょっとなぁ……内容はまあ面白いんだけどさぁ」という書き手の逡巡が、道しるべとしての「しかし」に込められていたわけです。
ふたつ前の段落の冒頭で使った「さて」はどうでしょう。これは「転換」の接続詞です。これまでの流れを汲んで次の話題に行く区切りの役割で、順接の意味が強いため、省略できます。
では、もうひとつの転換の接続詞「ところで」はどうか。そこで区切りがついたという気持ちを必ずしも感じさせないワードで、「ところで、その考え方は間違っていないでしょうか?」など、やや逆接のニュアンスを含みます。もしくは「まったく違う話題(予想できない話題)へ切り替える」合図でもある。その意味で、「ところで」の削除は難しいのです。
流れに乗っている文章では接続詞を省略してよい/予想外の文章をつなぐ場合は接続詞が必要。これが大まかなルールです。文章生成AIを用い、出力された文章を結びつけて長文にする場合、こうした接続詞の存在が、その文章の読みやすさを左右する道案内になるのです。これは、ここ数年で得られた新しい「気づき」でした。

■まとめ
・AIで生成された文章はぶつ切れ。長文を作るためには「接続詞」が重要となる。
・接続詞は道しるべ。これを見れば、文章はどんな方向に進むのかわかる。
・流れに乗っている文章では接続詞は不要。予想外の文章をつなぐ場合は接続詞が必要。
文/松井謙介