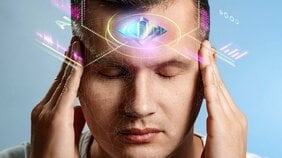生成AIには「書きたい文章」がない
2023〜2024年は、ライター、編集者など文章を生業とする方にとって、歴史的な転換点を迎えた年と言えるでしょう。そう、ChatGPTに代表される生成AIの爆発的な普及がその理由。「画像生成AI」も大きな話題にはなりましたが、画像生成に比べ、より汎用性が高く、多くの業務に実装できうる点で、「文章生成AI」の注目度は桁違いでした。
文章生成AIは、文章生成だけではなく、情報収集、翻訳、要約、文章拡張、校正など、文章にまつわるおおよそすべての業務に適用可能。そのあまりの精度の高さから「リリース起こしライター、もうオワタ」という流れになっています。
ここで大事なのは「ライターオワタ」ではなく、「リリース起こしライター」が終わる、ということ。そう、文章生成AIは、主義主張のないライターの代わりはできるのですが、内発的に(指示なしに)文章を生成することはできません。なぜなら、彼ら(AI)には「私」がなく、それはすなわち「書きたいこと」がないからです。
生成AIが出力できるのは「ぶつ切り状態」の文章
私は、2023年の夏に『生成AI導入の教科書』(ワン・パブリッシング刊)という本を編集しました。著者はWebメディア「AINOW」の元編集長で、彼は息をするくらい当たり前にChatGPTを活用し、本書を約半月で執筆(288ページ!)。その際、ChatGPTを以下の用途で使ったとのこと。
① 構成の生成
② 一般論の生成
③ インタビュー記事の整え
④ 文章の校正・整え
こうして生成された文章は、論理的な破綻もなく、一般の書籍として十分に楽しめるものでした。ただ、ひとつだけ、「生成AI時代は、この文章技術が重要になるなぁ」と思ったことがあります。
それは「接続詞」の使い方です。
ChatGPTはトークン数(テキストを構成する最小単位のことで、テキストを意味のあるかたまりに分けたもの)に上限があるため、現時点では「一気に10万字の文章を書いて」というプロンプトには非対応。何千字ごとなど、ある種「ぶつ切り」の回答が生成されます。それをつないで一編のテキストにするのは、間をつなぐもの、すなわち接続詞が必要になるのです。
接続詞は大きく分けると「順接」と「逆接」のふたつがあります。
順接 …(例) この書籍は面白い。だから、すごく売れています。
逆接 …(例) この書籍は面白い。しかし、執筆者の松井某は面白味に欠けます。
まず順接は、ふたつの文、または句の接続方法で、前の文が後の文の順当な原因・理由などになっているもの。順接の接続詞を用いれば、ふたつの文でとても自然な流れを作ることができます。一方、逆接は二文の接続で、前の文から予想される事象「以外」の結果が示される関係を結ぶ場合に使うもの。話が大きく変わるなど、違う方向に進む際に用いられます。
要は、接続詞は「道しるべ」で、高速道路などの分岐案内のようなもの。接続詞を見れば、そこに書かれている文章はどんな方向に進むのかが、なんとなくわかるのです。