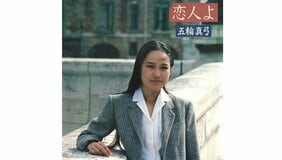省人化に背を向けるトリドールの特異な戦略
トリドールは従業員が心から幸福感を持って働ける職場環境を整えることを重視している。自ら考え行動するという内発的動機を発生させ、この内発性が顧客に感動をもたらす体験を生み出す原動力だとし、これを「ハピカン繁盛サイクル」と名付けた。
新たな制度では、従来の店長制度を刷新し、「ハピカンオフィサー制度」を導入。これまで店長が担っていたオペレーション業務の一部を他メンバーに移管し、「ハピカン繁盛サイクル」の実現が主たる役割になるという。具体的には人材の育成やマネジメントを行ない、従業員一人ひとりの内発的動機を引き出すというものだ。
飲食チェーンの店長の役割は大きく3つに集約される。1つ目は売上と利益のお金の管理だ。2つ目は食材などのモノの管理。そして3つ目がスタッフの管理である。
しかし、今では店舗の経理やシフト、受発注をスムーズに行なえるシステムが多数登場した。かつて時間がかかっていたシフト作成業務は、一部を自動で作成できるようにもなっている。デジタル化によって業務負荷の軽減が図れるようになったのだ。
トリドールは2019年12月に「ITロードマップ」を策定し、システムの刷新と業務改革に着手していた。早くからデジタル化に取り組んだことで、オペレーションや業務負荷軽減を実現していたのだ。
一方、「丸亀製麺」はロボットによる配膳の効率化やセントラルキッチンには否定的な姿勢を示している。各店舗で麺づくりを行ない、麺職人の育成制度も整備している。省人化ならぬ増人化が特徴で、「ハピカン繁盛サイクル」という考え方のベースになっている。
従って、各店舗の人材の育成は会社の成長を支える重要な要素なのだ。世間では店長2000万円という言葉が独り歩きしているが、従来の店長業務という枠組みは解体され、人材育成によって繁盛店を作るというハイレベルな仕事を任されるというのが実際のところだろう。