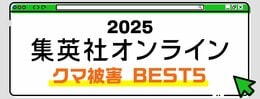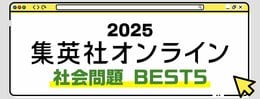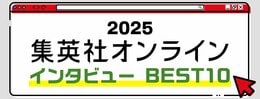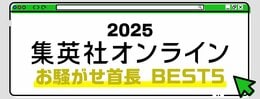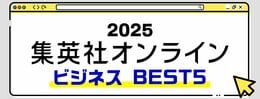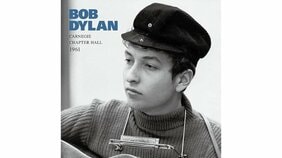終身雇用は終わったのか?
こうした議論の多くが、終身雇用の時代が終わったことを前提としている。ただ、いったい誰が「終わらせた」のか? いつ終わったのか? 終わりとは何か?
終身雇用の学術的定義として代表的なものを挙げよう。
「従業員が定年に達するまでひとつの企業に長期勤続する慣行」
注目すべき箇所が2つある。まず「慣行」であり明示的な契約には基づかない。そして主語は「従業員」なのだ。従業員は被雇用者であり雇用するのは企業なのだから、終身雇用は企業が主語じゃないとおかしい気もするけども、主語は従業員である。
終身雇用を支えてきた条件が3つある。勤続給、退職金制度、福利厚生(制度)である。つまり、勤める期間が長いほど報酬が増え、辞める際にも手厚い返礼があり、生活へのサポートもある状況だ。
企業側が「長くいてくれたらプレミアム(得)をつけるよ」と言って、ほなずっとおるわと社員が呼応してきたのだ。終身雇用は企業側と労働者が互恵関係にあれるシステムとして確立されてきたのである。
産業社会学者の神谷拓平氏は、終身雇用を次のように定義する。
「終身雇用とは年功賃金の『企業間移動抑制機能』によって促進される長期勤続傾向であり、長期雇用傾向である」
年功賃金によって別の企業に移るインセンティブが減じられるため、同じ会社に居続ける勤続傾向が「労働者に」発生する。それは同時に「企業の」雇用傾向でもある。終身雇用は、企業と労働者の互恵関係に裏打ちされて存続してきたのだ。