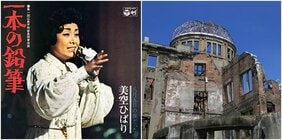圧力こそがダイヤモンドを生む
李 今回の本で紹介したPol.isという仕組みは、台湾がUberを導入する時の議論に使われたテクノロジーなんですけども、「賛成」「反対」「どちらでもない」の意見を投入して、さらに論点を加えていくと、違うグループ同士でも、「ここだったら妥協できるね」という意見の一致が可視化されていくツールです。ウェブ上で無料で使えます。
ですから、いきなり国会で実用されることが難しくても、まずは学校や町の自治会で使ってもいいし、会社の会議で使ってもいい。そのように日常生活のレベルで、「対立する者同士で歩み寄るポイントを見つける」体験を共有していく。そうすれば、「分断を煽って敵を糾弾する」とか、「自分の信者を使って気に入らない人物を追い込む」みたいなことをする人たちが出てきた時の「免疫」になるのではないか。そういうささやかな希望を持っているんです。
三牧 Pol.isという台湾発のテクノロジー。社会運動から入ってきたオードリー・タンさんならではの発想ですね。目の前の現実的な問題に関して「どうすれば解決するのか?」というふうに考えないと、出てこないアイディアだと思います。
やはりアメリカとの対照を考えてしまいます。シリコンバレーの富裕者たちは、草の根的な社会運動にはシンパシーも関心もない。むしろ、マイノリティの進出を疎ましく思うマジョリティ側に立っている。彼らは巨額のお金を武器に、自分に都合が良い政治家を後押しし、政府権力に近づく。
トランプ政権に深く入り込んだマスクの場合、アメリカ航空宇宙局(NASA)の部局や人員を削減して、代わりに自身のスペースXを入れるといった具合に、利益相反にあたることまで公然としている。
彼らはよく「人類」を語りますが、人類を実際に危険にさらしている地球温暖化問題をどう解決するか、おしとどめるかといったことには関心がない。むしろ、「地球に住めなくなったら火星に行けばいい」と言い放つ。結局、「人類を誰も取りこぼさず救うために、皆の住処である地球をどう保全するのか」という普遍的な救済計画ではなく、「住めなくなった地球は捨てて、選ばれた自分たちだけをどう救うか」という、かなり選民主義的な計画を追求している。
マスクは民間人でありながら、政府効率化省(DOGE)のトップとして連邦政府の予算削減を進めてきました。そのマスクがまっさきに解体したのは、USAIDという人道支援の中核となってきた機関だったことは、彼が、現実世界に生き、苦しんでいる「人類」には関心がないことを象徴していました。
USAIDは途上国でHIV対策や食糧や水の支援などでどれだけの命を救ってきたかしれない。合理化はありえるとしてもまさか解体はないだろうと思っていたら、躊躇なくほぼ解体されてしまった。マイクロソフトのビル・ゲイツのように、こうしたマスクやトランプ政権の動きへの抗議として、ほとんどの財産を人道支援に使う動きを見せている富裕層もいますが、ゲイツより若い世代の富裕層は、こうした公共の意識を、偽善としても見せることをせず、「自分の金を、自分の利益や野心の追求のために使って何が悪い」という態度です。
こうしたアメリカの現状を見ていると「民主主義でもテクノロジーでも欧米が頂点で、どうやって欧米に近づくか?」ということを自明の前提としてきた議論の根本的な再考が必要だと感じます。トランプ当選の2016年あたりから欧米では民主主義やリベラリズムの限界がいよいよ意識されるようになりましたが、非欧米に目を転ずれば、ちょうどその頃に、台湾でタンさんが政府に入り、デジタル民主主義を強烈に進めていった。
テクノロジーの在り方にしても、民主主義の在り方にしても、台湾はいよいよ今後、これからの世界を牽引していくモデルになり得るとも思うのですが、李先生のお考えはいかがでしょう。
李 テクノロジーで膨大な富を築いた人たちが、政治を利用して稼いでいく。それはまさに今回の本のタイトルに使った「テクノ専制」です。リベラルデモクラシーの世界のリーダーを自称していたアメリカが、民主主義を否定するような行動に出ているという、驚くべき状況。ただ先生がおっしゃるように、マスクがいきなり出てきたというよりは、2010年代ぐらいから徐々に欧米で、民主主義の価値だったり、実際の機能だったりというものが信じられなくなってきている状況はあったと思います。
そこで交代するかのように出てきた台湾、そしてエストニアやウクライナ、アイスランドもそうですけども、やはり周縁の小さな国ぐにが今、「テクノロジーを使っていかに民主主義をアップデートしていくか」という方向に舵を切っている。
オードリー・タンさんと対談した時、「圧力こそがダイヤモンドを生む」という詩的な表現をされていました。台湾はやはり中国からの圧力があった時に、「オープンな透明性のあるガバメント」という枠組みを選ばざるを得なかった。エストニアの場合は、ソ連が崩壊して既存のシステムが全く使えないので、まっさらな状態から始めざるを得ず、そこでテクノロジーを使って、旧ソ連とは違う民主主義的な仕組みを作る必要があった。