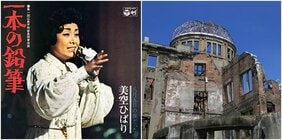ファシズム国家でファシズムの研究はできない
三牧 とりわけナイ教授が懸念していたのは、先ほど述べたUSAIDの解体です。確かにお金を使う話ですが、援助を受けた国の人たちは非常にアメリカを信頼しますし、そうして得られる無形のソフトパワーには、計り知れないリターンがある。そうした面を一切見ないで、「他国民に使う無駄なお金はカット」という無機的で短絡的な発想でトランプ政権は動いている。
アメリカを、旧ソ連や中国といった権威主義国とは違うものにしていた価値がいよいよなくなり、「アメリカの世紀」は終わる。その道を今、歩み出しているわけですよね。
対照的に台湾ではタンさんが、中国という権威主義国の隣にあって、その圧力に対抗するために「透明性のある民主主義」というところに戦略的に賭けている。非常に重要な視点です。かつてのアメリカもそういう視点を持っていました。
ソ連が非常に権威主義的で閉鎖的、だからこそ我々アメリカは民主主義を大切にし、開放路線でいく。その姿勢がアメリカを強くし、魅力的にしてきた。中国が人権侵害や閉鎖的な政策をとっていても、我々は違う。中国の学生も受け入れますと。こういう姿勢だったからアメリカは信頼され、魅力があった。
李 最近だと、ティモシー・スナイダーをはじめとしてイェール大学の教授3名がトロント大学に移りました。スナイダーが逃げるってすごい損失ですけどね。でも、ティモシー・スナイダーも妻のマーシ・ショアも、ファシズム研究という専門分野的にやはり耐え難いでしょう。ギャラリーアイコン
三牧 もう1人、イェール大学からトロント大学へ異動したジェイソン・スタンレーも、「ファシズム国家でファシズムの研究はできない」と述べていました。トランプの任期は4年ですが、「トランプ的なもの」は残存し続ける。そうした長期的な危険を考えての苦渋の選択だったのでしょうね。
6月14日、ちょうどトランプの誕生日だったわけですが、米陸軍創設250周年を祝う軍事パレードが首都ワシントンD.C.で行われました。「民主主義国アメリカは、権威主義国のように軍事力を誇示すべきではない」という抑制的な観念が共有され、長らく軍事パレードは行われてこなかったところ、実に34年ぶりの開催でした。
この同じ日に「ノー・キングス」デモが全米各地2100か所以上で起こり、500万人規模を動員しました。アメリカは王政を否定して誕生したのに、トランプはまるで王のように振る舞っているということで、全米で人々が「NO KINGS!(王はいらない)」と声を上げた。アメリカでも、みんながみんな「トランプのアメリカ」でいいと思っているわけではない。
アメリカが衰退するだけでなく、権威主義化している中で、我々日本も、どうやってそんな世界で民主主義の命脈をつないでいくか、ということを考えなければいけない局面に来ていると思います。