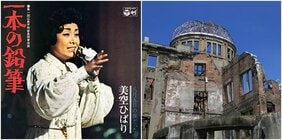長いアメリカの世紀の終わり
李 そして日本も、日本なりの状況であったり環境であったりというものがあるので、欧米をありがたがる必要はない。欧米をありがたがらないというのは、民主主義とか人権を否定する意味ではなく、我々もそれを既に持っているので、見つけだして、育てていくということです。
今回の本で書いた、柄谷行人の「交換様式D」もそうですし、田中優子先生との対談で出てきた「江戸時代の俳諧の連」、E・グレン・ワイルさんが言及していた「日本科学未来館」や「カイゼン」の取り組みなど、日本ならではのPlurality(プルラリティ)や民主主義は、探せばここにあるんです。
欧米の秩序が自壊して、アメリカがリベラルデモクラシーの親玉でなくなっていく。我々はかなり抜本的な世界秩序の変化の時代にいるはずで、「政権与党が替われば暮らしも良くなる」というような話ではないと思います。もっと抜本的な変化、「これからどういう未来が来るか」ということを考える時代に来ているのです。
欧米もアメリカも凋落していく中で、世界はどうなっていくんですかね? 一部では「アメリカが世界の警察でなくなったら、各地で紛争が起きて、世界は危険な状態になる」という予測もあるんですけども、いかがお考えでしょうか?
三牧 今年で戦後80年です。トランプの2期目の就任演説の中で、非常にトランプ、そしてトランプを支持する人たちの心情や世界観を表していると思った一文が、
「アメリカは今まで世界に搾取されてきた」です。
むしろ私たちが見てきた戦後80年のアメリカは、巨大な力で好き放題やって、世界から好き放題搾取してきた、トランプがいう真逆の姿をしていますよね。でも被害者意識は、虚妄ですよ、と指摘したところでなくなるわけではない。
トランプを強固に支持している中西部のラストベルト(錆びれた工業地帯)を中心に、こうした被害者意識が強固に存在し、トランプの煽動によってさらに増幅され、トランプの岩盤支持を形成しているのです。
しかし客観的に見ればトランプ政権は、戦後80年間、アメリカの力の源になってきたものを破壊しようとしている。一番端的なのは、大学や学術機関への攻撃です。
世界の優れた人材がなぜ、ソ連や今の中国ではなく、アメリカに来て勉強したがるのか。やはりそれは、開放性や多様性があり、どんな国の人でもアメリカに来れば自由に発言や好きな研究ができるからです。
アメリカは豊かさだけではなく、自由や民主主義、そうした価値がきちんと尊重されているという信頼があったから、みんなアメリカを目指したわけですよね。結果として、アメリカが強制したわけではなく、世界の有望な若者たちが自分の意志で、学生として研究者として、アメリカにやってきた。
本国へ帰った人たちは、アメリカに特に強制されずとも、アメリカの豊かさや自由への好意的な印象を本国に持ち帰り、自然と本国の親米エリートになる。アメリカに残った人たちも、価値ある研究を続けたり、企業を立ち上げたりして、アメリカをさらに魅力的で豊かな国にしてきた。
そういうアメリカの力の源を、トランプ政権は自分たちの手で破壊している。トランプ政権は、ハーバード大学への助成金を凍結し、その分を労働者の職業訓練の予算に充てるという計画も表明しています。
支持層の労働者へのアピールなのでしょうが、大学への助成金を財源にしなくてもできることで、どこまで本腰を入れた政策かも疑問です。結局、労働者の喝采や一時的な支持を求めて、エリート大学を痛めつけ、分断された社会状況を生み出し、戦後アメリカの力や富の重要な源泉となってきた研究力やソフトパワーを自ら損なっている。
「ソフトパワー」という言葉を生み出した国際政治学者ジョセフ・ナイ教授が、5月に亡くなられましたが、ナイ教授が最後に書いた記事のタイトルが「『アメリカ』の世紀の終わり」(フォーリン・アフェアーズ誌)であったことは象徴的です。戦後80年間のアメリカのパワーの源泉がトランプによって破壊され、長いアメリカの世紀は、いよいよ終わろうとしている。このことへの強い危機感が表れたタイトルです。
『ネイチャー』の調査によれば、3月の時点で既に7割の科学者が国外に出ることを検討しているという状況でした。トランプ政権の方針に沿わない「リベラルな研究」として、気候変動とか公衆衛生といった分野は、予算も雇用もどんどんカットされて、研究が困難になっています。