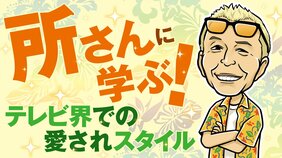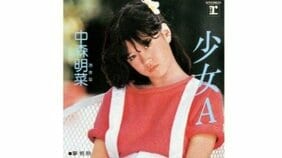民放の「商業放送」というビジネスモデルは、大きな曲がり角に…
インターネットがなかった時代には、映像コンテンツは、基本的にはテレビ放送でしか見ることができませんでした。後は、映画館に行って映画を見るくらいです。そして、テレビ放送は大都市圏でも6つのチャンネルしかなく、地方ではNHKのほか、民放が1~2チャンネルしかないというところも珍しくありませんでした。選択肢が極端に限られていたのです。そうした条件下で、人々は毎日何時間もテレビを視聴していました。
しかし、今やインターネットにアクセスすれば、何十万、何百万というチャンネルの中から、見たい動画を選ぶことができます。その一つ一つすべてが、基本的には「広告放送」です。つまり、一昔前では考えられないほど多くの「広告放送」が流れている時代になったのです。
インターネット上で「広告放送」を流しているのは、YouTubeだけではありません。ショート動画の投稿サイトであるTikTokは若者を中心に人気を集めていますし、多数のアカウントを抱えるFacebookやX、Instagramでも大量の動画が流れています。
これらも、広告を見る代わりに無料で動画を見られるという仕組みは同じですから、一種の「広告放送」と捉えることができます。ネット動画には、大手企業も盛んに広告をつけています。このような「広告放送」の乱立が、テレビ広告に影響を与えないはずがありません。
「供給量が増えれば、価格は下がる」というのが、経済の大原則です。テレビの広告費が減少しているのは、一面から見れば「広告放送の大量供給によってひき起こされた、広告価格の下落」とも捉えられます。
今、人々は何気ない日常の様子から、偶然撮影に成功した決定的な瞬間まで、競うように動画を投稿しています。親しい人とのコミュニケーションの一環として、あるいはユーチューバーの様に生活の手段として、次から次へと動画が投稿されています。今後、社会全体の「広告放送」の量が増えることはあっても、減ることはないでしょう。
そうした中にあって、民放の「商業放送」というビジネスモデルは、大きな曲がり角を迎えているのです。