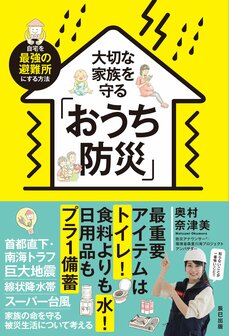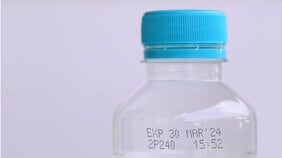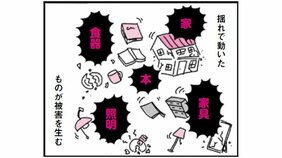地震後の初期消火の大切さ
繰り返しになりますが、火の元の確認は、揺れている最中は危険なので揺れが収まってからです。地震で怖いのは火災です。大きな災害になればなるほど、消防車などを呼ぶことが難しくなります。
火を消すためには初期消火が大変重要になってきます。たとえば首都直下地震で、東京都中野区では、火災で1328棟が焼失する想定ですが、その出火元となる家屋は11棟(中野区民防災ハンドブック)。つまり、延焼する前に、その11棟の火災を鎮火できれば被害は拡大しないとも言えます。
初期消火できる目安は、炎の高さが自分の目線より下の時。火が出た時に複数の人がいる場合は、消火に当たる人・火事が発生したことを近所に伝える人・消防に連絡する人と分担します。
炎ではなく、燃えている物に消火剤をかけるのがポイント。炎が天井に達したら危険なので、その前に避難しましょう。
地域の防災訓練や防災体験施設で、子どもと一緒に消火器の使い方を練習することができます。子どもが一人でいる時も消火器が使えるように教えておきましょう。東京消防庁のYouTubeでも見ることができます。
避難する前に必ずやることリスト
地震が起きると、気が動転し頭が真っ白になることもあります。家の外に避難する必要があった時にやることを、リストにして玄関のドアに貼っておくことをお勧めします。
ただし、火災や家屋の倒壊、津波の恐れがある人は、これからあげることをするよりも、急いで逃げることを優先してください。
「通電火災・ガス漏れ対策」
通電火災は、大地震で停電し、電気が復旧した時、電気器具などから出火する火災のことです。阪神・淡路大震災、そして、東日本大震災でも通電火災が確認されています。避難する前には必ず、電気のブレーカーを落としましょう。揺れで自動的にブレーカーが落ちる感震ブレーカーを設置することもできます。
また、ガスは揺れで自動的に止まる安全装置がついていますが、念のため、元栓を閉めることを忘れないようにしましょう。
「防犯対策」
災害時多くなるのが犯罪です。空き巣に入られないように必ず施錠してから避難しましょう。
「安否確認」
家族がバラバラで被災した場合、安否確認が欠かせません。通信機器を使っての連絡方法は後述しますが、確実にできることは手書きでメッセージを残すことです。
たとえば、玄関の扉の内側に貼ったホワイトボードに「生きています。念のため〇〇に避難します」など一言メッセージを残しておくだけで、別の場所で被災した家族が自宅に戻って玄関を開けた時、安心します(防犯上、外に貼るのは危険です)。
近隣の人同士の安否確認をスムーズにするため、マンションや自治会では、玄関にマグネットを貼ったり、旗を掲げてから避難するという方法を訓練している場所もあります。
避難する時、余裕があったら、近所の方で困っている人がいないか、声をかけてください。
阪神・淡路大震災では、地震によって倒壊した建物から救出され生き延びることができた人の約8割が、家族や近所の住民などによって救出されたということです(内閣府平成26年度防災白書)
文/奥村奈津美 写真/Shutterstock