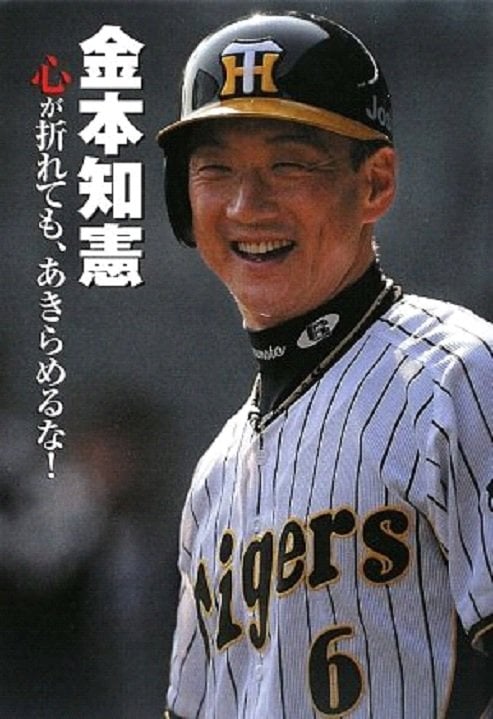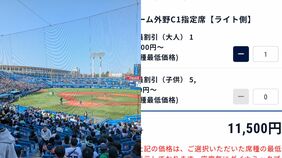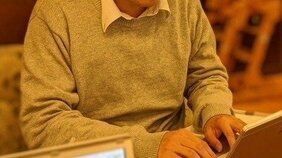本塁打数だけでない「スラッガーの証」となる数値
筆者が注目したいのは、本塁打数や打点数ではなく、その三振数だ。シーズン48三振は2位のキャベッジ(巨人)の41三振を大きく引き離しリーグ断トツ。シーズン換算でも実に171.6三振を喫する計算になる。
ただ、三振の多さは決してネガティブな指標ではない。もともと、佐藤は三振の多いタイプではあるが、過去4年間の三振数の推移は以下になる。
2021年 173三振(126試合/24本塁打)
2022年 137三振(143試合/20本塁打)
2023年 139三振(132試合/24本塁打)
2024年 133三振(120試合/16本塁打)
今季の佐藤はルーキーイヤーに並ぶ自身過去最多ペースで三振を喫している計算になる。その一方で、本塁打もキャリアハイを大幅に超えるペースで量産している。
このことからも、佐藤にとっては「三振」が決してネガティブなモノではないことがわかるはずだが、日本球界はこの「三振」を嫌がる傾向にある。フェアゾーンに打球を飛ばしさえすれば、快心の当たりではなくとも、たとえば相手のエラーがあったり、野手の間に打球が落ちたりしてヒットになる可能性が生まれるが、三振にはそれがない。見栄えの悪さも相まって、三振が多いとどうしても批判の対象になりがちだ。
ただその一方で、三振数の多さは「スラッガーの証」という見方もできる。たとえば、ドジャースの大谷翔平。昨季はシーズン54本塁打で本塁打王を獲得したが、同時に162三振を喫している。昨季までのメジャー通算7年間で860試合に出場しているが、225本塁打を放った一方で三振数は試合数を大きく上回る917。
日本のプロ野球を見ても、通算三振数の上位には球史に名を刻む長距離砲たちが名を連ねる。その中でも、三振数で堂々の歴代1位に座る中村剛也(西武)からは、過去にこんな話を聞いたことがある。
「基本的に、すべての打席で本塁打を打ちたいと思っています。ただ、それが狙えるボールが来ないこともたくさんある。それで結果的に三振したり、凡打になることもあるけど、それは別に仕方がないことです」
中村も大谷も、打席で三振を喫しても見ている側が肩透かしを食らうくらい、あっさりとベンチに引き下がる姿が印象的な選手たちだ。