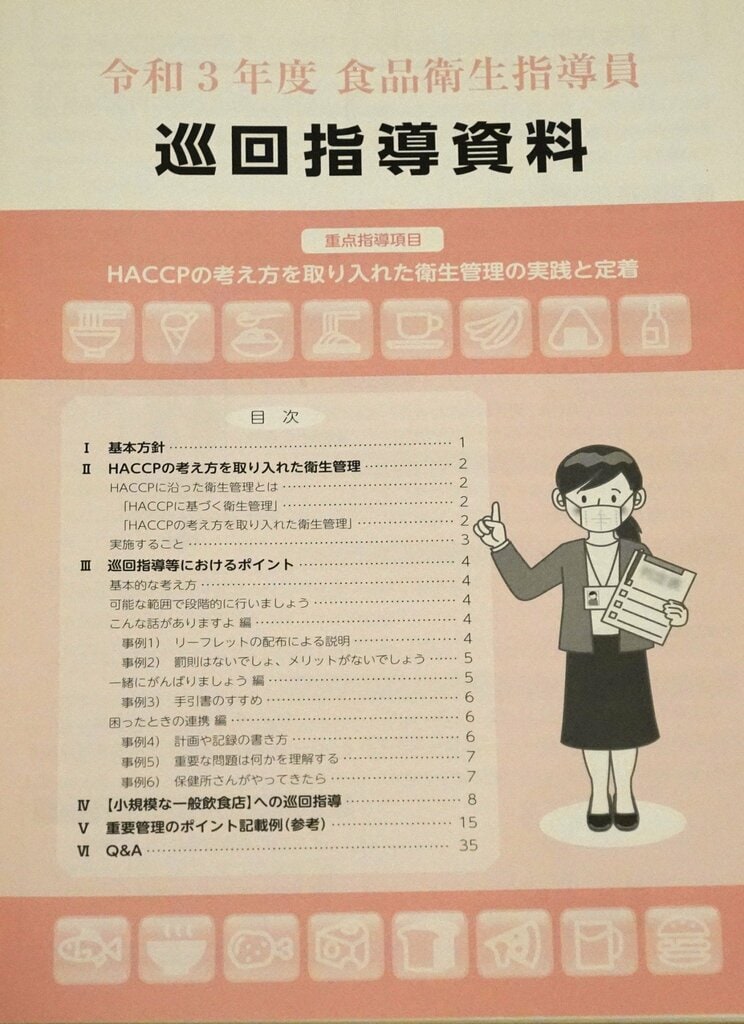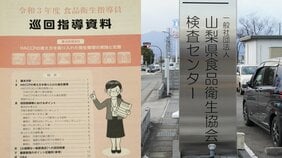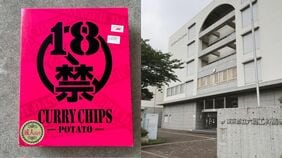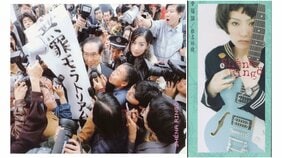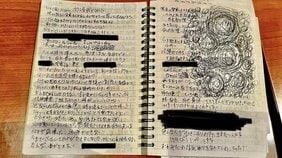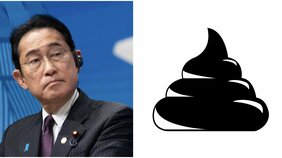「細菌検査の技術を持つ人はおらず検査は今も行なわれていません」
飲食業界では1947年に食品衛生法が制定され、翌年に「行政に協力し自主衛生管理を実施する」ことを目的にした日本食品衛生協会(日食協、現在は公益社団法人)が設立された。厚生労働省の外郭団体で最大の業界団体だ。
日食協には支部として都道府県や大規模市ごとに59の一般社団法人の食品衛生協会が置かれている。山梨県食協はその一つだ。さらにその下に各保健所単位で任意団体の地区食品衛生協会が全国で700弱存在する。
組織構造としては、上から日食協ー県食協ー地区食協という形だ。
この巨大なピラミッド型組織は全国130万余りの飲食関係の事業者の会費や事業収入で運営されている。日食協や各都道府県は山梨県食協など各県食協に補助金を出し、県食協から地区食協にも補助金が支給されている。
その日食協が「食品衛生協会活動の中核」と位置付ける根幹事業が、1960年に制度が作られた食品衛生指導員による衛生管理だ。
指導員は日食協の定めるカリキュラムによる指導員養成研修(講習)を受講した人に委嘱され、現行の講習は関係法令や食中毒事例の紹介など5科目計4時間の講習と、細菌や異物検出検査など3項目の実習を定めている。
「以前は講習は2日間にわたって行なわれました。でも、それだと時間がかかり負担が大きいとの声があったために簡素化され、今は1日で終わります」(日食協の担当者)
Aさんが言う、まともに行なわれなかった養成講習とはこれを指す。
「講習はいつから行なわれていないのかもわかりません。そんななか、昨年1月と2月に2回の講習が実施されました。でもその時も肝心の検査実習はなく、以前からの指導員はその講習も受けていません。ですから店舗巡回時の細菌検査の技術を持つ人はおらず、検査は今も行われていません」(Aさん)