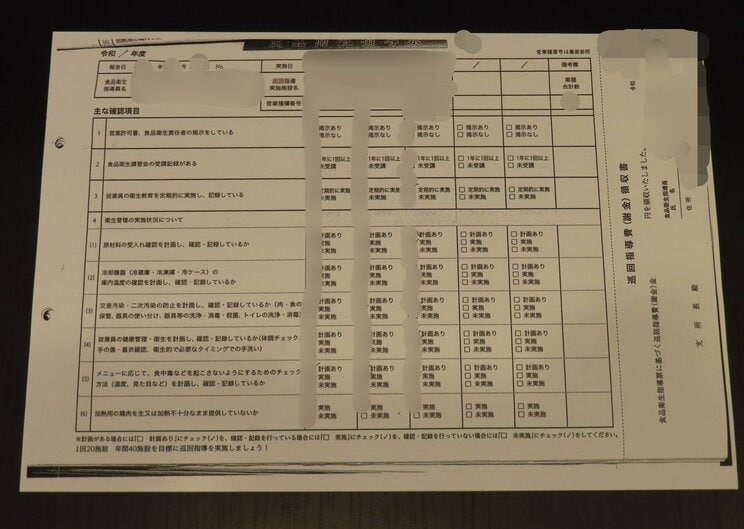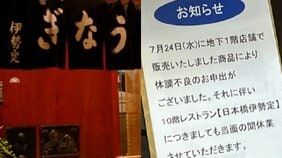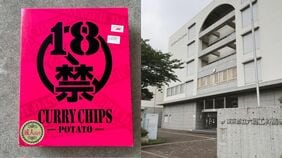「なり手不足もあって講習が“簡素化”された」
日本食品衛生協会が定めた要綱では、食品衛生指導員になるには都道府県単位の地区食品衛生協会の会長が「指導員としての資質が十分あると認める者」が養成講習を受けた上で、地域ごとに委嘱を受ける。
だが山梨県内の地区食品衛生協会で長年幹部を務め指導員活動をしてきたD氏は候補者探しの苦労を話す。
「もう話が逆なんですよ。指導員は今、高齢や体を悪くして抜けた人の埋め合わせができないんです。探して(引き受けるよう)お願いをして、一応、食協がみてから、よければ大体委嘱するんですよ」(D氏)
山梨県食協のX専務理事は、指導員の委嘱は地区の食協に任せていたので実態は「わからない」と説明した(♯1)。だが、なり手不足もあって講習が“簡素化”された可能性は認めた。
「日食協から(講習は)『できる範囲でいい』って聞いてるんです。指導員のなり手がないんで、逆に言うと、ぜひなっていただきたいというのが正直なところです」(X氏)
日食協によると全国の指導員は約4万人で、10年前から1万人減っている。山梨県内では約500人が登録されているが、これは「10年前の半分」(X専務理事)だという。5つあった県内の地区食協の一つは昨年解散した。ただ、山梨県内では10年よりもはるかに昔から養成講習が行なわれなくなっていたとみられている。
特にカリキュラムにある細菌を検出する「簡易検査実務研修」など3種類の実習が行なわれたという証言は、20年以上指導員を経験した人からも出てこない。
X専務理事は「日食協から『巡回指導の時にすればいい』って教えてもらったんで、巡回指導で先輩と行けば教わったでしょっていうスタンスでやってきたと理解しています」と説明する。
だが検査実習を受けた指導員自体がいないため、巡回指導の現場で後輩に教えることもできないはずだ。
指導員には検査技術が本当に必要なのか。技術を持たないと実害があるのか。日食協は検査技術を習得する必要性をこう説明する。
「指導員たるや、せめてこのくらいのこと(検査)はできるようにしておこうということです。(検査をした)その場で(細菌の)数値が出るので(飲食店の衛生管理の)意識づけには有効だと聞いています」(日食協担当者)