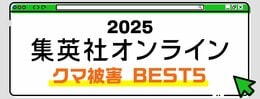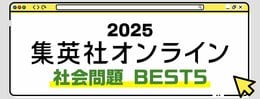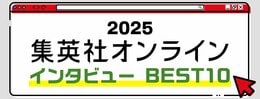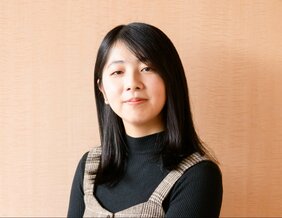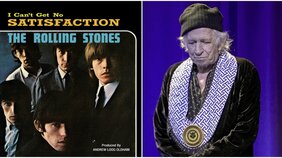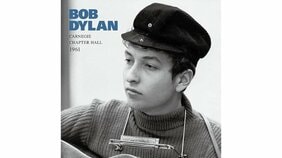残虐さへの自覚
岸本 もうすこしラロロリンの差別のことを教えてください。この差別構造が現実世界で何に相当するかを考えましたが、あんまり考えても意味がないのかもしれません。人種差別、容姿差別、年齢差別、職業差別の全部です。そんな差別の嵐の中でレナの自殺が描かれ、「ラロロリン・ガール・ラブ」という映画が製作される。人々は、他人の不幸を娯楽として消費し、安直に感動を得ています。
村田 楽な場所から見て、勝手に感動して消費する「感動ポルノ」の仕組みは書いておきたかったです。感動は、うまく言えませんが、快楽なので怖いんです。ドラマや映画で戦争とか原爆が描かれたときに、悲劇的なシーンでちょっと興奮していた人たちのことも思い出します。不幸の盛り上がりを欲するというか。これは自分の残虐さの認識にもつながります。
――明人が加害性を持つのに被害者面をしているというだけではなくて、被害者が自身の内なる加害性を自覚する、他人の不幸を快楽として搾取してしまうという反転は、この作品に通底する大きなテーマですね。村田さんの作品では、『新潮』に寄稿された「平凡な殺意」というエッセイにもそれが明確に見えます。かつて編集者から強烈なダメだしを食らった際、希死念慮とともに、相手への具体的な殺意、加害の欲望に襲われたことを告白する内容です。
村田 その体験もひとつのきっかけとなり、ありとあらゆる加害性について考えています。加害者の被害性にも被害者の加害性にも興味があって、幼少期は自分を被害者としか思えなかったけど、百パーセントそうであることはないなと。
岸本 加害者を悪人として切り離せないからしんどい。それもあってか、この作品の人物たちはみんなどんどん疲れていきますよね。第二章の終わりで「リセット」が起きて、第三章では世界がクリーンで優しくなり、ちょっと死後の世界のようになるんですが、これはこれで地獄みがある。とくに空子の友達の白藤さんは、自分の清らかな正義感で疲れています。
村田 第三章は、幼少時からいつも子宮を見張られていることに対する違和感を書きました。小学生のときから親戚に「沙耶香ちゃんは安産型ね」と言われたりしたあの気持ち悪さです。ピョコルンが子宮を見張られる役を代行してくれる。でも楽にはならなかったんです。
岸本 そもそもピョコルンは、生身の女性から、愛玩の道具、家事、恋愛、生殖、育児といったものをアウトソーシングした存在です。この思考実験はどんなふうにして生まれたんでしょう?
村田 ピョコルンが子を産むかは確定させずに書き進めました。性欲処理の家畜として女性がいた時代から、さらにその下の階層にピョコルンを置いてみたらどうなるかというものです。女性たちがその生き物をどう扱うのか、水槽で実験して書き起こしました。
岸本 空子は自身に性欲がないから、明人の性欲がピョコルンに向かって楽になるのかと思いきや、そこで留まらない。人間は自分よりさらに下位の存在ができたとき、容易に加害の側にくるっと変わるんだなと思いました。差別意識の複雑さが露呈します。空子のなかに明人性が生まれるというか、残虐さがちらつきますね。
村田 自分でもぞっとしました。空子がされて嫌だったことを彼女もまたしてしまう。こんなこと言う人だったのかと発見がありました(笑)。でもこれは自分のなかにもあるんです。私の性欲はわりと二次元に向かっているところがあります。十年ほど前、普段はフェミニズム的な思考の女性たちが、三次元の若手俳優さんたちに対して、「ビジュ落ちたよね」と言い、年配の方が画面に出てきたら、「クリーチャーだ」と言っていて、激しくショックを受けたことがありました。二次元でもその暴力性を自覚するようになりました。
岸本 二次元に対しても「作画悪いね」と言うことに罪悪感を持つ?
村田 はい。二次元だから軽く言えたり、欲望のまなざしを向けていることの罪悪感が軽減されていることも、怖いなと思います。消費の嗜虐性は常に考えます。自分がそうである自覚と、人の姿を見てぎくっとすること。とくに人の振る舞いはすぐ発見できても、自分の嗜虐性には口がもごもごする卑怯な感覚は反省する一方で大事にしたいです。
――本作には、家や学校、職場の光景に現代日本を想起させる生活のディテールが書き込まれています。一方で、法や議会制民主主義の意思決定が描かれない。統治の概念がないままに、いつの間にか世界が変容して空子はのっかっているだけに見えます。
岸本 一回だけ投票の話がありました。正義漢の白藤さんにうるさく言われるから、投票所に行って白票を投じると。この世界に選挙あるんだ! って思いました。
村田 日本だと政治の話をしなくともコミュニティが成立し、もっとがっと話したければそういうコミュニティに参加しますよね。ミュージシャンが政治の話題になるとSNSのアカウントを分けてとファンに言われたり。ところがスイスに滞在したり外国人の友人と話したりしていて分かったのですが、日本の政治の話のされなさはすごく不思議なようです。日本では政治の話をしないと、関係は表面的には穏やかになる。海外の文学フェスに行くと政治的な質問をされますが、日本のインタビュアーにはお散歩が趣味なんですかというようなことも聞かれます。どちらが好きかというと分からないのですが、このギャップは興味深いです。
岸本 作中には外国を表す言葉として「ウエガイコク」「シタガイコク」というのがありましたね。作中人物たちはそれらを自然に使い分けて、移民差別を表面化しています。
村田 政治や差別の構造については、無関心を決め込んでいる人というより、気付いてすらいない層を描きたかったんです。この世に政治という仕組みが存在していることや差別思想に根拠がないことに、ナチュラルに気付いていない人はいますよね。
岸本 きっとそれがリアルですね。第二章で空子は、世界①、②、③を使い分けます。①の人たちはいわゆる一般大衆で陰謀論にはまりやすい。世界②の人たちは快楽的で勝ち組です。③の人たちだけが政治的なんだけど、めちゃくちゃしんどそう。
村田 私も作家をやっていると、世界③の人と多く話します。でも①の人も②の人も世界には多い。あとは世界④のような、ネガティヴなことを話さない、癒しのコミュニティで会話することもあります。
岸本 しかもまだ私たちの知らない、世界マルいくつがあるわけでしょう。
村田 空子はそれらをあちこち行き来するので、変な主人公でした。
岸本 でも考えてみれば誰でも二つ、三つは行き来していますよね。たとえば編集者の人と話すときと中学の同級生と話すときと美容院に行くときでは、やっぱりちょっとモードが違う。だから空子という存在がどんどん自分に近しく思えてくるのが面白かったです。
――かつて、二一人ものラロロリン人が殺される「お台場惨殺事件」が起きたんですよね。それをラロロリン人権の日としていたのが、いつの間にかピョコルン人権の日に変わって、つまり「慰霊碑」が「人権記念碑」にすりかわり、いまや誰もそのことを覚えてないというエピソードがありました。
村田 怖かったです。自分で書いておきながら怖かった。私は自分がコップのようなものと思っていて、いつの間にか中身は入れ替わり、粒子も変わり、いまと二十年前、二十年後はぜんぜん違う考え方かもしれないんです。でもそれを忘れて、0歳からこうでしたみたいな顔をする自分もいる。価値観のアップデートなんだけど、プロセスを忘れていることが怖いんです。
岸本 「記憶喪失」という言葉も出てきますね。
村田 記憶を喪失して別の人間のようにふるまうのはいいとして、同調圧力に屈して無意識で変わったふりをしているだけかもしれません。
岸本 村田さんは本能もまた変わってしまうとこれまで書いてきました。「生存」(『信仰』に収録)では猫とゴキブリと人間しか生き延びていない世界で何を食べるかの本能が描かれます。どっちも嫌だ。
村田 どっちも食べたくないですよね……。
岸本 今作でも世界③の人々は、食欲という本能を変えてしまいます。「サラー」という、汚染物質から作ったものを摂取する。理念のために自身の体をフィルターにして、ナウシカの腐海みたいに無毒化しようとする。しかしサラーはまずそうですね。
村田 粉末ですしね。