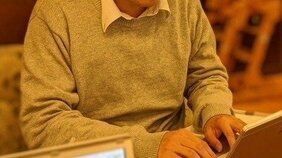満場の観客を集めたゴールドカップ
そして迎えた2002年8月。ゴールドカップの開会式で関係者全員が驚く事態がおきた。会場となった北九州市内の体育館に大会初日から次々と人が押し寄せてきたのだ。しかも、観戦した人がさらに口コミで「面白かった」と伝え、連日満員に。
予想外の観客数に大会運営スタッフは対応に追われながらも、終わってみると10日間の大会でのべ約8万人が参加し、大成功に終わった。そして、北九州市はゴールドカップの成果を継承することを決定し、2003年から「北九州チャンピオンズカップ国際車いすバスケットボール大会」が開催されることになった。
小学生に車いすバスケを本格的に教えるようになったのもこのころだった。2003年の第1回のチャンピオンズカップから、小学生はエキシビジョンマッチとして参加していたが、当時の子どもたちは大会当日の1時間の練習だけで試合に出場していた。
それが、子どもたちが真剣に競技をする姿を見て、「もっと本格的に車いすバスケを教えよう」となったという。それまで足立クラブのメンバーを中心に学校訪問を重ねていたこともあって、車いすバスケに興味を持ってくれた校長や教頭、クラス担任の先生たちが後押しし、アレアスから指導者を派遣して子どもたちに車いすバスケを教える形式になった。
それが、小学生5年生が参加する「北九州市小学生車いすバスケットボール大会」に発展し、2006年に第1回大会が開催された。
「最初は小さく始めたのですが、試合に負けると子どもたちがあまりにも悔しがるし、先生もそれを見て熱くなるんです。一度参加した先生が、別の学校に異動して5年生の担任になると『車いすバスケをやりたい』と手をあげてくれるようになって、広がっていきました」
車いすバスケの授業が教えてくれること
北九州市には126の小学校があるが、参加できるのは5校のみ。アレアスが所有している競技用車いすが50台で限られていて、競技を指導できるスタッフや予算も限られているためだ。そのため、毎年、抽選で参加校を決めることになっている。
練習も兼ねた車いすバスケの授業は、車いすユーザー以外の障害者への理解を促すことにもつながっている。
現在の小学校では以前に比べてインクルーシブ教育が進んでいるため、障害を持つ子どももクラスの中でできるだけ一緒に授業を受けることが多い。本番の大会では、決勝以外の試合では選手全員が1度はゲームに出場することがルールだ。
だからこそ、子どもたちは障害がある人でもゲームの中でどうやったら活躍できるかを考えて、作戦を立てなければならない。例えば、シュートを打つのが苦手な子どもなら、自陣のゴール前で待ち伏せをして、相手チームの選手がディフェンスを突破してゴール前にきたら、全力でボールを奪いに行くことに特化する。
シュートのタイミングを少しでも遅らせることができれば、ディフェンスの陣形が整うまでの時間稼ぎができる。それぞれが得意なことを活かし、不得意な部分をチームで支え合うことが、この大会の見どころだ。
だからこそ、眞鍋さんは練習の時に子どもたちに何度も「思いやり」という言葉を投げかける。人にやってもらってうれしいことを自分もやり、やられて嫌な思いをしたことは自分も人に対してやらない。勝敗を超えてそのことを学べることに、車いすバスケの価値があるという。
「大会が終わると、先生たちから『バラバラだったクラスが一つにまとまりました』という声が、たくさん届くんです。もちろん、知的障害の子だと、ルールを覚えることが難しい子もいます。でも、その子たちもみんな一緒になって仲良く体を動かして、楽しく過ごすことができたなら、それが最も有意義なことなのだと思います」
東京パラリンピック開催を契機に、国はパラスポーツの認知向上のために広報や選手強化のための支援制度を強化した。
その成果は、パリ・パラリンピックで東京大会を上回る14個の金メダルを獲得できたことにつながった。しかし、東京大会終了後に、パラスポーツの普及や、社会全体での障害者の受け入れが大きく進んだわけではない。
今でも車いすユーザーが体育館でスポーツをしようとすると「床が傷つく」という理由で使用を断られることが多いという。その障壁を解決するためにも、北九州小学生車いすバスケットボールのような大会が、全国に広がればその意義は計り知れない。
写真/越智貴雄[カンパラプレス]・ 文/西岡千史