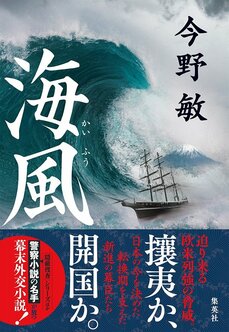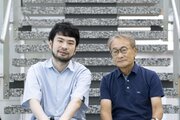したたかでなければ続かない
長崎での人間ドラマ
――永井は優等生ですが、岩瀬のような天才肌ではないし、堀のような豪胆さというか、力強い感じでもない。〝普通の人〟に近い人物ですね。
幕臣としては卓越した仕事をした人で、『海風』のその後の時代にも活躍した人なんですよ。ただ、物語の視点人物はあまり個性がないほうがいいんです。そのほうが読者が物語に入っていきやすいので。その代わりに周りに面白いやつを配置しておかなきゃいけない。水野みたいに一癖も二癖もある人物とかね。
――長崎奉行の水野忠徳ですね。永井が目付として外交の最前線である長崎に赴任すると、木で鼻をくくったような対応を取ります。そうかと思うと永井をこき使ったり。
ああいう人だったらしいです。小説ですから、キャラづくりはしていますけどね。調べてみたらあの人はキャリアが長いんですよ。長いこと幕府で働いていますから、ああいう清濁併せのむタイプだったんじゃないかなと思いますよね。
――したたかでなければ長くは続けられないんですね。「濃い」キャラの水野とは対照的に、もう一人の長崎奉行、石見守(荒尾成允)はすごく存在感が薄いという設定で、とぼけたやりとりに笑ってしまいました。
ああいうクセのある人を長崎で活躍させたかったんですよね。花魁の浮舟大夫とかもそうですね。
――長崎の場面では、通詞(通訳)の描写が面白かったですね。英語ができないから、オランダ語を挟んで訳すとか。通詞にもランクがあったそうですね。
大通詞、小通詞、稽古通詞がいました。大通詞が一番しっかりした通詞で交渉ごとの通訳を務めたのですが、それだけではなく、西洋人の身の回りの世話や、食事にまで気を配らなくてはいけなくて、大変な仕事だったらしい。そういう人たちの中には半分スパイみたいなことをやってる人もいたみたいです。そうかと思うと大通詞の話すオランダ語が古過ぎて分からないと言ったアメリカ人がいたり。
――日本語の訳がやたら大仰で、永井が戸惑うというエピソードもありましたね。
通詞といっても、今みたいに学校でオランダ語を教えているわけじゃない。通詞は家業として、代々、伝えていくスタイルなので、それはどうしても古くなりますよね。
でも、書いた私が言うのも変なのですが、よくあんな難しい交渉事を、そういう通詞でやれたものだなと思いますね。実際に交渉の現場を見てみたかった。どんな雰囲気でどんなことを話したのか。精いっぱい想像して書いたんですけどね。
――長崎に取材に行かれたそうですね。
行きました。当時からある老舗の料亭に行って食べてきましたよ。作中にも出てきた和華蘭料理を。
――「日本風の和、清国風の華、オランダ風の蘭で和華蘭」と本文にありますね。お店も実在するんですか。
「一力」というお店です。有名なお店なんですよ。
――実在するといえば、歴史小説は史実に基づくことが原則ですよね。やはりそこに苦労されましたか。
そうですね。調べながら書くのがしんどかったですね。長崎のことも登場人物を生かしてもっと書きたかったんですが、今のキャリア官僚と同じで、幕臣も異動が多いんです。二年ぐらいで異動するのは今とまったく変わらない。長崎奉行も一年ぐらいでころころ代わっちゃうので、面白いエピソードを思いついても「あ、あの人もう異動になってる」みたいなことの連続でしたね。
誰がどこにいるかを調べるのも大変で、うっかりすると「せっかく書いたけどこの人、今ここにいないわ」みたいなことが起きるんですよ。たとえば、交渉相手になるオランダ船の艦長、ファビウスがどこにいるのか。ずっと長崎にいるわけじゃなくて、気がついたら函館にいたりする。ファビウスと永井が長崎で話をしている面白い場面が書けたと思ったら、実はその時、彼は下田で岩瀬と会っていたという史実がわかって慌てて書き直す、そんなことの連続でした。
――同じ歴史小説でも琉球空手の名人たちを描いた作品とは苦労の度合いが違いますか。
そうですね。琉球は狭い島の中で起きていることなので、誰がどこにいたということでは、そんなには齟齬が起きないんですよ。琉球の王朝の仕組みを調べるのは大変でしたけど。
幕末の幕臣に見る「本物の官僚」とは何か
――意外だったのは、江戸幕府もかなり海外の事情をよく知っていて、しかもそれが漢籍から得た情報だということ。西洋事情を知っていたからこそ、危機を感じていたということがよく分かりました。
漢文で書かれたものが日本に入ってきていたので、漢学者は西洋の事情に詳しかったようですね。幕府が一番頼りにしていたのは長崎のオランダ商館長に書かせたオランダ風説書なんですけど、それも漢文に訳されたものを漢学者が読んでいたそうです。
――薩長史観だと、薩長が幕府よりも外国のことを知っていたみたいな感じで描かれていたりしますが。
実態は逆ですよね。幕府が一番知っていて、薩摩・長州にはあまり情報がなかったんです。知らないから攘夷、攘夷と騒いだわけです。それに比べたら、幕府が持っていた情報量にはすさまじいものがあって、長崎を通じて西洋人のことも知ってますし、ロシアの動きもちゃんと知っている。あの時代の外交を描くには幕府の動きは不可欠なんです。
――長崎では、地元で採用した「地役人」が重要な働きを担っている。もともと町人だった人を武士として使っているわけで、幕臣たちは現場でかなり柔軟に動いていたんですね。
人材不足だったんだと思います。長崎の事情を知っている人を使うしかなかったんですよね、多分。
――現場で官僚たちが知恵を絞って融通無碍にやっていたということですね。
そうだと思いますね。いきなり海軍の伝習所をつくれと上から言われても、何から手をつけていいか分からないですよね。でも、永井たちはそれをやりおおせてしまうわけです。海軍の士官を育てて、数年後には咸臨丸で太平洋を越えてアメリカまで行ってしまう。すごいことですよ。
――永井は水野に、製鉄所を併設した造船所もつくれとむちゃぶりされますしね。
伝習所の運営に責任を持つ「伝習所総督」という役職にあったとはいえ、独断で製鉄所のための建設機械や資材を発注していますから、決断力が半端じゃないですよね。おかげでその時の長崎奉行の不興を買うんだけど。
――その時に永井がつくった長崎造船所がのちに三菱重工業長崎造船所になる。日本の近代化に大きな貢献をするわけですよね。でも、永井尚志の名前はあまり知られていません。
永井も知られていないし、横須賀に製鉄所、造船所をつくった小栗上野介(忠順)も知られていない。小栗は本当にすごい官僚だったんですよ。江戸幕府の財政を立て直し、西洋式の軍隊を整備して、製鉄所と造船所をつくったんだから。
――小栗は永井のさらに一回り下の世代なんですね。当時の江戸幕府は、優秀な若者たちが国の危機に立ち向かった。若者たちはなぜあんなふうに前例がないことをできたんでしょうか。
なぜでしょうね。官僚ってふつう、前例のないことはやりたがらないものなんです。でも、本物の官僚はきっとそうじゃないんでしょう。国にとって必要なことをしかるべき時にする。それが官僚なんだということもこの小説で書きたかった。どんな時にも合理的に考えて、国にとって一番いいことを進めていくのが官僚であるべきなんです。永井たちがやったことはそういうことだったと思います。